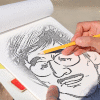| ���C���g�o�ւ��ǂ� | ���y�Ǝ��s�n�o |
|

|
||
�אl�͐��W�����̉��q�������y�P�z �����b�l�͐��c�p�O�Y�������� �@���͍K�^�ɂ��A�I�|�X�g�����A�̃����{������w�Ƃ����Ƃ���ŁA��w�𑲋Ƃ������ƁA���� �����𑗂邱�Ƃ��ł����B �@���b�l�ɂȂ��Ă����������̂����c�p�O�Y���B�c�@�É��̕��N�ł���B �@�������Ŏ��́A�Ƃ�ł��Ȃ����E�i�H�j�ɑ��ݓ���Ă��܂����B���̐Q���肵���A�C���^�[ �i�V���i���E�n�E�X�́A�e���̍c���≤���̎q������B���W�����̉��q��|���V���X�̍c ���q�B�i�C�W�F���A�̉����̑��q�ɁA�}���|�V�A�̑呠��b�̑��q�ȂǁB�x�l�Y�G���̐Ζ��� �̑��q�������B �@�u���̍��̕����ŁA���������Ă���v�Ɨ��Ƃ��A���W�����̉��q�͂����������B�u�C���h �l�V�A�ꂩ�A����Ƃ��Ƒ��̕������v�ƁB �@�u�Ƒ��̕����v�Ƃ����̂ɂ́A�������B�����ɂ͉��������g��Ȃ������Ƃ������̂��������B �܂��u�}���|�V�A�̂��D�ɂ́A����Ԃ����̂��₶�̃T�C��������v�ƕ������ꂽ�Ƃ��ɂ��A�� �����B��l���O�͏o���Ȃ����A���`�}�t�B�A�̐e���̑��q�������B�u�s���L�[�ƃL���[�Y�v�i�� ���̐l�C�̎�j�����`�Ō��������Ƃ��̎ʐ^�������A�u���ɗ����Ă���̂��Z���v�Ə����B �@���x�͎��̔ԁB�u���܂��̂��₶�́A�������Ă��邩�v�ƕ����ꂽ�B�����Łu���]�ԉ����v�Ƃ� ���ƁA�u���{�ň�ԑ傫�����]�ԉ����v�ƁB�����u����A�c�ɂ̎��]�ԉ����v�Ƃ����ƁA�u�r���� ���K���Ă��v�u�Ԃ́A��������Ă��邩�v�u�]�ƈ��̐��͉��l���v�ƁB ���}�_���E�K���W�[������Ă��� �@����Ȃ킯�Ő��E�e������v�l������ƁA�K���������̃n�E�X�ւ���Ă��ẮA�[�H���� �ɂ��A�X�s�|�`�����ċA�����B��Ǎ��n�C�W���b�N�����ŁA�k���N�ɓn�����R�������������A�� ���̎��ɘA����Ă���Ă������Ƃ�����B �@�R�����͂��̎����̂��ƁA�x�ɂ��Ƃ��āA�����{�����ɗ��Ă����B���̑O�N�ɂ̓}�_���E�K ���W�|���������A�w�T�|�x�̏̍������l�����A���T�̂悤�ɂ���Ă����B�C���h�l�V�A�̊C�R�� �����Ƃ��ɂ́A�㋉���Z�������o�X��A�˂āA���W�����̉��q�̂Ƃ���ցA�������ɗ����B ���̂Ƃ��͎��͔ނƕ���ŁA�Ōh�炷�镺���̑O��������ꂽ�B �@�܂��؍��̋��O����b�������Ƃ��ɂ́A�u��b���s�����Ɏv���Ƃ����Ȃ�����v�Ƃ������R �ŁA���͐Ȃ��͂����悤�Ɍ���ꂽ�B�����́A�܂������������ゾ�����B�ς�����l���ł́A�g ���C�E�h�i�q���|�Ƃ����f��X�^�|�����āA��T�ԂقǐQ�H���Ƃ��ɂ��Ă��������Ƃ�����B�w���| �g�U�U�x�Ƃ����f��ɏo�Ă������A���ł͒m���Ă���l�����Ȃ��B �@���������A����Ȃ��Ƃ��������B���܂��܃~�X�E���j�o�[�X�̈�s���A�J�Í��̃A���[���`���� ��̋A�蓹�A�������̃n�E�X�ւ���Ă����B�����ă_���X�p�|�e�B�������̂����A���鍑�̉��q �����{��\�́A�W�����R�Ƃ��������ɁA��ڍ��ꂵ�Ă��܂����B�ŁA�ނ̂��߂Ƀ��u���^�|���� ���Ă�����̂����A���̂���ɂƁA�ނ��ނ̍��̃~�X��\���A���ɂ��ꂽ�B �@�u���ꂽ�v�Ƃ������������ւ��A���������悤�ȁA�����������B���̍��ł́A�ނɂ����炤 �l�ԂȂǁA�N�����Ȃ��B�����炦�Ȃ��B�������Ŏ��́A�I�|�X�g�����A�֒����Ă��炷���ɁA�� �炵�������ƃf�[�g���邱�Ƃ��ł����B����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł��悢���A���̂Ƃ��̃W�����R�Ƃ� �������́A��ɑ勴����Ƃ����^�����g�ƌ��������ƕ����Ă���B �@�c�c����Șb�����A���Ă��A�N���u�z���v���Ǝv���炵���B���������v����̂�����ŁA�߂��� �ɂ��̘b�͂��Ȃ��B���A���̐��ɂ��s�v�c�ȗ��w����́A�������Ďn�܂����B��㎵�Z�N�� �t�B���̂�����{�̑��ł́A�������n�܂낤�Ƃ��Ă����B �����Ɠǂ�ł���������́c�c�� |
|
||
���O��N�ڂ̖� ���傤�ǎO�\��N�O�̑��ƃA���o���ɁA���͂����������B �u��Z�Z��N�ꌎ����A�ߌ�ꎞ�ɁA�i����́j�ΐ��̑O�ŌN��҂v�ƁB ������������Ƃ��A���͔��Ώ�k�̂��肾�����B�����̎��͓�\��B���傤�ǃA�[ �T�[�E�N���[�N����́u��Z�Z��N�F���̗��v�Ƃ����f�悪�b��ɂȂ��Ă�������ł��� ��B���ɂƂ��ẮA�O�\��N��̎����Ƃ����̂́A�F���̗��Ɠ������炢�A�u���肦�Ȃ��� ���v�������B �@�������A���̎O�\��N���߂����B�ꌎ����ɋ���w�ɂ��肽�ƁA�̂�˂��h���悤 �ȗ₽���J���~���Ă����B�u�~�̋���͂����������v�ƌ����ƁA���[���̂�k�킹���B�� ����A�����̎v���o���ǂ��Ɠ��̒����P�����B�b���������Ƃ͂����ς�����͂��Ȃ̂ɁA ���t�ɂȂ�Ȃ��B�ׂ��H�n�������������āA�₪�ċߍ]���s��̃A�[�P�[�h�ʂ�ɏo���B �����Ȃ�C�Y���邨�₶�̐��ŁA�ɂ��₩�ȂƂ��낾�B���A���̓��͋x�݁B�u���� ��͌ܓ�����v�Ƃ������莆���A����߂����B�J�j�̏L���������A�����@�������B �@�����̏������������A�C�ɂȂ�n�߂��̂͐��N�O���炾�����B����܂ŁA�A���o���� ���邱�Ƃ��A�قƂ�ǂȂ������B�������̖{�I�̑O�ŁA����t�̋������͂��āA�w�ґR�� ���Ďʐ^�ɂ����܂��Ă��鎩�����A�ǂ������₾�����B ��������Z�Z��N���߂Â��ɂ�āA���̓������̐S�ɏd���̂�������悤�ɂȂ����B �A���o���Ƀ����������������u������v�Ƃ���Ȃ�A���̓��́u�o���v�Ƃ������Ƃ��B�� �����U��Ԃ��Ă݂�ƁA���̓�����Əo�����A��̃h�A�ł����Ȃ��B���̊Ԃɖ����̎v ���o������͂��Ȃ̂ɁA���ꂪ�Ȃ��B�l���Ƃ��������ɓ����Ă݂���A���������̂܂o ���������B����Ȋ����ŎO�\��N���߂��Ă��܂����B �@�u�ǂ����Ă��Ȃ��͋���֗����́H�v�Ə��[���������B�u�c�����ɑ���ӔC�̂悤�� ���̂��v�Ǝ��B���̃������������Ƃ��A�S�̂ǂ����ŁA�u��Z�Z��N�܂Ŏ��͐����Ă��邾 �낤���v�Ǝv�����̂��o���Ă���B���A���̎��������Ă���B�����Ă����B���̗���́A ���ɔ������A�����Ď��ɕ��߂����B �t�����X�̎��l�A�W�����E�_���W�[�́A���Ă����̂����B�u���l������āA�܂�����c�v �ƁB �����I�ɂ����o���Ă��Ȃ����A������߂͂����������B�u�����Ď��́A���Ȃ��́A�� �́A�ޏ��́A�����Ĕނ�̐l���������B�������������Ƃ��Ȃ��������̂悤�Ɂc�v�ƁB �����������悤�ŁA���ǂ́A���͉����ł��Ȃ������B���̗���͕��̂悤�Ȃ��̂��B�� ������Ƃ��Ȃ������Ă��āA�܂��ǂ����ւƋ����Ă����B���ނ��Ƃ��ł��Ȃ��B������ �Ǝv���Ă��A���̂܂w�̊Ԃ���R��Ă����B �@���ꌎ������A������݂���܂���̌������J���~���Ă����B�������͌��Z���̒ʂ� �ɂ��钃���Œ��H���Ƃ�A�����Ĉꎞ�����O�ɂ������o���B���A�������o��ƁA�J����� �ł����B��������ΐ��܂ł́A�����Đ������Ȃ��B �����āA�������͐ΐ��̉��ɗ������B�u���A�������v�ƕ����ƁA���[�����v�����Ȃ��� �u�ꎞ��c�v�ƁB���͂�����x�ΐ��̉��ő����ӂ���Ă݂��B�u�����ɗ����Ă���v�� �����������ق��������B �w������A�l�N�Ԓʂ蔲�����ΐ�傾�B�ƁA���̂Ƃ��A���̒��قǂ����l�̒j���� �Ȃ������Ă���̂ɋC�������B�����ɂ����납�琺��������j�������B����ɂ����� �l�c�c�I�@ ���̂Ƃ���A���̖ڂ���A�Ƃ߂ǂ��Ȃ��܂����ӂ�o�����B |
|
||
�i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j �����b�g�E�C�b�g�E�r�[ �@�v�����āA�Ȃ�����B���̊ԂɎq�ǂ�������B�Ƒ��Ƃ����̂͂����������̂����A���̕v�ƍȂ����������A�M���������Ă���Ƃ����P�[�X�́A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǁA���Ȃ��B�ǂ̕v�w�����X�̐����ɒǂ��āA�����̋C�������m���߂�]�T����Ȃ��B �����A�w�q�͂��������x�Ƃ͂悭���������̂��B�u�q�ǂ��̂��߁v�ƍl���āA�K���ɂȂ��ĉƑ�����낤�Ƃ��Ă���v�w�������B���ʂƂ����Ή��ʂ����A�v�w�Ƃ����̂͂����������̂ł͂Ȃ��̂��B���Ƃ��Ƒ��l�̐l�Ԃ��A������̉��ŁA�P�O�N���Q�O�N���A�V�������̋C�����̂܂܂ł��邱�Ƃ̂ق������������B���̏��[�Ȃǂ��A�u���O�́A�I���̂��ƍD�����H�v�ƕ����ƁA�u�l�������ƂȂ�����A�킩��Ȃ��v�Ɠ�����B �@�c���������ƁA�Â��Ă䂤���ȉƑ������z�������������A�����ł͂Ȃ��B����ȕv�w������B��������鏗���i�S�O�j�����̉ƂɗV�тɗ��āA���[�̑O�ł����������B�u�o���U�[�C�A�������I�v�ƁB �����ƁA�v���P�g���C�Ŗk�C���֍s�����ƂɂȂ����Ƃ����B�ӂ��Ȃ�v�̒P�g���C��߂��ނ͂������A���̏����́u�o���U�[�C�I�v�ƁB�܂��ʂ̏����i�R�R�j�́A�v�w�ł��ʁX�̐Q���ŐQ�Ă���Ƃ����B���������N�Ɉ�x���邩�Ȃ����Ƃ������x�炵���B�������u�Ƃ��ɁA�l�����y����ł����B����ł����Ⴀ�A�Ȃ��H�v�ƁB���邭�������Ȃ��B �v�͕v�w�ɕW���͂Ȃ��Ƃ������ƁB�����悤�ɐl���ςɂ��ƒ�ςɂ��W���͂Ȃ��B�l�́A�l���ꂼ�ꂾ���A���ꂼ��̐l����z���B���₠�Ȃ��̂悤�ȑ��l���A����ɂ��ĂƂ₩�������K�v�͂Ȃ����A�܂������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���Ȃ��̗���Ō����Ȃ�A�l���ǂ��v�������A����Ȃ��Ƃ͋C�ɂ��Ă͂����Ȃ��B �@���͐e�q���B�������͂Ƃ�����A���z�̐e�q�W�̒��ɕ`���B���ꎩ�͈̂������Ƃł͂Ȃ��B���A���́u���v�ɔ�����̂͂悭�Ȃ��B����ɔ�����Δ�����قǁA�u�����łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��A�u����Ȃ͂��͂Ȃ��v�Ƃ������C���������B���̋C�������e���ꂳ����B�q�ǂ��ɂƂ��Ă͏d�ׂɂȂ�B�s�K�ɂ��ĕs�K�ȉƒ�Ɉ�����l�قǁA���̋C�������������璍�ӂ���B�u�悢�e�q�W��z�����v�Ƃ��������肪�A���ǂ͐e�q�W���������Ⴍ�����Ă��܂��B�����Ď��s����B �@�����łǂ����낤�B�����l���ẮB�܂�v�w�ł���ɂ���A�e�q�ł���ɂ���A���ꎩ�̂��u���z�v�ł���Ƃ����O��ŁA�l����B�������̒��Ɉꕔ�ł��A�{��������Ȃ�A���������́B�ꕔ�ł悢�B�����l����A�C����������B�u�v�w������c�v�u�e�q������c�v�ƍl����ƁA���Ȃ������邪�A�Ƒ�������B ��Ȃ��Ƃ́A��������̂��A���邪�܂܂Ɏ���Ă��܂��Ƃ������ƁB�u���������Ȃ����猋���������܂��v�Ƃ��u�e�q���f�₵������A�ƒ�Â���Ɏ��s�����v�Ƃ��A���������ӂ��ɑ傰���ɍl����K�v�͂Ȃ��B�܂�Ƃ���v�w��Ƒ��A����Ɏq�ǂ��ɁA���܂���҂��Ȃ����ƁB�قǂقǂ̂Ƃ���ŁA������߂�B ���������j�q���Y�������Ȃ��̐S�ɕ�����������B�����Ă��ꂪ�A�v�w��Ƒ��A�e�q�W�𐳏�ɂ���B�r�[�g���Y�����āA�����̂����ł͂Ȃ����B�u�b�g�E�C�b�g�E�r�[�i���邪�܂܂Ɂc�j�v�ƁB����͂܂��Ɂu�q�b�̌��t�v���B |
|
||
�i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j�i���y���A�N���b�N�j ��e���A�C�h�����O����Ƃ��@ ���A�C�h�����O�����e �@�������̑���Ȃ��B�ǂ����������āA���݂ǂ��낪�Ȃ��B���X�͕����ŁA����Ȃ�ɍK���̃n�Y�B���A���̎������Ȃ��B�q��Ă��킸��킵���B�����]�͂Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A���̏[�������Ȃ��c�c�B���A����ȏ������ӂ��Ă���B �g����i�R�Q�j���������B���������̂͂Q�S�̂Ƃ��B�ǂ����s�{�ӂȌ����������B����A�Q�O�̂���A��x�����d���ɑł����悤�ȗ����������A���̒j���Ƃ́A���ǂ͕ʂꂽ�B���̂��Ƃ��炭���āA���̕v�Ɖ��ƂȂ����ۂ��n�߁A���N��A����܂����ƂȂ����������B ���}�f�B�\���S�̋� �@ �q�E�E�H���[�́w�}�f�B�\���S�̋��x�̖`���́A����ȕ��͂Ŏn�܂�B�u�ǂ��ɂł�����c�ɓ��̓y�ڂ���̒�����A���[�̈�ւ̉Ԃ���A�������Ă���̐�������v�i����������j�ƁB��l���̃t�����`�F�X�J�̓L���P�C�h�Ɖ�A�����Ŕޏ��͓ˑR�̗��ɗ�����B�Y��Ă��������̋��тɂ��̐g���ł����B�ǂ��܂ł��������A�݂��Ɉ��������B �܂�t�����`�F�X�J�́A�u���ɓ��ɖ��_�o�ɂȂ��Ă������E�ŁA�����Ԃ����炯�̊��̊k�ɕ��������āv���������Ă������A�L���P�C�h�ɉ���āA��ς���B�ޏ����܂��A�u�i���́j���܂�I��D�݂��Ă͂����Ȃ��̂�F�߂�������Ȃ��v�Ƃ����̒��ŁA�A�����J�l�̃��`���[�h�ƌ������Ă����B ���s���S�R�ďnj�Q �@�S���w�I�ɂ́A�s���S�R�ďnj�Q�Ƃ������Ƃ��B���傤�ǐM���҂��Ŏ~�܂����Ԃ̂悤�ȏ�Ԃ������B�A�C�h�����O���肵�Ă��āA��i�܂Ȃ��B����܂����肷��B�g����͂��������s�������Ƃ̗��e�ɂԂ����B���A�u�킪�܂܁v�Ǝ���ꂽ�B�v�͕v�ŁA�u�����s�����v�u���O�͍K���ȃn�Y�v�ƁA����ɂ��Ă���Ȃ������B���������ꂩ���X�g���X�͑����Ȃ��̂��B �́A�������Ƃ�����Ƃ������B���̍�����������A�����z�n�̂���Z���^�[�������ƁA����Șb�����Ă��ꂽ�B�u�����͎Ⴂ����͏C�s���肵�Ă����B�t����͂���ŏI����Ă��܂����B�����獡�ł��A�w���܂����I�x�Ǝv���āA�x�b�h����ƂыN���A�����ɍs���v�ƁB �u�����v�ƌ����Ă��A�����̂����́A�G�̃��f���ɂȂ鏗�������߂�Ƃ������Ƃ������B�ӔN�̍����́A���̏����̊G�������Ă����B�ׂ����̂��Ȃ₩�ȃ^�b�`�̊G�������B���͍����́u���v�ւ̎����S�ɋ��������A�S�́u�����Ԃ��v�Ƃ����̂́A�����������̂��B���̐l�̐l���̒��ŁA���܂ł��d���A�S���ӂ����B ���v�����ăA�N�Z���� �@���A���������A�C�h�����O��Ԃ��甲���o�������������B�s����́A��l�̏��̎q���������A���̎q�����w�Z�֓��w����Ɠ����ɁA��|�̓X���o�����B�`����́A�v�̈�@����`�������A��Î����̒m����g�ɂ��A�₪�Ĉ�Î�����������u�t�ɂȂ����B�܂��m����́A�w���p�[�̎��i����邽�߂ɕ����n�߂��A�ȂǂȂǁB �u�����Ԃ����炯�̊��̊k�v���甲���o���A���H�𑖂�o�����l�͑����B�����獡�A���Ȃ����A�C�h�����O���Ă���Ƃ��Ă��A�ߊϓI�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B���̗���͕��̂悤�Ȃ��̂����A�~�܂邱�Ƃ�����B���������̂܂܂Ƃ������Ƃ́A�Ȃ��B �q��Ă���i������Ƃ�������B���̂Ƃ����V�����o���_�B�A�C�h�����O�����Ă��A���ꂪ�I���_�Ǝv���̂ł͂Ȃ��A���������_�Ƃ��đO�ɐi�ށB���@�͊ȒP�B�E�C���o���āA�A�N�Z���ށB�Ȃł��Ȃ��A��ł��Ȃ��A���ł��Ȃ��A��l�̐l�ԂƂ��āB����ł܂����͐����n�߂�B�l���͓����n�߂�B |
|
||
�i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j ���}�_���E�o�^�t���C �i���y���A�N���b�N�j http://jp.youtube.com/watch?v=7Z3-yBlDckY �@�v���Ԃ�ɁA�u�}�_���E�o�^�t���C�v�����B�W���R���E�v�b�`�[�j�̃I�y���ł���B���͂��̋Ȃ��D���ŁA�����o���Ɖ��x���A�J��Ԃ������B �u�鐰�ꂽ���ɁA �@�@�����C�̌������Ɉ�̉��������A �@�@�₪�Ĕ����D���`�ɒ����c�c �@�@���̐l�͎�����������A �@�@�ł��A���͌}���ɍs���Ȃ� �@�@����ȂɎ���҂���������c�c�v �@���̋Ȃ��ƁA���Ƃ��Ȃ��C�����ɂȂ�̂́A�Ȃ����B�����́A���肩�炫�������ɗ����������Ƃ����邩�炩�B�F�̔����A�������l�������B�{���ɔ������l�������B���̐l�����ƁA��Ăɑ��z���P���A��ʂɉԂ��炭�悤�������B���̐l�͂����A�t�̗z�������тāA�܂䂢����ɋP���Ă����B �@�}�_���E�o�^�t���C�A�܂蒱�X�v�l�́A���Ƃ��Ƃ͕��m�̖����������A�������疾���ɂ����Ă̍������ɁA�|�҂Ƃ��Ē���ւ���Ă���B�����ŊC�R�m���̃s���J�[�g���ƒm�荇���A�����B�����Ēj�����o�Y�B���A�s���J�[�g���́A�A�����J�A��B��̉̂́A���̃s���J�[�g����҂}�_���E�o�^�t���C���̂����́B����������ȂǕK�v�Ȃ���������Ȃ��B �i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j �@�����悤�Ȕߗ����ꂾ���A�E�B���A���E�V�F�[�N�X�s�A�́u�����I�ƃW�����G�b�g�v�����炵���B���������Ⴂ����A�Z���t���ꐶ�����ËL�������Ƃ�����B�����I�ƃW�����G�b�g���͂��߂ăx�b�h�Œ����}����Ƃ��A�ǂ��炩���������͖Y�ꂽ���A���������B �@�uA jocund day stands tip-toe on a misty mountain-top�v�ƁB�u��т̓����A�����̂��������R�̒���ŁA�ܐ�ŗ����Ă���v�ƁB�{���Ȃ��т̒��ƂȂ�͂������A���̒��A����ƎR�̒���Ƀ����ɂ������Ă���B���������̂��Ƃ̓�l�̉^�����ے����Ă���킯�����A���͂�͂肻�̃V�[���ɂȂ�ƁA���܂�Ȃ��قǂ̐Ȃ����o����B �����A�I���r�A�E�n�b�Z�[�ƃ��i�[�h�E�z���C�e�B���O��������u�����I�ƃW�����G�b�g�v�͂��炵���B���͂��̉f������x�������B�r�f�I�������Ă���B�T�E���h�g���b�N�ł̂b�c�������Ă���B���̉f��̒��ŁA�Ⴂ�j���A�����̂��B�����I�ƃW�����G�b�g���͂��߂Ċ�����킹���p�[�e�B�ʼn̂���̂��B �@�u��Ⴓ���ĉ��H �@�@�@�Փ��I�ȉ��B �����Ƃ͉��H�@ �X�Ɨ~�]�B ���E�����̏�ł�蓮���c�c�v �@ �@���́u�����I�ƃV�����G�b�g�v�ɂ��ẮA�ȑO�B�u���q����������Ƃ��v�Ƃ����G�b�Z�[���������̂ŁA���̂��ƂɓY�t���Ă����B �@�Ō�ɂ�����f��̘b�ɂȂ邪�A�u�}�W�\���S�̋��v�����炵���B�Z���Ȃ����A�f��̍Ō�̃V�[���ɗ����A�uDo Live�v�i�����āj�́A���x�����Ă������Ȃ��B�����d���ɑł����悤�ȗ������āA�g���Ă��s�����悤�ȗ������Ă݂����Ǝv���B���Ȃ�ʖ������A�����������������}���X�����͖Y�ꂽ���Ȃ��B�����c�c�B �i�O�Q�|�P�O�|�T�j�� ���q���������@�������@�i���������� �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �i�k�������@�s���������@���������@�q���������@�������@�i�����������j What is a youth? �@Impetuous fire. �@�Ⴓ���āA���H�@�R�������鉊�B What is a maid?�@ Ice and desire. �@�������āA���H�@�X�Ɨ~�]�B The world wags on, �@���E�́A���̏�ŗx��B a rose will bloom....�@��͍炫�A It then will fade: �@�����ĐF������B so does a youth, �@�Ⴓ���A�܂������B so does the fairest maid. �����Ƃ��������������A�܂������B Comes a time when one sweet smile ���̐l�̊Â����݂� has a season for a while.... �@�����̊ԁA���̋G�߂��}����Ƃ�������Ă����B Then love's in love with me. �@�����Ď��Ɨ��������Ƃ�������Ă����B Some they think only to marry, �@�����������l����l������B others will tease and tarry. �@���炩�������̐l��A���炷�����̐l������B Mine is the very best parry. �@�ł����̂́A���邪�܂܁B Cupid he rules us all. �@�L���[�s�b�h�������A���������x�z����B Caper the cape, but sing me the song, �@�P�[�v���Ђ�߂����A���ɉ̂��̂��B Death will come soon to hush us along. �₪�Ď����K��A��������ɂ߂���B Sweeter than honey... and bitter as gall, �@�I�������Â��A�_�`�Ɠ����قNjꂭ�A Love is a task and it never will pall. �@���́A���ׂ����ƁA�B�����Ƃ͂ł��Ȃ��B Sweeter than honey and bitter as gall. �I�������Â��A�_�`�Ɠ����قNjꂢ�B Cupid he rules us all."�@�L���[�s�b�h�����������x�z����B �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �����q����������Ƃ� ���q����������Ƃ��i�l�������Ƃ��l�Ԃ炵���Ȃ��Ƃ��j �@�I�̖̗t���A���F���F�Â�����A���q�ɃK�[���t�����h���ł����B���[���ŁA�u���܂ł̐l���̒��ŁA��Ԋy�����v�Ə����Ă����B��������[�Ɍ�����ƁA���[�́u�ւ����A���̎q���˂��v�Ə����B���̊�����āA�������ď����B �@�������傤�Ǔ�������A���������B�����������͑����Ȃ������B���炭���ۂ��Ă���ƁA����̏����̕�e���玄�̕�ɓd�b���������B�����Ă����������B�u�����̖��́A����̂悤�ȉƂ̑��q�Ƃ������悤�Ȗ��ł͂Ȃ��B���̌����ɃL�Y��������A���ۂ���߂����ق����v�ƁB ����̏����̉Ƃ́A�]�ƈ��R�O���قǂ̐����H����o�c���Ă����B������̉Ƃ́A���]�ԉ��B�u�i���Ⴄ�v�Ƃ����̂��B���̓d�b�ɕ�͌��{�������A��������̏������C�ɂ��Ȃ������B���A��l�ɂ́A�����ӂ������Q�����z����͂͂Ȃ������B������Ƃ����܂Â����A���̂܂ܕʂ�ɂȂ��Ă��܂����B �@�u��Ⴓ���ĉ��H�@�Փ��I�ȉ��B�����Ƃ͉��H�@�X�Ɨ~�]�B���E�����̏�ł�蓮���c�c�v�ƁB �I���r�A�E�n�b�Z�[�ƃ��i�[�h�E�z���C�e�B���O��������u�����I�ƃW�����G�b�g�v�̒��ŁA�Ⴂ�j�������̂��B���킢���Ȃ����̕���ƌ�������܂ł����A�Ȃ����̋Y�Ȃ��������̐S��ł��ƌ����A�����ɓ�l�̎�҂́u�������v�������邩��ł͂Ȃ��̂��B ���������ƂȂ̐��E�́A���܂�ɂ��U�P�Ƌ��U�ɂ��ӂ�Ă���B�N��P���~���Q���~������悤�ȃj���[�X�L���X�^�[���A�u�s���Ő����������ւ�ł��v�Ɗ�������߂Ă݂���B�ꒅ���S���~������悤�Ȓ����Őg���������^�����g���A�ǂ����̍��̓�̕����܂Ȃ���ɑi����B�\�͉f��ɏo�����A�\������f���Ă���^�����g���A�����s��e�����{����A���{���\���镶���l�Ƃ��ĕ\�������B �����l�������Ƃ��l�Ԃ炵���Ȃ�Ƃ�������Ƃ���A�d���ɑł����悤�ȏՌ����A�g���S���Ă��s�����悤�ȗ�������Ƃ��ł����Ȃ��B����͐l���l���̒��ŗB����ނ��Ƃ��ł���A�u�^���v�Ȃ̂�������Ȃ��B���̂Ƃ��͂��߂Đl�́A�����Ƃ��l�Ԃ炵���Ȃ��B�������ꂪ�܂������Ă���Ƃ����̂Ȃ�A�����Ă��邱�Ƃ��܂������Ă��邱�ƂɂȂ�B����������Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ��B �����I�ƃW�����G�b�g�́A����̐����͂ɁA���������ł��̂߂����B�����Ă��������ϋq�́A���̓�l�ɐS�����킹�A�g���ł����B�܂����ڂ��B����������͌����āA���l�̗������Ƃ����ޗ܂ł͂Ȃ��B�߂����肵�������́A���̎Ⴓ�ւ̗܂��B���̖����ɍL���������t������A�߂������Ă݂�ƁA�܂�ł��������̏u�Ԃł����Ȃ��B�̂͂��������B�u��o���͍炫�A�����ĐF������B�Ⴓ�������B�������������A�܂������c�c�v�ƁB �@����̏���������������B���͈�����A�����̕����œV������߁A�̂�����点�ĐQ�Ă����B�U���̂ނ��������������B�ق�̏����ł������A���̂܂ܑ̂��������āA���Ȃ��ȂɂȂ��Ă��܂������������B�W���W���Ǝ��Ԃ��߂��Ă����̂������Ȃ���A���͊��ƐȂ��ŁA���x�����x�����͎��������������B ������������v���ƁA���̂Ƃ��قǎ����������ŁA�������������Ƃ͂Ȃ��B�����Ă��ꂪ���A���܂�Ȃ��Ȃ������B���͏��[�ɂ����������B�u���肪�ǂ�ȏ����ł��������}���Ă�낤�ˁv�ƁB����ɓ����ď��[�́A�u���R�ł���v�Ƃ����悤�Ȋ�����ď����B�����A�܂������B |
|
||
�i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j �y�r�[�g���Y�̉̂ŏI������t����i�����a�������W���j�z �i���ɂ��s�v�c�ȗ��w�L���j ���s�����Ō�Ƃ������ゾ���� �@�s���̂��Ō�A�A��̂��Ō�Ƃ������ゾ�����B�����̗�����ŁA�S�O���~�ȏ�B�܂��܂����{�͕n���������B�����{�������ї��Ƃ��́A�{���ɂ��т��������B�����Ă��̂��т����́A�t�B���b�s���̃}�j���ɓ������Ă���������Ȃ������B ��A���U�|������������Ă���ƁA�U�A�V�l�̊w�����M�^�|��e���Ă����B�����ڂ���ƌ��Ă���ƁA�u�����A�Ȃ�e���Ă����悤���v�Ɛ��������Ă��ꂽ�B���́u�r�|�g���Y�̃A���h�E�A�C�E���u�E�n�|���v�Ɨ��B���͂��̋Ȃ��Ȃ���A���ӂ��܂��ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �@���ɂ͈�l�̃K�|���t�����h�������B�W���A���E�}�b�N�O���S�[�Ƃ������O�̏��̎q���������A�u�R���W���v�Ƃ����������ŌĂ�Ă����B���A���ɂ͂��������������B�f��u�g���g���g���v���l�Ō��ɍs�����Ƃ����A�ޏ����������{�̖��������Ă��ꂽ�B�f��ق̒��ŁA�A�����J�̔�s�@�������邽�тɁA���芅�т����Ă��ꂽ�B ���̍��ł́A�Â��ɉf������Ă���ϋq�Ȃǂ��Ȃ��B���̃W���Ɏ����A�����������Ƃ��A�ޏ��͂����������B�u�q���V�I�@���͔����a��B���̎���u���Ă����́I�v�ƁB���͂��ꂪ�R���Ǝv�����B�c�c�v���Ă��܂����B�����玄�͓V��ɁA���݂����Ă����R�|�q�|�̃J�b�v�𓊂����A�u�R���I�@�ǂ����ČN�́A�ڂ��ɂ܂ʼnR�����I�v�Ƌ��B �@��A�n�E�X�̗F�����̕����ɂ���ƁA�f�j�X�Ƃ����A���ł�����̐e�F�����A���̔ނ������}���ɂ��Ă��ꂽ�B���̃f�j�X�N�ƃW���͗c�Ȃ��݂ŁA�݂��̗��e�����ӂɂ��Ă����B�f�j�X�ɁA�W���̕a�C�̘b������ƁA�ނ͂����������B�u����͖{������B������ڂ��͌N�Ɍ���������B�W���Ƃ͂������Ă̓_�����B������邱�ƂɂȂ�A�ƁB�������ˁA�W�����N�ɂ��̘b�������Ƃ������Ƃ́A�W���͌N�������Ă����v�ƁB �ޏ��̕a�C�́A�ޏ��Ɣނ�̗��e�������m���Ă���閧�������B���̓W�|�����Ƃ����A�����{�����̓�ɂ��钬�܂ōs���r���A��������Ȃ��狃�����B�I�[�X�g�����A�̐���́A���{�̂���������{���L���B�n�������炷�������P���Ă���B���͂��������A����Ɉ��|����ċ������B ���������Ď��̐t����͏I�����c�c �@�������Ď��̗��w����͏I������B�����ɁA���̐t������I������B�����Ă��̎�����삯�������Ƃ��A���̐l���ς��ꔪ�Z�x�ς���Ă����B���͂��̍��ŁA�u���R�v���������A���ꂪ���ł����̐����̊�{�ɂȂ��Ă���B�������̌�A�l���Y�Ƃ�����Ђ���߂āA�c�t�����t�ɂȂ����Ƃ��A�ǂ̐l�����������B�C���������Ƃ��킳����l�������B ��ɑ��k����ƁA��܂Łu���͓���������v�ƁA�d�b���̂ނ����ŋ�������Ă��܂����B�����f�j�X�N�����́A�u���炵���I�����v�Ɗ��ł��ꂽ�B�Ȍ�A�c����������āA�N�ɂȂ�B�͂����Ă��̑I���������������̂��ǂ����c�c�H �@���������A�W���ɂ��Ĉꌾ�B�����A�����Ă��琔�J����B�W���́A���h�C�c�ɂ���Z��������ăh�C�c�֓n��A�����ŃM���V���l�ƌ������A�A�e�l�ߍx�̒��ŏ�����f�����B �܂������n�E�X�ɂ����A���̍c���q�≤���̑��q�����́A���͂��̍��̌��̐l���ƂȂ��Ċ��Ă���B�e���r�ɂ����X����o���B�f�j�X�́A���w�Z�̋������������ƁA���h�Ȃɓ���A���̓��i�[�V����w�̐}���قŎi�������Ă���B�{���D���Ȓj�ŁA�����u�ڂ��͖{�Ɉ͂܂�čK�����v�ƌ����Ă���B�������͑��ς�炸�A���́u���]�ԉ��̑��q�v�̂܂܂����c�c�B |
|
||
���N�̎��i���j �_�������@�u�̏� �Ԃ̗����@�p�i�����ނ�j�� ���ɐA����@�ЂƂ��Ƃ� �ЂƂ��Ƃ� �Ⴋ��]�Ɓ@���̕c ��ɐL�т�@�N�̎��� �������ԁ@��������� �J���ɈÂ��@����Ȃ� �r�g�ݍ��킹�@�����s���� �����s���� �M���S�Ɓ@�ӋC�n���� �X�Ɉ�ā@�N�̎��� �����̗F��@�v�킸�� �c���̎p�@���@���� �����̖閾�����@��������� ��������� �䓙�������ā@�N������ �������i�����j���@�N�̎��� �i�쎌�A�����s�m���E�Ό��T���Y���j �@���͊w������A�߂������Ƃ�炢���Ƃ�����ƁA���܂��Ă��̉̂��������݁A�������Ȃ����߂��B���ł��A�Ƃ��ǂ��A���̉̂��A������o�Ă���B �@�ŁA���̉̂ɂ́A����ȃG�s�\�[�h������B �@�����I�[�X�g�����A�̃J���b�W�ŁA���̉̂��̂��Ă���ƁA��l�̗F�l�i�I�[�X�g�����A�l�j���A�u����͉��̉̂��H�v�ƁB�����Ŏ����A�u����͂��炵���̂��B�Ă����悤�v�ƌ����āA�Ă�����B �u�_���A�u�̏�ɗ���āA�݂�ȂŐN�̖Ƃ�����A�����B���̖�A�L�т�Ƃ����̂��Ƌ�����v�ƁA���̗F�l�́A����������āA�u�����A����ȉ̂��v�Ƃ����悤�Ȋ�������B �@�ŁA�����u�����̎�����v�Ƃ����݂�����ƁA�u�q���V�A�_���u�̏�ɂ�����āA����Ȃ��Ƃ͉��ł��Ȃ��ł͂Ȃ����v�ƁB�ނ�ɂ́A���{�I�ȃf���J�V�[�������ł��Ȃ��悤���B �@�������A����Ɣ��̂��Ƃ�����B �@�����Ԃ�Ɛ̂����A��l�̍��Z���i�j�q�j���A�����������������Ŏ��̂Ƃ���ɂ���Ă��āA�����������B�u�搶�A���炵���̂�����B�|�Ăق����v�ƁB �@���ꂪ���b�h�E�X�`���A�[�g�́u�Z�[�����O�v�������B���A�Ă݂�ƁA���ł��Ȃ��̎��B �@�u�ڂ��́A�q�C���Ă���B�ڂ��͍q�C���Ă���ƁA���ł��Ȃ���B�C�������āA���Ȃ��̂Ƃ���A����āA�ˁv�ƁB �@���̍��Z���́A�������肵���l�q���������A���ꂩ�炵�炭�������Ƃ̂��ƁB���͂��̋Ȃ��āA�����ւ�Ȃ܂��������������Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B�u�Z�[�����O�i���������������j�v�́A���炵���Ȃ������B �@���ƂŁA���̍��Z���ɂ���܂������Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��B �i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j ��Sailing �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ I am sailing, I am sailing, home again 'cross the sea. I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying, I am flying, like a bird 'cross the sky. I am flying, passing high clouds, to be with you, to be free. Can you hear me, can you hear me thro' the dark night, far away, I am dying, forever trying, to be with you, who can say. Can you hear me, can you hear me, thro' the dark night far away. I am dying, forever trying, to be with you, who can say. We are sailing, we are sailing, home again 'cross the sea. We are sailing stormy waters, to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free, Oh Lord. �iWritten �����@Rod Stewart�j �@�Ⴂ��������A���ꂳ��́A�u�N�̎��v���A�u�Z�[�����O�v���m��Ȃ���������Ȃ��B�s�v�c�Ȃ��̂��B�����������������̂��������ނƁA���̂Ƃ��̌��i�݂̂Ȃ炸�A�F�̊�A���͋C�A�S�̗l�q�܂ŐS�̒��ɂ�݂������Ă���B�̂Ƃ����̂́A�����������̂��B �@�����Ă�����B���������̂��o�Ă���Ƃ��Ƃ����̂́A���̂Ƃ��̐S��Ƌ��ʂ���Ƃ��B�u�N�̎��v���o�Ă���Ƃ������Ƃ́A�������̂��݂����Ƃ��A�炢�Ƃ���������Ȃ��B����낤�I �i�O�R�O�W�R�P�j �����b�h�E�X�`���A�[�g�́A�Ō�ɂ����̂��B �u��I�[�A���B���Ȃ��ɋ߂Â����߂ɁA����������邽�߂ɁB �@�@�I�[�A���A���Ȃ��ɋ߂Â����߂ɁA����������邽�߂ɁB �@�@�I�[�A���v�ƁB �@���������̂X�Ɖ̂���l���A�����܂����B |
|
||
�i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j �����U�O�I ���A�U�O�B���̎����́A�Ȃ��B�܂������A�Ȃ��B �F�ŁA�痿����H�ׂ��B�P�[�L��H�ׂ��B �u�i�s�̂́j�V���[�g�P�[�L�ł�����v�Ǝ��������ƁA �u��邩�炢���v�ƁA���C�t�͌������B �Â��Ȏ������ꂽ�B���炢���������ꂽ�B ���̓p�\�R����O�ɂ��āA�������B�������̖��������B ����ƁA���C�t�����ɂ����B�u�������݂����v�ƁA���B �u���������A�������ł��邩��v�ƁA���C�t�B �����̗[���B�����̗[�H�B�����Ă����̒a�����B ���j�ƃ��C�t���A���̐��ɍ��킹�ĉ̂��Ă��ꂽ�B �u��n�b�s�[�o�[�X�f�B�A�c�[�A���[�v�ƁB �[�H��A�݂ȂŁA�w���b�L�[�E�U�E�t�@�C�i���x�������B �悢�f�悾�����B�Ȃ����������B�܂����ӂꂽ�B �U�O�̒a�����ɁA�ӂ��킵���f�悾�����B ���u���ƂP�O�N�A������v ���u�����̃y�[�X�ł����̂�v ���u�������ˁv�ƁB ���͂����Ő����B �����P�l�̎��Ȏ��Ƃ́A���ʂ���B�������₷���A �Ђ��݂₷���A�������₷���B����Ȏ����B ����ɂ����ЂƂB���̐�A���̂P�O�N�ɁA ���̖���q����B���̖���R�Ă���B�R�Ă������B �c��̐l���́A���̂��̂ł͂Ȃ��B ���̑��q�����̂��́B���̃��C�t�̂��́B �����āc�c�B ���������Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B�����Ȃ��B ���������̖����A���̒n���ɁA�F���ɁA �Ԃ������B�݂ȂɁA���������B �u�ǂ�ȋC���H�v�ƁA���C�t�͌������B ���U�O�ɂȂ����C�������C�t�͕������B���́A �u�ʂɁc�c�v�Ɠ������B �����ς��Ȃ��B���̎��o���Ȃ��B �u�U�O�v�Ƃ��������ȂǂɁA�Ӗ��͂Ȃ��B ���͎��B�ǂ��܂ł����Ă��A���͎��B �������̓��u�͉����H�@�u��邼�I�v�Ƃ������u�B ���܂łɂȂ��������́B�����ɂ��A������i�������j�B ������߂邱�ƁA���������邱�ƁA�������� �l���Ă����B���A����Ȏ��̒��ŁA�������R���������B �悢�f�悾�����B�w���b�L�[�E�U�E�t�@�C�i���x�́A �悢�f�悾�����B����Ȏ��ɂ��A������E�C�� �^���Ă��ꂽ�B��]��^���Ă��ꂽ�B ���ɂ���̂́A�ߋ��ł͂Ȃ��B�������B ���̖����Ɍ������āA���͐i�ށB �u�ǂ�Ȃɑł��̂߂���Ă��A�O�ɐi�ݑ�����c�c�B �����Ă�����߂��ɁBNEVER GIVE UP!�v �u������M���Ȃ���A�l������Ȃ��v�ƁB ���Ă��ė܂��|���|���Ƃ��ڂꂽ�̂́A���̂��߂��B �R�T�N�O�́A���̊����A�܂肠�̓����̊������A ��݂������Ă����B ���̎���A���́A���䖲���Ő����Ă����B�����A ���ނ����ɓ������B���̊������A��݂������Ă����B ���ꂩ����A���́A���䖲���ŁA�����Ă��������B �����Ă����B���A�͂₵�_�i�́A�܂��܂��������B ���̓�������܂Łc�c�B �͂₵�_�i�A���U�O�̒a�����ɁB �i�t�L�j �@�w���b�L�[�E�U�E�t�@�C�i���x�̒��́A�V�����F�X�^�[�E�X�^���[���̓��̂����Ăق����B�ނ͂��̉f������������邽�߂ɁA�����̓��̂�b�����B���̃v���������A�X�N���[����ʂ��āA�������ɓ`����Ă����B���ꂪ�A�������������������B �V�����F�X�^�[�E�X�^���[���́A���҂Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�f���ʂ��āA�����̐������܂��A�������Ɏ����Ă��ꂽ�B �@�E�\��C���`�L�ł́A���̉f��͂ł��Ȃ��B |
|
||
�i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j �����̓h���L�z�[�e �@�Z���o���e�X�i�~�Q���E�f�[�T�[�A�x�h���E�Z���o���e�X�E��l���`��Z��Z�E�X�y�C���̏����Ɓj�̏������{�ɁA�w�h���L�z�[�e�x������B�w���}���`���̒j�x�Ƃ��Ă�Ă���B���z�ƂƂ������A�ϑz�ƂƂ������A�h���L�z�[�e�Ƃ����j���A������R�m�Ǝv�����݁A���X�̖`��������Ƃ�������ł���B �@���̕���̂������낢�Ƃ���́A�ЂƂ��Ƀh���L�z�[�e�̂��߂ł����ɂ���B������R�m�Ǝv�����݁A�����ЂƂ肾�������`�̎g�҂ł���A���ꂱ�����E��������ė����Ă���Ǝv������ł��܂��B�����ď������̂ɂԂ��A�_�v�̃T���`�����]�҂ɂ��A�V���ڂꂽ���o�̃��V�i���e�ɏ���āA���ɏo��c�c�B �@���������u���߂ł����v�́A�Ђ���Ƃ�����A����ɂł�����B���̂Ƃ���A���̎��ɂ�����B�悭���C�t�͎��ɂ��������B�u���́A���{�̋�����A���ׂĂЂƂ�Ŕw�����Ă���݂����Ȃ��Ƃ������ˁv�ƁB�ŋ߂ł́A�u���Ȃ��͓��{�̊O����b�݂����v�Ƃ��B�������ꂱ�ꍑ�ۏ��S�z���邩�炾�B �@���A�l���Ă݂�A����l���炢���A����_��������Ƃ���ŁA�܂����ۖ���S�z�����Ƃ���ŁA���{�␢�E�́A�r�N�Ƃ����Ȃ��B���Ƃ��ƁA��������ȂǁA����ɂ��Ă��Ȃ��B����͂���Ƃ����قǂ킩���Ă��邪�A�������A���͂����ł͂Ȃ��B�u�����ł͂Ȃ��v�Ƃ����̂́A����ɂ���Ă���ƌ�����Ă���Ƃ����̂ł͂Ȃ��B���́A����ɂ�����ɂ���Ȃ��Ă��A�����̐S�Ƀu���[�L�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������ƁB���������Ӗ��ŁA�h���L�z�[�e�Ǝ��́A�ǂ������Ȃ��B���邢�͂ǂ����Ⴄ�̂��B �@�悭�A���m���o�c���Ă���l�����ƁA����_���킷���Ƃ�����B���m�̌o�c�҂Ƃ����Ă��A�o�c�������l���Ă���o�c�҂����邪�A���ɂ́A��簁i�����܂��j�Ȏv�z�������Ă���o�c�҂��A���Ȃ����A����B�����c�_�����킷�̂́A��҂̃^�C�v�̌o�c�҂����A�Ƃ��ǂ��A���������o�c�҂Ƌc�_���Ȃ���A�ӂƁA�����v���B�u����ȋc�_�������Ƃ���ŁA���ɂȂ�̂��H�v�ƁB �@�������͂悭�A�u���{�̋���́c�c�v�Ƙb���n�߂�B�������A������c�_���Ă��A�܂��������Ӗ��B����͂��傤�ǁA�X���̓X�̃I���W���A�u���{�̌o�ς́c�c�v�Ƙ_����̂ɁA�悭���Ă���B���邢�͂���ȉ���������Ȃ��B�_�����Ƃ���ŁA�}�X�^�[�x�[�V�����ɂ��Ȃ�Ȃ��B����������ł��A�������͋c�_���Â���B�܂��A�����Ȃ�ƁA��̂悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B���邢�͓��̑̑��H�@���Ȗ����H�@����A��͂�}�X�^�[�x�[�V�������B����ɂ�����ɂ��ꂸ�A�����Ђ�����A�����Ŏ������Ȃ����߂�c�c�B �@���̎p���A�����A���́A�h���L�z�[�e�Ɏ��Ă��邱�Ƃ�m�����B�W�v�V�[�����̎ŋ����A�����̐��E�Ǝv������ő�\�ꂷ��h���L�z�[�e�B���Ԃ������Ǝv�����݁A�����œ˂�����ł����h���L�z�[�e�B����͂܂��ɁA�u�����ȋ����v���A�u����v�Ǝv������ł��鎄�����̎p�A���̂��̂ƌ����Ă��悢�B �@���Ď��́A���A�������ăp�\�R���Ɍ������A����_��q��Ę_�������Ă���B�u���ɂ����Ă���v�ƌ����Ă����l�����邪�A�������{���̂Ƃ���́A�킩��Ȃ��B�ǂ�ł�����Ă��邩�ǂ��������A�킩��Ȃ��B����������ł��A���͏����Ă���B�l���Ă݂�Ώ����Ȑ��E�����A���������̓��̒��ɂ��鑊��́A���{�ł���A���E���B�S�ӋC�����́A���{�̑�����b��荂���H�@���A�̎���������荂���H�@�c�c����ɂ����v������ł��邾�������A����䂦�ɁA���͂����v���B�u���́A�܂��ɁA���߂ł����h���L�z�[�e�v�ƁB �@���ꂩ������Ƃ����h���L�z�[�e�́A���̂������Â���B����ɂ�����ɂ���Ȃ��Ă��A�����Â���B���߂ł����j�́A���܂ł����߂ł����B���������̂��߂ł����������A�܂��Ɏ��Ȃ̂��B�����珑���Â���B �i�O�Q�|�P�Q�|�Q�P�j ���������̂������Ă���ƁA����Ȃ��ƂɋC�Â��B����͓��̉�]�Ƃ����̂́A���̂Ƃ��̃R���f�B�V�����ɂ���ĈႤ�Ƃ������ƁB�����A�����ɕω�����B�ŁA���q�̂悢�Ƃ��́A����ł悢�̂����A�����Ƃ��́A�u�����A���͂��̂܂܃_���ɂȂ��Ă��܂��̂ł́c�c�v�Ƃ������|�S�ɂ�����B���������Ӗ��ł́A�����A�������ď����Ă��Ȃ��ƁA��]���ێ��ł��Ȃ��B���킢�̂́A�A���c�n�C�}�[�Ȃǂ̔]�̕a�C�����A�������Ė����A���̂������Ă���A�����\�h�ł���̂ł́c�c�Ƃ������҂�����B �������]�̘V���́A�]�̂b�o�t�i�������Z���u�j���̂��̘̂V�����Ӗ����邩��A���ɘV�������Ƃ��Ă��A�����ł���ɋC�Â����Ƃ͂Ȃ��Ǝv���B�u�����ł͂ӂ����v�Ǝv������ł���ԂɁA�ǂ�ǂ�ƃ{�P�Ă����c�c�B���������ω����킩��̂́A���̕���A�����ēǂ�ł����ǎ҂������Ȃ��̂ł́B���邢�͂��łɁA����ɋC�Â��Ă���ǎ҂����邩������Ȃ��B�u�т̏����Ă��镶�́A���̂Ƃ���ʍ����v�ƁB�c�c���́A�����g�����̂Ƃ��낻���v���悤�ɂȂ��Ă����B�����A�ǂ����悤�I�I �����z���Ƃ��Ă���ԂɁA����������B�i�Z���o���e�X�u�h���E�L�z�[�e�v�j �����̂��邩����A��]�͂���B�i�Z���o���e�X�u�h���E�L�z�[�e�v�j �����R�̂��߂Ȃ�A���_�̂��߂Ɠ����悤�ɁA������q���邱�Ƃ��ł��邵�A�܂��q���˂Ȃ�Ȃ��B�i�Z���o���e�X�u�h���E�L�z�[�e�v�j ���p����������A�����Ă��̔߂��݂͊�������B�i�Z���o���e�X�u�h���E�L�z�[�e�v�j �����Ŏ��͂��̐��ɂ����B�����玄�͗��ł��̐�����o�čs���˂Ȃ�Ȃ��B�i�Z���o���e�X�u�h���E�L�z�[�e�v�j ���^�̗E�C�Ƃ́A�ɒ[�ȉ��a�ƁA�����������̒��Ԃɂ���B�i�Z���o���e�X�u�h���E�L�z�[�e�v�j |
|
||
�i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j ������L�́u���Ɓv�_ �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �w�Z�ȊO�Ɋw�Z�͂Ȃ��A�w�Z�𗣂�ē��͂Ȃ��B����ȑ��ꂵ�����A����L�́A�w���Ɓx�̒��ł����̂����B�u��c�c�`���C������A�����̂����̐Ȃɍ���A���ɏ]���A�]���ׂ����l���Ă����v�ƁB�u�l�Ԃ͎��R���v�Ƌ���ł��A����́u���܂ꂽ���R�v�ɂ����Ȃ��B�����ɂ̓R�[�X������A���̃R�[�X�ɋt�炦�t������ŁA�������̃��b�e�����Ă��܂��B����͂�����A�u�ƃ��A���ȋC�����v�ƕ\�������B �@�F����s�m�̂l���́A�����ւ����悤�ɂ����������B�u�q�ǂ�������A�������āv�ƁB�������������Ă������ŁA�ꂵ�ނ̂́A�q�ǂ��������g�ł͂Ȃ��̂��B�܂������Ƃ��狖����Ȃ��B�ق�̈ꕔ�́A�l���̂悤�Ȑl�ԑI�ʂ����܂������蔲�����l�������A���������̖������Ȃ��邱�Ƃ��ł���B�唼�̎q�ǂ��͂��̉ߒ��ŁA�������A�������A���܂���B����͂���������B�u�����ی�X�ӂ���A�������͕��̒��B�ǓƁA���ɕ����ׁA�₵���������v�ƁB ����҂����̐��Ȃ����R �@���{�l�͎�҂̗���ł��̂��l����̂����B�ڂ����������Ă���B���Ƃ��Β��p�c�A���p���p�̊w�����A�u�������ڂ�v�ƌ��߂Ă�����B�������ނ�ƂĐ���t�A���Ȏ咣���Ă��邾�����B���ꂪ���߂��Ƃ����Ȃ�A�ނ�ɂ͂ق��ɁA�ǂ�ȕ��@������Ƃ����̂��B����������҂Ɍ������āA�����𐳂��ƌ����Ă��A�����B����������̂��B�u��s�V�悭�܂��߂Ȃ�Ăł��₵�Ȃ������v�ƁB�ނɂ��Ă݂�A����́u���M�����ʂ��ƂȂƂ̑����v�ł��������B �@���ۂ��̐��̒��A�U�P���������ӂ�Ă���B�N��~������悤�ȃj���[�X�L���X�^�[���A�u�s���Ő����������ւ�ł��v�Ɗ�������߂Č�����B�����͍��Ȉߑ���g�ɂ��Ă���e���r�^�����g���A�ʂ̂Ƃ���ŁA�܂Ȃ���ɕn�����l�����ւ̊����i����B���������̂�����������ƁA���̎������Ă܂��߂ɐ�����̂��o�J�炵���Ȃ�B�����Ŕ���͂��̃z�R����A�w�Z�Ɍ�����B�u����̍Z�ɁA���K���X�ĉ�����c�c�v�ƁB������K���X���Ƃ����s�ׂ́A�������ׂ��s�ׂł͂Ȃ��B���A����ȊO�ɕ��@���v�����Ȃ������̂��낤�B����A���̑O�ɂ���������҂̍s�ׂ��A�N���u���āA�łĂ�v�̂��B ���b�c�ƃV���O���Ղ����œ�Z�Z�����ȏ�I �@���́u���Ɓv�́A��O�̃q�b�g�ȂɂȂ����B�b�c�ƃV���O���Ղ����ŁA��Z�Z���������i�b�a�r�\�j�[�L�A���݂̃\�j�[�l�d�j�B�u�J�Z�b�g�ɂȂ����̂�A�A���o���̒��Ɏ��^���ꂽ���̂��܂߂�ƁA����ɑ����Ȃ�܂��v�Ƃ̂��ƁB���̐����������A����̋���ɑ���A��҂����́A�܂��ɐ��Ȃ��R�c�Ƃ݂�ׂ��ł͂Ȃ��̂��B �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �������錴�_�Ɏ��_���c�c �@�{���Ȃ�A�t���g���A����L�̂悤�ɁA�u�w�Z�ȂA�N�\�H�炦�I�v�Ƌ���ł݂��炢���Ǝv���̂ł��B���邢�́A��x�A����L�́u���Ɓv���Ă݂�ꂽ�炢�����ł��傤���B�����͋��̒����A�X�J�b�Ƃ��邩������܂����B���x�������Ă���ƁA�������ł����A�ӎ����ς���Ă��邩������܂���B�����Ă݂Ă��������B �@�b�����Ƃɂ��ǂ��܂����A�t����́A�������イ�Ԃ�ꂵ�݂܂����B�������ˁA�t������ꂵ�߂��̂́A�t����̂��q����ł͂Ȃ��B�t���g�ł��Ȃ��B�t������ꂵ�߂��̂́A���́A�t���g�̒��ɂ���A�u����ꂽ�ӎ��v���Ƃ������Ƃł��B���������Ō����邱�Ƃ́A�u�E�C�������āA���̈ӎ��Ƃ͌��ʂ��Ȃ����v�Ƃ������ƁB���̂t����ɂ́A�z�������Ȃ����Ƃ�������܂��A���̐�ɂ́A���邢�o��������܂��B�����č��Ɠ����悤�ɁA����₩�ȋ�C������A���邢���z������܂��B�����ς��Ȃ��̂ł��B�V�����h���i�n���K���[�̎��l�A�P�W�Q�R�|�S�X�j�͂��������Ă��܂��B �w��]�����ςł���̂́A�܂��Ɋ�]�Ɠ����x�i�u��]�_�v�j�ƁB �@���̘D�v���A�܂������������Ƃ������Ă���̂́A�����ւ��[���ł��ˁB���������Ă��܂��B �w��]�̋��ςȂ邱�Ƃ́A�܂��Ɋ�]�Ƒ������x�i�u�쑐�v�j�ƁB �@���̂����肪���l�����̋��ʂ����ӌ��̂悤�ł��B�킩��₷�������ƁA��]�ɂ���A��]�ɂ���A�����������̂́A����ɐl�Ԃ���肾�������̂ɂ����Ȃ��Ƃ������ƁB��Ȃ��Ƃ́A���̌������ɂ�����̂�������Ȃ��Ƃ������ƁB�t����̗���Ō����Ȃ�A���q�����Ƃ��J�i�����ȁj���A�������Ă͂����Ȃ��Ƃ������ƁB�����A���A�����ɂ��Ȃ������āA�q�ǂ�����������B���̏d�v����Y��Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�J�肩�����܂����A�܂��ɂ���́u��Ձv�Ȃ̂ł��B���̊�Ղɂ܂����]�ȂǁA����͂����Ȃ��̂ł��B �@�����X�g���[�g�ɏ��������邽�߁A�C���������Ȃ������Ƃ�������邩������܂��A�ǂ������̎莆���A�O�����ɂƂ炦�Ă��������B�����Ă��Ȃ��͂ЂƂ�ł͂Ȃ��B�������܂��B�����Ǝ����A���Ȃ��̂��ɂ��܂�����A�E�C�������āA�O�ɐi��ł��������B������ł��͂ɂȂ�܂��B�����A�t���A�u�����������Ƃ�����܂����v�Ə���������܂ŁA�͂ɂȂ�܂��B��������ɁA�����܂��傤�I �͂₵�_�i |
|
||
�i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j �����{�̏펯�A���E�̏펯 �����b���_ �@���̕����ւ́A�悭�q�������B�u���{��������Ă���v�u�|�āv�ȂǁB���ɂ́A�u���������Ă���v�u�n���L���i�ؕ��j�̂����������Ă���v�Ƃ����̂��������B���邢�́u�e�ۗ�ԁi�V�����j�́A������܁Z�}�C���ő���Ƃ������{�����v�u���{�ł́A���n�̔n�́A�R�[�X���A�I�[�X�g�����A�Ƃ͋t�ɉ��B�Ȃ����v�ƁB����Ɂu���{�l�́A���̏��ւ����ނƂ������{�����v�Ƃ����̂��������B�b���ƁA�u�J���s�X�v�Ƃ���������������Ă������Ƃ������Ƃ킩�����B�J�E�́A�u���v�A�s�X�́A�Y�o���A�u���ցv�Ƃ����Ӗ��ł���B �@���A������A�I���G���^���X�^�f�B�Y�i���m�w���j�֍s���ƁA�l�A�ܐl�̊w���������͂�ŁA�����������B�u���b����������Ăق����v�ƁB���킭�A�u��삪�g�ǂɐ�����B��삪�����B�����Ő��͑ߕ߁A�����A�����Đؕ��B�����܂ł͂킩��B�������Ȃ��A���̕������A�g�ǂɕ��Q�������̂��v�ƁB���Q�҂̕������A��Q�҂��ÎE����Ƃ����̂́A�ǂ��l���Ă��A���������B����Ɏ��Y��鍐�����̂́A�g�ǂł͂Ȃ��A���̐��{�i���{�j���B�Y���d�߂���Ȃ�A���̐��{�ɍR�c����悢�B�܂����������̐E����Ȃ��ɂ����̂́A���Ƃ����{�X�ł���B�ǂ����ă{�X�ɐӔC��Njy���Ȃ��̂��A�ƁB �@�������b�����^�������Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�ԓ��ɍ����Ă���ƁA�ʂ̊w�����A�u�ǂ����ē��{�l�́A���ˉ���ɓ���������̂��B���ˉ��傪�A�܂����������Ƃ����Ă��A����������̂��v�ƁB�����A�u���ˉ���͈������Ƃ͂��Ȃ��v�ƌ����ƁA�u����͂��������v�ƁB �@�C�M���X�ł��A�I�[�X�g�����A�ł��A���̌��͂Ɛ�����l�����p�Y�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���Ƃ��I�[�X�g�����A�ɂ́A�}�b�h�E���[�K���Ƃ����j�������B�̒���S�ł������A��������l�ŁA���{�̖�l�Ɛ�����j�ł���B�C�M���X�ɂ��A���r���E�t�b�h��A�E�B���A���E�E�H���X�Ƃ����l���������B �����{�̒P�g���C �@�@�w���ł�����Ȃ��Ƃ��b��ɂȂ����B���[�X�N�[���̈ꎺ�ŁA�݂Ȃ�����������ł���Ƃ��̂��ƁB�u���i���@�w�����������ɂ����������B�u���{�ɂ͒P�g���C�i�����́A�Z���o���ƌ������B�Z���o���́A�P�g���C�������������j�Ƃ������x�����邪�A�@�I�ȋK���͂Ȃ��̂��ˁH�v�ƁB�����Ŏ����u�����Ȃ��v�Ɠ�����ƁA�܂��ɂ����w�������܂ł����A�u�Ƒ����o���o���ɂ���āA�����d�����I�v�Ƌ��B �@���{�̏펯�́A�����Đ��E�̏펯�ł͂Ȃ��B���������̏펯�̈Ⴂ�́A���{�ɏZ��ł��邩����A��ɂ킩��Ȃ��B���A���̏펯�̈Ⴂ���A�S��A�v���m�炳�ꂽ�̂́A�������{�A���Ă��Ă���̂��Ƃł���B ���������ꂽ�� �@�����O�䕨�Y�Ƃ�����Ђ���߂āA�c�t���̋��t�ɂȂ肽���ƌ������Ƃ��̂��ƁA�i���̂Ƃ����łɎO�䕨�Y��ސE���Ă������j�A���̕�́A�d�b���̌������ŁA�I�C�I�C�Ƌ�������Ă��܂����B�u�p������������A���ꂾ���͂�߂Ă���v�u�_�����A���͓���������A�`�v�ƁB������Ƃ����āA���ӂ߂Ă���킯�ł͂Ȃ��B��͕�ŁA�����̏펯�ɏ]���āA�����������������B�����A���͕ꂾ���́A����M���āA�����x���Ă����Ǝv���Ă����B���A���̈ꌾ�ŁA���͂������莩�M���Ȃ����A���ꂩ��O�Z���߂���܂ŁA���́A�O�̐��E�ł́A�c�t���̋��t�����Ă��邱�Ƃ��B�����B����A���̐��E�ł́A���w���Ă������Ƃ��B�����B�ǂ���ɂ���A�b������b�����ŁA�݂ȁA�u�ǂ����āH�v�Ǝ���������Ă��܂����B �@���A���̂Ƃ��A�܂莄���c�t���̋��t�ɂȂ�ƌ������Ƃ��A�����x���Ă��ꂽ�̂́A�ق��Ȃ�ʁA�I�[�X�g�����A�̗F�l�����ł���B�݂ȁA�u�q���V�A�悢�I�����v�u���炵���d�����v�ƌ����Ă��ꂽ�B���̌��t���Ȃ�������A���̎��͂Ȃ������Ǝv���B �@ |
|
||
�i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j ���������A����Ȃt�e�n�I �@�������̂͌����B����Ȃt�e�n�A���B�n�o����A��L���͂������B���������Ə��[�̓�l�ŁA����������B�������Ƃɂ͂܂������Ȃ��̂����A�������\�ܔN�߂����O�̂��ƂŁu�Ђ���Ƃ�����c�v�Ƃ��������͂���B���A���̌�A����ƂȂ����[�Ɗm���߂��������A�������_�͓����B�u�܂������Ȃ��A����͂t�e�n�������v�B �@���̖�A�������́A�����̂悤�ɃA�p�[�g�̋߂����U�����Ă����B�����͐^�钆�̏\���߂��Ă����B���̂Ƃ����B���̋C�Ȃ��ɋ�����グ��ƁA�W�����������F�̊ۂ����̂��A����Ŕ��ł���̂��킩�����B���͍ŏ��A��������^�J�������̒�������Ŕ��ł���̂��Ǝv�����B�����v���āA���̐����������Ɛ����͂��߂��B���Ƃŕ����Ə��[���������Ƃ����Ă����Ƃ����B �@���A������܁A�Z�܂Ő������Ƃ��A���͔w��������̂��o�����B���̊ۂ����̂��͂ނ悤�ɁA����肳��ɍ����u���v�̎��^�̕��̂������Ɍ��ꂽ���炾�B�������^�J���Ǝv�����̂́A���̕��̂̑��炵�����̂������B�u�����v�Ɛ����o���ƁA���̕��͓̂ˑR���x�������A���̕����ɁA�����Ȃ���ы����Ă������B �@������Ԃɕl���̍q�q���ɓd�b�������B���̕��̂���n�̂ق�������ł������炾�B���A�ǂ̕����ɓd�b�������Ă��u���������͂���܂���v�ƁB����������ꂪ�t�e�n�Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B���̒m���Ă����t�e�n�́A������A�_���X�L�[�^�̂��̂ŁA�t�e�n�ɁA�܂�������قǂ܂łɋ���Ȃ��̂�����Ƃ͎v���Ă��݂Ȃ������B �@���A���̂��Ƃ��Ǐ��ꎁ�i�t�e�n�����Ɓj�ɘb���ƁA��ǎ��͑܂����ς��̂t�e�n�̎ʐ^��͂��Ă��ꂽ�B�������̓A���o�C�g�ŁA���{�e���r�́u�P�P�o�l�v�Ƃ����ԑg�̊�����`���Ă����B��ǎ��͂��̔ԑg�̃f�B���N�^�[�����Ă����B���̃����E�Q���[����{�֘A��Ă����l�ł�����B���Ə��[�͂��̒��̈ꖇ�̎ʐ^�ɓB�Â��ɂȂ����B�������������̂ƁA�܂����������`�̂t�e�n�����������炾�B �@�F���l�����邩���Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ�A���͂���Ǝv���B�l�Ԃ������F���̐����ƍl����̂́A�l�Ԃ������n����̐����ƍl���邭�炢�A�������Ȃ��Ƃ��B�����Ă��̉F���l�i�����A�����Ȃ̂��낤���c�j���A�t�e�n�ɏ���Ēn���ւ���Ă��Ă����������͂Ȃ��B�������̖錩�����̂��A�ڂ̍��o���Ƃ��A��s�@�̌��܂��������Ƃ������l��������A���͂��̐l�Ɠ����B�����Ă��Ӗ����Ȃ����A�����B���̓E�\�������Ă܂ŁA���̃R�����������������Ȃ����A���E�\�Ƃ������ƂɂȂ�A���͏��[�̐M�����������ƂɂȂ�B �@�c�Ƃ܂��A����R�����̒��ŁA�Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ������Ă��܂����B���̘b������ƁA�u�N�͋���]�_�Ƃ𖼏���Ă���̂�����A���������b�͂��Ȃ��ق����悢�B�N�̎������^����v�ƌ����l������B���������͂��������ӂ��Ƀ��N�Ŕ��f�����̂��A�D���ł͂Ȃ��B���������Ƃ����Ă��A����]�_�����ł͂Ȃ��B�������G�b�Z�C�����p���������B�m���t�B�N�V���������ӂȕ��삾�B���m��w�Ɋւ���{���O�����������A�@���_�Ɋւ���{���܍��������B�����l���͒�����ɂ��|��Ă���B �@����Ȃ킯�Ŏ��́A�����u����v�Ƃ����J�x��������_���l���Ă���B���Ƃ����̐��E�ł́A�t�e�n�ɂ��Č��̂̓^�u�[�ɂȂ��Ă���B�����炱�������āA���͂���ɂ��ď����Ă݂��B |
|
||
���q�ǂ��̋��K���o�����܂�Ƃ� ���������̂������Ȃ����� �@��Z���~�̂������c�����Ƃ��A���͏��[�ɕ������B�u���̂����ō��`�֍s���������B����Ƃ������������������v�ƁB����Ə��[�́A�����Ȑ��ł����������B�u���`�֍s�������c�c�v�ƁB �@�����̎��͂قƂ�ǖ��T�̂悤�ɁA��k�⍁�`�֍s���Ă����B�}�j����V���K�|�[���܂ő����̂����Ƃ��������B�������̉�Ђ̖|���ʖ�A����ɖf�Ղ̎d������`���Ă����B�����ł��̎d���̈�ɁA���[��A��čs�����Ƃɂ����B����Ȃ킯�Ŏ������͌����������Ă��Ȃ��B�c�c�ƌ������A���̂������Ȃ������B ���z�e���Ŏ��O�̔�I�� �@ �@���ꂩ��N���܂�B��Z�Z�Z�N�̂��钋�A�e���r�����Ă�����A����ȃV�[������э���ł����B���ł����ł́A�q�ǂ��̎��O�̏j�����A�z�e���ł���e������Ƃ����B���Ȕ�I���ɁA���ȐH���ƈ����o���B��p�͈�l������A�~����O���~���Ƃ����B����Ƃ܂����ǂ��Ȃ��q�ǂ����A����܂����Ȉߑ���g�ɂ܂Ƃ��A�������̐V�Y�V�w��낵���A�F�̑O�ł����������Ă����B���Ə��[�͂�������Ȃ���A���t���������B �@���̎������B���������c�����v���ŁA�V��������I�����B�Ⴂ���돗�[�͂悭�A�u��x�ł�������A�ԉňߏւ𒅂Ă݂����v�Ƃ��ڂ����B�����ł��傤�ǎ����O�Z�ɂȂ����Ƃ��A���邢�͎l�Z�ɂȂ����Ƃ��A��I�������͂��悤�Ƃ����b���������������B���������̂ǐg���̐e�����̎��Əd�Ȃ��āA����Ă��܂����B�������Ɏl�Z�������߂��A���̖тɔ�����������悤�ɂȂ�ƁA���[���������̂��Ƃ͌���Ȃ��Ȃ����B �����������Ȃ����q�ǂ� �@ �@���������Ɋ����Ί����قǁA�q�ǂ��́u�������v���Ȃ����B�����╨�́A�V����~���Ă�����̂��Ǝv���悤�ɂȂ�B�q�ǂ����g�������A���ƂȂɂȂ��Ă�����A���ꂾ���̐������ێ��ł���悢�B���A�����łȂ���A��J����̂́A���ǂ͎q�ǂ����g�Ƃ������ƂɂȂ�B����A�e�����ċ�J����B���ł́A���l���̔�p�́A�����Ă��e���o���B�����̐��ꒅ�̂����A�݈ߑ��ł��낦�Ă��A��ܖ��~�����Z���~�i�l���s���݈̑ߑ��X��̘b�j�B����͂Ȃ��B �@����ɎЉ�l�ɂȂ����Ƃ��̐V���̔�p�A�������̔�p������A�e�����S����B���O�̏j���ł���A�z�e���ō��ɍÂ��������ł���B�ǂ����Ă��̂Ƃ��ɂȂ��āA�u�����̔�p�͎����ŕ����v�ƁA�q�ǂ��Ɍ����邾�낤���B���A���ꂾ���ł͂��܂Ȃ��B ���X�g�[�u�͈�����A�����ςȂ��@ �@���������Ȃ������q�ǂ��́A�u�e�̋�J�v�Ƃ������̂��ǂ��������̂��A�킩��Ȃ��Ȃ�B���ӂ����Ȃ��B�u���Ă�����ē��R�v�ƍl����B�����e�����Ŋw�����������Ă��鑧�q�̃A�p�[�g��K�˂Ă݂��Ƃ��̂��ƁB����قǗT���ȉƒ�ł͂Ȃ��B���̕�e�͑��q����w�ɓ��w����Ɠ����ɁA�߂��̃X�[�p�[�Ńp�[�g�̎d�����n�߂��B��e�͋������B�t�悾�����Ƃ������A�d�C�X�g�[�u�͈�����A�����ςȂ��B�g�ѓd�b�̓d�b�������ɎO���~�߂����������Ă����B�u�o�C�N���ق����v�ƌ������̂ł����𑗂����̂����A���̑��q�́A�O�Z���~������L���L���L���̃A�����J���X�^�C���̃o�C�N���Ă����Ƃ����B�u���Ẫ\�t�g�o�C�N�Ȃ�A�O�`�l���~�ł���܂���v�Ǝ��������ƁA���̕�e�́A�u����A�\�`�E�I�v�Ƌ����Ă����B ���u���Ȃ�o�Ȃ��Ȃ���v �@�l�͐l���ꂼ�ꂾ���A���������́A���Ə��[�̉�b�����̂܂����B�������O�̗l�q�����Ă�����Ă���ƁA���[�͂����������B�u��������������v�ƁB�������������B�u���Ȃ�A����Ȕ�I���A���҂���Ă��s���Ȃ���v�ƁB���͎��ł����������B�u�c���̂Ƃ�����A����Ȃɂ��������Ɉ�Ă�A��J����͎̂q�ǂ����v�ƁB�u�q�ǂ����ɂ���Ƃ������Ƃ́A�q�ǂ������l�ɂ��邱�Ƃł͂Ȃ��B���������āA�y�������邱�Ƃł͂Ȃ��B�e�Ƃ��Ă��ׂ����Ƃ��Ⴄ�v�ƁB����������́A���������ł��Ȃ������������v�w�́A�Ђ��݂�������Ȃ��B���Ə��[�͂��̕����Ȃ���A���x�����ߑ��������B ���`�̃z�e���ŁA�e�����̐l�ɁA���̉̂��̂��Ă��炢�܂����B �Q�l�Œ������v���o�̋Ȃł��B �i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j |
|
||
�����{�̉f�� �i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j �@�؍��̉f��̖��i���߂��܂����B��������̂͂��B���A�؍��ł́A���������āA�f�搧��̐U�����͂����Ă���B�����̑�w�̑����ɂ́A�����Ƃ��������w��������B�o�D�ɂȂ邽�߂̊�{���A���̊�b���炽��������ł���B �����m�邩����ł��A�R�T�N�O�ł����A�I�[�X�g�����A�̏��w�Z�ɂ́A�h���}�i�����j�Ƃ����Ȗڂ��������B���Ƃ��A�����J�ɂ��A�������B �@����Ɉ��������A���{�́c�c�H �@�o�D�̉��Z���A�ǂ�����Z�A���Z���Ă���H�@��{���y�̕\�����A�܂��ɁA���̂܂܁B�u�{���Ă���Ƃ��́A���������\���������̂ł��v�u�߂����Ƃ��́A���������\���������̂ł��v�Ƃ����悤�ȉ��Z������B���̉��Z�ۂ����A���{�̉f����A�܂�Ȃ����̂ɂ��Ă���B �@����ɂ������Ȍ��Ў�`���A�͂т����Ă���B�u�̂���̔o�D�v�u�̕���o�D�v�Ƃ��������ŁA�剉�ɂȂ邱�Ƃ������B �@���{�̉f��t�@�����A�������ƂƎv���B�����Ď��̂��������ӌ��ɁA���𗧂Ă�l���������ƂƎv���B�������A���ɂ́A���炵���o�D������B�u���X�g�E�T�����C�v���剉�����A�v�j�̉��Z�́A�悩�����B �@���A��͂�S�̂Ƃ��Ă݂�ƁA���{�̉f��́A�܂�Ȃ��B���Ƃ��A���{�̉f��ł́A�����ɂ��m�I���x���̒Ⴛ���Ȓj�D���A�w�҂⌤���҂̖��������肷��B�u����Ȋw�҂͌������ƂȂ����ǂȂ��v�Ǝv�����Ƃ���A�������߂Ă��܂��B���邢�͊璆�A���ςœh�肽�������悤�ȏ��D���A�����Ŕ�ꂽ�����������Ă݂����肷��B �@�ǂ����A����������B���̖������A�܂��܂����{�̉f����A�������낭�Ȃ����̂ɂ���B �@�ŁA�Ƃ��ǂ��A�O�]���Ȃǂ��āA�u���x�����c�c�v�Ǝv���āA���{�f��̃r�f�I����Ă���B���������̂قƂ�ǂɁA���]�B�����Ă��r���ŁA����̂���߂Ă��܂��B �@���R�ȉ��Z�B�������R�ȉ��Z�B�J������ϋq���ӎ����Ȃ��A���R�ȉ��Z�B�����������Z���ł���o�D�𖼗D�Ƃ����B���A���ꂪ�ނ��������H �@���̍D���ȉf��ɁA�؉��b��ḗA�w��т��߂��݂�����Ό��x������B���̒��œ����̗L��l�Y���������A���c�[��A�Ȃ̂���q���������A����G�q��́A���D���̖��D�B�o�D���g�̐������Ƃ������A�l�Ԑ����A���̂܂܉�ʂɏo�Ă����B �@����������ƁA�o�D�́A�o�D���g���A���̐S�̎�����łȂ���Ȃ�Ȃ��B�ɂ������S�̔o�D���A�����琽���Ȑl�Ԃ������Ă��A�s���Ƃ��Ȃ��B�s���Ƃ��Ȃ��Ƃ��납��A���������܂��B�����A���̂��ƍ��ꂽ�A�����C�N�ł́w�V�E��т��߂��݊�Ό��x�́A�u���ꂪ�����Ȑl�Ԃł��v�Ƃ������Z�ۂ����肪�ڗ����i����I�j�A�܂������������낭�Ȃ������B �@�b�͕ς�邪�A���̃��C�h�V���[�����Ă����Ƃ��̂��ƁB��l�̃L���X�^�[���A����^�����g�̃n�����`�s�ׂ����ꂱ��Ɣ��Ă����B�������������Ă���L���X�^�[���g���A���邩��ɃX�P�x�����B�ގ��g���A�����ɂ��A�����������Ƃ��������ȕ��͋C��Y�킹�Ă����B���̓��C�h�V���[�����Ȃ���A�����v�����B �@�u���������āA�������Ƃ��Ă����Ȃ��́H�v�ƁB �@�܂�͐l�Ԑ��̖��Ƃ������ƂɂȂ�B���̐l�Ԑ����Ȃ��ŁA����ׂ����ʼn��Z���Ă��A���Z�͉��Z�̂܂܁B������ϋq�����ʂ����Ƃ��A�ϋq�́A���̉f�悩��A����A�ނ��Ă��܂��B�o�D�ɁA�����𒍓��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �@�f��́A����߂ďd�v�ȕ����ł���B�|�p�ł���B��{�̉f��̒��ɁA���̍��̕������ׂĂ��W��邱�Ƃ��������Ȃ��B���A���̓��{�ł́A�o�D�ɂ��Ă��A�ǂ����̃v���_�N�V�������{������̂��A�ЂƂ̗���ɂȂ��Ă���B �@�������������߂邾���̔o�D����ׂāA�f�������̂��A�f��ł͂Ȃ��B����Ӗ��ŁA�f��قǁA���낵���|�p�͂Ȃ��B���w�ɂ���A���p�ɂ���A�����͊ԂɁA�{��G���Ԃɒu�����ƂŁA�����̕\����B�����Ƃ��ł���B �@�������f��́A�������B���̐l�̐l�Ԑ����A�\���ʂ��āA���̂܂܃����ɏo�Ă���B���Z�Ƃ͂����Ȃ���A�ϋq�́A���Z�̌������ɁA���̐l���g������B �@���������Ӗ��ł́A�A�����J�f��́A���{�f����͂邩�ɐ���s���Ă���B����C���^�r���[�ԑg�̒��ŁA�n���\���E�t�H�[�h�͂��������Ă����B�u�O�Ȉ�̖������邱�ƂɂȂ����Ƃ��ɂ́A�a�@�֍s���A�����������ĊO�Ȉ�̕��͋C���A�����i�����������j�����v�ƁB �@���������p���̂��������A�A�����J�f����A�������낢���̂ɂ��Ă���B���ł��A�����J�̉f��Y�Ƃ��҂��O�݂́A���{���d�q�Y�Ƃʼn҂��O�݂Ɠ������������B�f��́A���h�ȎY�Ƃɂ��Ȃ肦��B ���ꂾ���ł͂Ȃ��B�P�O�O�l�̊O�������A�P�O�O�N�������Ă���悤�Ȏd�����A�P�{�̉f�悪���邱�Ƃ����āA���肦��B �@����̕���ɂ��Č����Ȃ�A���̐l�������邱�Ƃɂ���āA�ʂ̐l�����邱�Ƃ��ł���B���l�̗���ł��̂��l����͂�g�ɂ��邱�Ƃ��ł���B���̌��ʂƈӋ`�ɂ��ẮA���ꂩ��̉ۑ�Ƃ������ƂɂȂ邪�A���Ƃ������߂��ċꂵ�ގq�ǂ��̖��������邾���ł��A���̎q�ǂ��́A�����߂ɂ��Ă̂��̂̌������ς�邩������Ȃ��B �@�Ƃ���Ŏ����q�ǂ��̂���ɂ́A�u���ҁv�Ƃ����E�Ƃɂ́A�傫�ȕΌ����������B�E�Ƃɂ�鍷�ʈӎ����A�܂��������c���Ă����B�ǂ��Ό������������ɂ��ẮA�����ɂ͏����Ȃ����A�����g���A�����܂Ŗ��҂ɑ��錩�����ς��Ƃ́A�v���Ă����Ȃ������B �@�u���ƂȂɂȂ�����A�^�����g�ɂȂ肽���v�ƌ����q�ǂ��́A���ł́A�������Ȃ��B���A�����q�ǂ��̂���ɂ́A�܂��A���Ȃ������B�u�o�D�ɂȂ�v���Ƃ��l����q�ǂ��������Ȃ������̂ł́c�c�B���������Ό����A���{�̉f����A�����܂Œx�点���Ƃ�������B �@�����A���{�̉f��l�I�I�I �i��L�j���̋����ł́A�N�Ɉ�x�A�u���Z�v�Ƃ����e�[�}�Ń��b�X�����Ă���B�\���A������A�q�ǂ������ɁA�\��������B�u���ꂵ��������A���ꂵ�����Ȋ�����Ȃ����I�v�ƁB �@�S�̏�ԂƁA�\��A��v���Ă���q�ǂ����A�c������̐��E�ł́A�u���Ȃ��Ȏq�ǂ��v�Ƃ����B �i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ ��т��߂��݂���Ό� ���疦�́@������ �ȂƓ�l�Ł@���s���D�� �������F���� �����������@���������� �~���������Ɓ@�C���Ȃ��� �k�͐ፑ�@����̖�� ���ɖ��J�� �Ăт�����@�Ăт����� ���ꏬ���Ɂ@��̕��� �����Ώt����@�Ԃ̍��ւ� �����̗� �v���o���@�v���o�� ���ɗ[�Ɂ@���D�o�D �Ȃ悪���@�܂��ʂ��� �����Ă���߂� �Ă̊C�@�Ă̊C ���𐔂��ā@�g�̉������� ���ɉ߂����@��Ό��� ��낱�є߂��� �ڂɕ����ԁ@�ڂɕ����� �i�؉����i�E�쎌�A��ȁj |
|
||
���v�����[�O ���ăW�����E���m���́A�u�C�}�W���v�̒��ŁA�����̂����B ��u�V���͂Ȃ��B���͂Ȃ��B�@���͂Ȃ��B �@�@�×~����Q�����Ȃ��B�E���������Ƃ� �@�@���ʂ��Ƃ��Ȃ��c�c �@�@����Ȑ��E��z�����Ă݂悤�c�c�v�ƁB �����O�܂ŁA���̓��{�ł��A�F�����̒��B���̂ƌ����Ă����B �c�����́A�M�����́A�m�����̂Ƃ������Ă����B ���������A����Ȃ��Ƃ������l�́A��������Ȃ��B ����Ɠ����悤�ɁA�₪�āA�W�����E���m�����������悤�� ���E���A����Ă��邾�낤�B�������ɂ͖������Ƃ��Ă��A �K���A����Ă��邾�낤�B �݂�Ȃƈꏏ�ɁA�͂����킹�āA�����������E���߂������B ������߂Ă͂����Ȃ��B�����~�܂��Ă���킯�ɂ������Ȃ��B ��Ȃ��Ƃ́A���̖ڕW�Ɍ������Đi�ނ��ƁB �����Č�ނ��Ȃ����ƁB �����Ђ�����A���̖ڕW�Ɍ������Đi�ނ��ƁB �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �C�}�W���i��P�j ���V���͂Ȃ����Ƒz�����Ă݂悤 ���̋C�ɂȂ�ΊȒP�Ȃ��� �ڂ������̉��ɂ͒n���͂Ȃ� ���̏�ɂ���̂͋� �݂�Ȃ������̂��߂ɐ����Ă���Ƒz�����Ă݂悤�B �ȂȂ��Ǝv���Ă݂悤 �ނ����������Ƃł͂Ȃ� �E���������Ƃ��Ȃ���A���̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ��Ȃ��Ȃ��B �@�����Ȃ� ���a�Ȑl����z�����Ă݂悤 ����Y���Ȃ����Ƃ�z�����Ă݂悤 �N�ɂł��邩�ǂ����킩��Ȃ����� �×~����Q���̕K�v���Ȃ� ���ׂĂ̐l�������Z��� �݂�Ȃ��S���E�������Ă���Ƒz�����Ă݂悤 ���l�͂ڂ����A������l�ƌ�����������Ȃ� ����ǂ��ڂ��͂ЂƂ�ł͂Ȃ��B ���̓����A�N�������ڂ��ɉ���邾�낤�B �����Đ��E�͂ЂƂɂȂ邾�낤�B �i�W�����E���m���A�u�C�}�W���v���j �i���F�uImagine�v���A�����̖|��ƂɂȂ���āA�u�z������v�Ɩ����A�{���́uif�v�̈Ӗ��ɋ߂��̂ł́c�c�H�@���������ӂ��ɖƁA���̂悤�ɂȂ�B�����̎��ł��A���ɂ���āA���̃j���A���X���A�����Ɉ���Ă���B �C�}�W���i��Q�j ������V�����Ȃ��Ɖ��肵�Ă݂悤�A �������肷�邱�Ƃ͊ȒP�����ǂˁA �����ɂ́A�n���͂Ȃ���B �ڂ������̏�ɂ���̂́A���B ���ׂĂ̐l�X���A�u���v�̂��߂ɐ����Ă���� ���肵�Ă݂悤�c�c�B ��������Ƃ������̂��Ȃ��Ɖ��肵�Ă݂悤�B �������肷�邱�Ƃ͂ނ����������Ƃł͂Ȃ����ǂˁB ��������A�E���������Ƃ��A���̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ��Ȃ��B �@�����Ȃ��B�������a�Ȑ���������c�c�B ��������L������̂��Ȃ����Ƃ����肵�Ă݂悤�B �N�ɂł��邩�ǂ����͂킩��Ȃ����ǁA �×~�ɂȂ邱�Ƃ��A�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ���B �l�X�݂͂�ȌZ�킳�A �������E���̐l�������A���̐��E�����L������ˁB ��N�͂ڂ����A������l�ƌ�����������Ȃ��B �������ڂ��͂ЂƂ�ł͂Ȃ���B �����N�������ڂ��ɉ���邾�낤�Ǝv����E �����Ă��̂Ƃ��A���E�͂ЂƂɂȂ邾�낤�B ���łȂ���A�W�����E���m���́u�h�������������v�̌����� �����ɍڂ��Ă����B���Ȃ��͂��̎����ǂ̂悤�ɖ��낤���B �i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j Imagine Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today�c Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for No religion too Imagine life in peace�c Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world�c You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one. �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �����S�ɂ��čl���� �c�c�W�����E���m���́u�C�}�W���v���Ȃ���c�c�B �@���N������ܓ��ɂȂ�ƁA���{������A�u�����S�v�Ƃ������t���������Ă���B�����̓ǔ��V���i������Z���j������ƁA����ȋL�����������B�u�V�������j���ȏ��������v�i��E�c���p���E���k�勳���j�̃����o�[�����M�����u���w���j���ȏ��v���A���Q���Ō������w�Z�ł��̑�����邱�ƂɂȂ����Ƃ����B�̑��i�S���v�j�����߂����Q������ψ���̈�֘a�F�ψ����́A���̂悤�Ɍ���Ă���B �@�u����������S����āA���ʓI�A���p�I�ɗ��j���Ƃ炦��Ƃ����w�K���\���Ɣ��f�����B�푈�^���Ƃ̎w�E�͌����߂��ŁA������Ɠǂ߂ΐ푈��ے肵�Ă��邱�Ƃ��킩��v�i�ǔ��V���j�ƁB �@���{�ł́A�u����������v���Ƃ��A���E�̏펯�̂悤�Ɏv���Ă���l�������B�������A���Ƃ��Β�����k���N�Ȃǂ̈ꕔ�̑S�̎�`���Ƃ��̂����āA����̓E�\�B���{�ł́A�u�����S�v�ƁA�����Ɂu���v�Ƃ�������������B���������Đl�́A�A�����J�l���A�I�[�X�g�����A�l���A�u���v�ȂǁA�l���Ă��Ȃ��B���Ƃ��Ήp��ŁA�����S�́A�u���������������������v�Ƃ����B���̒P��́A���e����́u�����������������i�p��̂��������������j�A����ɃM���V����́u�������������v�ɗR������B �@�u�������������v�Ƃ����̂́A�u���Ȃ��n�v�Ƃ����Ӗ��ł���B�܂�A�u���������������������v�Ƃ����̂́A���{�ł́A�܂��ɓ��{���ɁA�u������`�v�Ɩ��A���Ƃ��Ƃ́u���Ȃ��n���������`�v�Ƃ����Ӗ��ł���B�O�̂��߁A�������̔h�������ׂĂ����̂ŁA�Q�l�ɂ��Ăق����B �����������������c�c���Ȃ��n��������l�i���{�ł͈����҂Ɩj ���������������������c�c���Ȃ��n�������邱�Ɓi���{�ł͈����I�Ɩj ���o��������������'�@�c�����c�c�ꎵ���ܔN�A�l�������A�k�����������������ł̐킢���L�O�����L�O���B���̐킢�����ɁA�A�����J�͉p���Ƃ̓Ɨ��푈�ɏ��B���{�ł́A�u�����L�O���v�ƖB ���ĂŁA�u�����S�v�Ƃ����Ƃ��́A���{�ł����u�����S�v�Ƃ������́A�u�����S�v�ɋ߂��B���邢�͈����S���̂��̂������B���Ȃ��Ƃ��A�ނ�́A�̐����Ӗ�����u���v�ȂǁA�l���Ă��Ȃ��B�����ɓ��{�l�Ɖ��Đl�́A�傫�ȃY��������B�܂�̐������Ă̍��ƍl������{�A�������Ă̑̐��ƍl���鉢�ĂƂ́A��{�I�ȃY���Ƃ����Ă��悢�B���A���������Y����m���Ă��m�炸���A���邢�͂��̃Y�����I�݂ɂ��肩���āA���{�̕ێ�I�Ȑl�����́A�u�����S�͐��E�̏펯���v�Ȃǂƌ������肷��B �@���Ƃ��Ύ����u�D�c�M���͖\�N�������v�Ə��������Ƃɂ��āA�u�N�́A���{�̈̐l��ے肷��̂��B���Ȃ��͂���ł����{�l���B���͐M���h���Ă���v�ƍR�c���Ă����j���i�l�Z���炢�j�������B���̃^�C�v�̐l�ɂ��Ă݂�A�������Ă̖��ƍl���邩��A�D�c�M���ǂ��납�A�T�؊�T�i�̂��܂ꂷ���A��������̌R�l�j��A�����p�@�i�Ƃ����傤�Ђł��E��O�̗��R�叫�j�������A�u�����x���Ă����p�Y�v�Ƃ������ƂɂȂ�B ���������j�͗��j������A��Âɂ݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����������Ɠ����ɁA���j��s�K�v�ɔ���������A�c�Ȃ��Ă͂����Ȃ��B��̑��ɂ��Ă��A�O�Z�Z���l���̓��{�l�������A���{�l�́A�������O�Z�Z���l���̊O���l���E���Ă���B���{�ɁA�����ꔭ���̔��e�����Ƃ��ꂽ�킯�ł��Ȃ��B���{�l�����{�����ŁA������l�E���ꂽ�킯�ł��Ȃ��B���������{�l�́A�i���ł��N���ł��悢���A�Ƃ��������A�O���ւł����Ă����O�Z�Z���l�̊O���l���E�����B �@���{�̐��{�́A�u���̂��߂ɐ�����p��v�Ƃ������t���悭�g�����A�ł́A���̉p�삽���ɂ���ĎE���ꂽ�O���l�́A�����Ƃ������ƂɂȂ�B�����������t�͍D���ł͂Ȃ����A���Q�҂Ƃ���Q�҂Ƃ��������ƂɂȂ�A���{�͉��Q�҂ł���A�����E���ꂽ���N�⒆���A����A�W�A�́A��Q�҂Ȃ̂��B����������Q�҂̐S���l���邱�Ƃ��Ȃ��A����I�ɉ��Q�҂̗�����������̂͋�����Ȃ��B���ꂪ�킩��Ȃ���A���̗���ōl���Ă݂�悢�B �@������ˑR�A�j���̋���ȌR�����A���{�ւ���Ă����B���{�̐��{����̂��A������Ď��������̐��{��u�����B�Â��ē��{����֎~���A�ނ�̂j���������Ƃ��ċ`���Â����B���{�l���O�l�W�܂��āA���{���b���A���A�����A���Y�B�������j���R�́A�ނ�̂����Ƃ���̎�́A�����q���������A���̏@���{�݂ւ̎Q�q���`���Â����B������肩�A���\���l�̓��{�l���j�������A�s���A�j���̍H��œ��������B���_�A����ɒ�R������̂́A�e�͂Ȃ������A���Y�B�������Ĉł���łւƑ���ꂽ���{�l�͐��m��Ȃ��c�c�B �@���������j���̉��\���ɑς����˂��ꕔ�̓��{�l���������������B�����Đ킢�����������B������������A�͂��Ⴂ������B�킦�ΐ키�قǁA�]���҂��ӂ����B���A�������͂ȏ����l�����ꂽ�B�A�����J�Ƃ��������l�ł���B�A�����J�͑O�X����j�����A�u���̐����i���������j�v�ƌĂ�ł����B�����ŃA�����J�́A����ɋ���ȌR���͂��g���āA�j�����A���Ȃ��Ȃɕ��ӂ����B���{�͂��̂Ƃ�����ƁA�j�����������ꂽ�B �@���A�����Řb���I���킯�ł͂Ȃ��B���ꂩ��܁Z�N�B���܂��ɂj���͓��{�ɂ�т邱�Ƃ��Ȃ��A�u���������͐��������Ƃ����������v�u���̐푈�͂�ނ����Ȃ��������́v�Ƃ����Ԃ��Ă���B������肩�A���{��N���������{�l�������A�u�p��v�A�܂�u���̉p�Y�v�Ƃ��čՂ��Ă���B����������������������ꂽ��A���Ȃ��͂��������A�ǂ������邾�낤���B �@���͌J��Ԃ����A�����A���{��ے肵�Ă���̂ł͂Ȃ��B���̂܂܂ł͓��{�́A���E�̌ǎ��ǂ��납�A�A�W�A�̌ǎ��ɂȂ��Ă��܂��ƌ����Ă���̂��B�܂�ǂ��̍����������ɂ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���́A���̌o�ϗ͂ɂ��̂����킹�āA�܂肨�����o���܂����ƂŁA���Ƃ��n�ʂ�ۂ��Ă��邪�A�����ł͐S�����Ȃ��B�����ł̓L�Y�����S�����₷���Ƃ͂ł��Ȃ��B���{�̌o�ϗ͂ɉA�i�����j�肪�o�Ă������Ȃ�A�Ȃ����炾�B �܂����ɔے肵���Ƃ���ŁA�����łԂ킯�ł͂Ȃ��B���̃h�C�c�́A���A�O��I�Ƀi�`�X�h�C�c����̂����B���Ձi�����j�������c���Ȃ������B�����Đ��E�Ɍ������Ĕ��Ȃ��A���������̔���Ӎ߂����B�i����ɑ��āA���{�͎��ɂ������Ȃ��Ƃ����A�����ɂ͂����̈�x�����������̔��F�߁A�Ӎ߂������Ƃ͂Ȃ��B�j���̌��ʁA�h�C�c�̓h�C�c�Ƃ��āA���̍��A���[���b�p�̒��ł����A�d�t�i���[���b�p�A���j�̍Ɏ�Ƃ��āA���̒n�ʂ��m�ۂ��Ă���B �@������߂悤�B����ȋ��ȋc�_�́B���������{�l�́A�܂�������Ƃ����B����͓����������������ł���A�����琳�������悤�Ƃ��Ă��A�������ł�����̂ł͂Ȃ��B�܂��������������قǁA���{�͐��E����Ǘ�����B����ɂ���Ȃ��Ȃ�B���ꂾ���̂��Ƃ��B �@�Ō�Ɉꌾ�A��������Ȃ�A���ꂩ��́u�����S�v�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�u�����S�v�ƌ�����������ǂ����낤���B�u�����S�v�Ƃ����Ɂu���v�Ƃ������������邩��A�b�����������Ȃ�B���A�����S�Ƃ����A����ɔ�����l�͂��Ȃ��B ���������Z�ލ��y��������B�����������������鋽�y��������B���{�l����ĂĂ����A�������̓`���ƕ�����������B���ꂪ�����S�Ƃ������ƂɂȂ�B�u�����S�v�ƌ����A���������q�ǂ��Ɍ������āA���X�Ƌ����Č������Ƃ��ł���B�u�����A�݂Ȃ���A�������̋��y�������܂��傤�I�@�������̓`���╶���������܂��傤�I�v�ƁB �i�O�Q�|�W�|�P�U�j�� |
|
||
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�͂₵�_�i �����A�u���v�ɂ��āA�Ⴂ�Ƃ��A�Y�݂܂����B ����ɂ��ď������̂��A���̌��e�ł��i�����V���f�ڍς݁j �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�͂₵�_�i �i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j �����Z�싅�Ɋw�Ԃ��� �@�����ɐ����邩��A�l�͔������B�P���B���̉��l�����邩�Ȃ����̔��f�́A���Ƃ��炷 ��悢�B������Ӗ���ړI���A���̂��Ƃɍl����悢�B���Ƃ����Z�싅�B ���������Ȃ����̍��Z�싅�Ɋ������邩�Ƃ����A�����Ɏq�ǂ������̌������������� ����ł͂Ȃ��̂��B�������{�[���̃Q�[���Ə��Ă͂����Ȃ��B�����������Ă���u�d ���v�����āA�Ӗ�������悤�ŁA����قǂȂ��B�u���̂��Ă��邱�Ƃ́A�{�[���̃Q�[�� �Ƃ͈Ⴄ�v�Ǝ��M�������Č�����l�́A���̐��̒��Ɉ�́A�ǂꂾ�����邾�낤���B ���l�͂Ȃ����܂�A�����Ď��ʂ̂� �@���͊w������A�V�h�j�[�̃L���O�X�N���X�ŁA�~���[�W�J���́w�w�A�[�x�������B���z �I�ȃ~���[�W�J���������B���̒��Ŏ�l���̃N���[�h���A����ȉ̂��̂��B�u�����͂� �����܂�A�Ȃ����ʂ̂��A�i�����m�邽�߂Ɂj�ǂ��֍s�������̂��v�ƁB ���ꂩ��O�Z�N���܂�B�������̖��ɂ��āA�����ƍl���Ă����B�����Ă��̌��ʂ� �����킯�ł͂Ȃ����A�g���X�g�C�́w�푈�ƕ��a�x�̒��ɁA���͂��̓��̃q���g������ �������B �@���̂ނȂ����������邠�܂�A�������瓦�����A���ǂ͖łт�A���h���C���݁B����A �l���̖ړI�͐����邱�Ƃ��̂��̂ɂ���Ƃ��āA�l����O�����ɂƂ炦�A�ŏI�I�ɂ͍K�� �ɂȂ�s�G�[���B���̃s�G�[���͂��������B�w�i�l�Ԃ̍ō��̍K������ɓ���邽�߂ɂ́j�A �����Ђ�����i�ނ��ƁB�����邱�ƁB�����邱�ƁB�M���邱�Ɓx�i��ܕҎl�߁j�ƁB �܂茜���ɐ����邱�Ǝ��̂ɈӖ�������A�ƁB�����ƌ����A�l���̈Ӗ��ȂǂƂ��� ���̂́A�����Ă݂Ȃ���킩��Ȃ��B�f��w�t�H���X�g�E�K���v�x�̒��ł��A�t�H�� �X�g�̕�́A���������Ă���B�w�l���̓`���R���[�g�̔��̂悤�Ȃ��́B�H�ׂĂ݂�܂ŁA �i���̖��́j�킩��Ȃ��̂�x�ƁB �������ɐ����邱�Ƃɉ��l������ �@�����ł�����x�A���Z�싅�ɂ��ǂ�B�ꋅ�ꋅ�ɑS�_�o���W��������B������s�b�`�� �[���A������}�����o�b�^�[���^�����B�����c�͋������悤�ɁA�������J��Ԃ��B�݂� �ȕK�����B���������B�s�b�`���[�̊炪���ŃL�����ƌ��������̏u�ԁA�{�[�����������A �����Ă��ꂪ�����ԁB ���̒���A�J�L�[���Ƃ����������A����ɂ����܂���B��u���Ԃ��~�܂�B���A�� �̂��Ɗ�т̊����Ɣ߂��݂̐⋩���A�����ɏ���߂����c�c�B �@���͂��ꂪ�l�����Ǝv���B�����Ė����̐l�����̌����Ȑl�����A����܂����G�ɂ���� �����āA�l�Ԃ̎Љ������B�܂肻���ɐl�Ԃ̐�����Ӗ�������B ����A�����Č����Ȃ�A�����ɐ����邩�炱���A�l���͌�����B�����鉿�l�����B ����������ƁA�����łȂ��l�ɁA�l���̈Ӗ��͂킩��Ȃ��B������]���Ȃ��B��M���� �u���Ȃ��B�����A�����������܂܁A���̓����̓����A����ɉ߂����Ă���l�ɂ́A�l ���̈Ӗ��͂킩��Ȃ��B ����Ɍ���������ƁA�u�������͂Ȃ����܂�A�Ȃ����ʂ̂��v�ƁA�q�ǂ������ɖ��ꂽ �Ƃ��A���������q�ǂ������ɋ����邱�Ƃ�����Ƃ���Ȃ�A�����ɐ�����A���̐����� �܂ł����Ȃ��B���̍��Z�싅�ŁA�����A�I�肽�����G�k�����A�َq���ق���Ȃ���A �K���Ɏ��������Ă�����A���Z�싅�Ƃ��Ă̈Ӗ��͂Ȃ��B�������Ȃ��B����ق����A�� �܂�Ȃ��B�����������̂͂�����J��Ԃ��Ă��A�����̃q�}�Ԃ��B�l��������Ɠ����B ���������l������́A���ǂ͉������܂�Ȃ��B���Z�싅�́A������������ɋ����Ă��� ��B |
|
||
���j���̐����ʁi�W�F���_�[�j +�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �j�̎q�́A�j�̎q�炵���A���̎q�� ���̎q�炵������ׂ��B ����Ȏ������I�A�t�s�I�Ȉӌ� ���A�܂��܂��A�䓪���Ă����B �j�Ə������ʂ��邱�Ƃ́A��{�I �ɁA�܂������Ă���B ��������I�ȈႢ�Ƃ����̂� ����B���e�ƕ�e�Ƃ̖����̈Ⴂ ������B �������u�j�v�Ɓu���v����ʂ��� �K�v�́A�܂������Ȃ��B�܂��A�� �Ă͂Ȃ�Ȃ��B �j���́A�P�O�O���A�����ł���� ���ł���B�ǂ����ē����ł����� �͂����Ȃ��̂��H +�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j ���d���������������� �@�����́A�q�ǂ����Y��ŁA�݂ȁA��e�ɂȂ�B���A��e�ɂȂ����Ƃ���A�����́A����܂ł́u��v�������B �@���Ƃ��Ύ��̋����֘A��Ă����e���������Ă݂悤�B�����̉��ł�����Ă����e������A�����ӂ��̕�e�����ł���B���������̂����A���̂����̉������́A�����ւ�Ȍo���̎�����ł��邱�Ƃ��킩��B �@���ې��̌��X�`�����[�f�X�B �@���̂̌��I��B �@�����i�f�U�C�i�[�B �@�o�C�N�̌������e�X�g���C�_�[�B �@���q�Z��̌��u�t�A�ȂǂȂǁB �@�����_�ɂ����āA���������l�������A�u��e�v�����Ă���B �@�b���āA�u�n�A�H�v�ƁA���̂ق����A�����قǂł���B�������������������A�������A�q�ǂ����������邱�ƂŁA�u�d���v���痣���B���������ꂩ���A���܊��Ƃ������A���f���ɂ́A�����Ȃ��̂�����B �@�����A����܂ŃL�����A�����Ďd�������Ă����������A�����Ɠ����ɁA���̎d������߁A�ƒ�ɓ���B������[�����������ł����Ă��A���B�������E��̉X�����������A���ł͂Ȃ��B�Ō�w��c�t���̋��t�����Ă����l�ł��A���̍��܊��Ƃ������A���f���́A�����ł���B �@���A�ƒ�ɓ���A����Ȃ�ɍK�������Ɍ����鏗���ł��A�s���S�R�Ă̂܂܁A��X�Ƃ��Ă��鏗���́A�����B �@���������������A����Ӗ��ŁA�����������N�����Ă���̂ł͂Ȃ����B���邢�͂��̐S����Ԃɋ߂��̂ł͂Ȃ����B���A�ӂƁA�����v�����B �@���́A����������e�����ɏo����тɁA�u�ǂ����āH�v�Ǝv���Ă��܂��B�u�ǂ����āA�d������߂��̂��H�v�ł͂Ȃ��A�u�ǂ����Ďd������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H�v�ƁB ���W�����_�[ ���̓I�Ȑ������u�Z�b�N�X�v�B�Љ�I�A�����I�A�`���I�Ȑ������u�W�F���_�[�v�Ƃ����B�������j���̊Ԃɂ́A�z���������Z�b�N�X������B����͂���Ƃ��āA���̓W�F���_�[�B ���̃W�F���_�[�ɂ��ẮA���ꎩ�́A�Ӗ����Ȃ��A���ꂩ�琶�܂��Ό��ƌ�����Ȃ����̂��A���A���E�̏펯�ɂ��Ȃ��Ă���B �@���������w�I�ɁA�j�炵���A���炵�������߂�̂��A�A���h���Q���Ƃ����z�������ł��邱�Ƃ́A�悭�m���Ă���B �j���͂��̃A���h���Q�����������傳��A�����ɂ͏��Ȃ��B����ɔ]�̍\�����̂��̂ɂ��A������x�̐��������邱�Ƃ��m���Ă���B���̂��ߒj�́A���j���I�ȗV�т����߁A���͂�菗���I�ȗV�т����߂�Ƃ������Ƃ͂���B�i�����łǂ������V�т��j���I�ŁA�ǂ������V�т��j���I�łȂ��Ƃ͏����Ȃ��B���ꎩ�̂��A�Ό��ށB�j �@�����q�ǂ��̂����A�����������������m�łȂ��A�����I�ɁA�j���������̗V�т����߂���A�������j���̗V�т����߂��肷�邱�Ƃ́A�悭����B �������w�R�N�����炢�̂Ƃ��A�l�`���ق����Ă��܂�Ȃ��������Ƃ�����B�����Ŕ���ɓ����ō���Ă��炢�A���ӕ����ĐQ�����Ƃ�����B������Ƃ����āA���A�ǂ������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�����������ۂ͔��N�P�ʂŁA�l�q���݂�̂��悢�B�܂��������҂ɂȂ邩�Ȃ�Ȃ����́A�����Ɩ{���I�ȗ��R�ɂ��Ƃ����B �@�����������ɂ́A�j���̏������́A�������B���̒��̐l�����́A�ǂ������Ƃ�������āA�u�j�炵���c�c�v�u���炵���c�c�v�Ƃ������t���g���̂��A�悭�킩��Ȃ��B���ł́A�c�t���⏬�w�Z�i��w�N���j�ł��A�����߂��ċ����̂͒j�̎q�B�����߂ċ������̂́A���̎q�Ƃ����}�����蒅���Ă���B �@�r���i���ς��j�ŁA�̕��ɂ����܂����j���ƂȂ�ƁA�P�O�l�ɂP�l�Ƃ���Q�l�������Ȃ��B�Ƃ��ɍŋ߂̒j�̎q�́A�ǂ����i���i�����Ă��āA�n�L���Ȃ��B �@�u�j�̎q�炵���v�Ƃ������ƂɂȂ�A����Ȃ��ƂɁA�ŋ߂̏����̂ق����A����ۂǁi�j�̂炵���j�B ���Ȃ������́A�ƒ�ɓ���̂��H ���܂��ɏ����A�Ȃ����u�ȁv���A�u�����i���v�̕s�����j�v���x�ɂ����l���Ă��Ȃ��j���������̂́A�����ł����Ȃ��B ����A�j������ł͂Ȃ��B�������g�ł��A�u����ł����v�ƍl���Ă���l���A�Q���߂�������B ���Ƃ������Љ�ۏ�l����茤�����̒����i�Q�O�O�O�j�ɂ��ƁA�u�|���A����A�����̉Ǝ����܂��������Ȃ��v�Ɠ������v�́A��������T�O���ȏ�B�u�v���Ǝ���玙���ɕ��S���ׂ����v�Ɠ����������́A�V�V������B���A���̔��ʁA�u�i�j���̓����ɂ́j�����v�Ɠ������������Q�R��������I �@����_���n��ł��̃W�F���_�[�ɂ��Ęb������A�S���ҁi����ψ���ے��j���A�u���������b�͂܂����ł��B�����łȂ��Ă��A�ǂ̉Ƃ��A�ł̖��œ����������Ă���̂�����v�ƁB�u�v���Ǝ�������Ƃ����̂��A�����I�Șb�ł͂Ȃ��v�Ƃ��B���̘b�Ɏ��͋������B �@����͂Ƃ��������A����Ȍ���ɁA���̏�����������������͂����Ȃ��B�v�ɕs�������Ȃ��ӂ��Ă���B�u��Q��A�S���ƒ듮�������v�i�����ȁE�X�W�N�j�ɂ��ƁA�u�Ǝ��A�玙�ŕv�ɖ������Ă���v�Ɠ������Ȃ́A�T�Q���������Ȃ��B ���̐��l�́A�O��X�R�N�̂Ƃ������A��P�O�|�C���g���Ⴍ�Ȃ��Ă���i�X�R�N�x�́A�U�P���j�B�u�i�v�̉Ǝ���玙���j���Ƃ��Ɗ��҂��Ă��Ȃ��v�Ɠ������Ȃ��A�T�R���������B�Ȃ��A�A�����J�ł͍ٔ������������͎̂��������A����͍ٔ����x�̈Ⴂ�ɂ����́B�i�����H�j �@�ŁA���������i�Ⴂ�j�́A�O���̕v�w�Ɣ�r���Ă݂�ƁA�����킩��B �@�挎���A�I�[�X�g�����A�v�w���A�Q�g�A�䂪�ƂɁA�z�[���X�e�C�������B���傤�ǂP�������܂�؍݂��Ă������B �@���̕v�w�B�Ǝ��ɂ��ẮA�������Ɍ����ȂقǁA���S���Ă���̂��킩�����B�|�������͂������̂��ƁA�H��̂��ƕЂÂ��ȂǂȂǁB���{�̒j�����N�̂悤�ɁA�H��A�f�`���ƁA�e�[�u���̑O�ɍ����Ă���v�́A���Ȃ��B �@�H�����I���ƁA�����Ɨ����āA�H���A�����@���āA�˒I�ւ��܂��B�������Q�l�Ƃ��A�v�́A���̒n���ł́A�����ȃh�N�^�[�����ł���B �@������������������������ƁA���{�̒j���������A��{�I�Ȃ��������Ƃ������A�����ɑ���Ό����A����������B����͕ʂ̃I�[�X�g�����A�l�j���̘b�����A��͂�䂪�ƂɃz�[���X�e�C�����Ƃ��A������������Ă����̂́A�v�̂ق��������B �@�ŁA���̃��C�t������Ɍ����˂āA�������`�����قǂ����A���̕v���킭�A�u�I�[�X�g�����A�ł́A�T�O�����炢�̕v�́A�����Ő��������v�Ƃ̂��ƁB�u�T�O���v�Ƃ����������āA���́A�S�̂ǂ����ŁA�ق��Ƃ����̂��o���Ă���B �@���������@���̉Ƃ̋߂��ɁA�����ȋn�������āA�����͋߂��̘V�l�����́A���������̏W���ɂȂ��Ă���B���̂Ȃ�����炩�ȓ��ɂ́A�ǂ��������Ă���̂��͒m��Ȃ����A�������`���l�̘V�l������B �@���A���������V�l���ώ@���Ă݂�ƁA�������낢���ƂɋC�Â��B���̋n�̈�p�ɂ́A�����Ȕ������邪�A���̔��̐��b��A�S�~���W�߂��肵�Ă���̂́A���������̂݁B�j�������͂����A�C�X�ɍ����āA�����b������ł��邾���B ���͂������̑O��ʂ��Ďd���ɍs�����A���܂������āA�j�������������̎d�������Ă���p���݂��������Ƃ��Ȃ��B�����������I�����i�W�F���_�[�j���A����ȂƂ���ɂ������Ă���I +++�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �����ނ��������b���Â��܂��� �̂ŁA�ȑO�A���q�̈�l�ɏ����� �莆���A���̂܂܂����ɓ]�ڂ��� ���B �W�����_�[���l����A��̃q�� �g�ɂȂ�A���ꂵ���ł��B +++�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ ���W�F���_�[�́A�������H �@�l�Ԃ����肠���������Ƃ����̂́A���܂����i���Ɓj�̏W�܂肾��B�����́i�����Ɓj���A���ꂼ�ꕡ�G�ɂ����ŁA����������B �@�u�L�@�I�v�Ƃ����������́A�ǂ��������܂��Ȍ����������A�������u�����Ă���v�Ƃ����Ӗ��ŁA�����͗L�@�I�ɂ����ł���B�������ʂ��������āA�܂肻�ꂪ�������Ă��邩��Ƃ����āA�����ے肵�Ă͂����Ȃ��B �@�g�C�����ɂ����āA�l���Ă݂悤�B �@���O�́A�j���ʂ̃g�C�������m��Ȃ����A�I�[�X�g�����A�̗�Ԃł́A���Ƃȗp�Ǝq�ǂ��p�ɕ�����Ă���B���̒��������ɂȂ邩��ˁB �@���ꂩ����{�ł́A���O�g�C���̃h�A�́A�݂ȁA�܂��Ă���B�������A�����J�ł́A�g�p���Ă��Ȃ��g�C���́A�J���Ă������킵�ɂȂ��Ă���B �@�����O�܂ŁA�C�M���X�ł��I�[�X�g�����A�ł��A���O�g�C���ɂ́A�h�A�͂Ȃ������B�ʘH������ƁA�݂Ȃ��p�𑫂��Ă���p���A�O����ی����������B �@���̓��{�ł��A�g�C�����ł����̂́A�]�ˎ�����A�I���ɂȂ��Ă���ł͂Ȃ��̂��ȁB��������ɂ́A�V�c�ł�����A�L��������Ɍ����āA���ւ����Ă����Ƃ�����B���������́A�����̒��ɒu���ꂽ�A�i���܂�j�̒��ŁA��������Ă����B �@�ڂ����q�ǂ��̂���ł����ˁA�����́A���i�����j����ɂ܂����āA�������܂܂��K��֊�̂ق��Ɍ����āA���ւ����Ă�����B�����������i���悭�������A�����a�����Ȃ������B �@�����������́i���Ɓj���W�������Ă���ƁA�����ɕ��������܂��B���邢�͂��ꂪ�Ƃ��ɂ́A���ꂪ�Ό��ɂȂ�����A����肷��B�Z�b�N�X�Ƃ������t�́A���̓I�Ȃ��������������t�����A�W�F���_�[�Ƃ����̂́A���������������I�Ȕw�i���琶�܂ꂽ���������Ӗ����錾�t����B �@���������W�F���_�[�i�����I�����j���A���܂ꂽ�B �@���ꂪ�������Ƃ��A�������Ȃ��Ƃ��������f�́A���������P�[�X�̂����A�قƂ�ǁA�Ӗ����Ȃ��B�j��������l�N�^�C�ɂ���A�������͂��X�J�[�g�ɂ���A�u����͂��������v�Ǝv���̂́A���̐l�̏��肩������Ȃ����A�ے肵�Ă͂����Ȃ��B �@�������l�I�ȗ���ŁA�����ᔻ����͎̂��R�����ǂˁc�c�B �@�Ƃ����̂��A�������������Ƃ����̂́A�����ɂ��������悤�ɁA���ꂼ�ꂪ�A�������ɕ��G�ɁA���L�@�I�ɂ����ł���B�����Ă��̌��ʂƂ��āA���A�ڂ������������Ɍ��镶���Ƃ������̂����肠�����B �@���ے肷��ƁA�܂�́A�ʂ̑����̖ʂŁA����ɑ傫�Ȗ�肪�N���Ă���B���Ƃ��A�u���O�g�C���̒j���ʂ͂��������v�Ǝ咣���āA���O���A�����g�C���ɓ������Ƃ���ƁA�ǂ��Ȃ邩�B���̌��ʂ́A���O�ɂ����āA�z���ł���Ǝv����B�A�����J��������A�e�ŎˎE����邩������Ȃ��c�c�B �@�Ƃ��Ƀg�C���̖��́A�����Ɂu�j�v�Ɓu���v�Ƃ�����肪�����ł���B���̖��́A�l�Ԃ̎푰�ۑ��{�\�Ƃ����ł��邾���ɁA��������Ȗ��Ƃ����Ă��悢�B���������܂Ŕے肵�Ă��܂��ƁA�����Ƃ������x���̂��̂܂ŁA���������Ȃ��Ă��܂��B �@�q�ǂ��ɂ���A�u���l�̎q�ǂ����A�����̎q�ǂ����A�q�ǂ��͎q�ǂ��B�l�ނ̋��ʂ̍��Y�v�Ȃǂƍl�����Ȃ����Ȃ����A�����܂Ŏ����̍����A������i������������j���Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂łɂ́A�܂��܂����Ԃ�������B �@�����悤�ɁA�u�j�������A�����B�����A�g�C�����g�������v�ƍl������悤�ɂȂ�܂łɂ́A�܂��܂����Ԃ�������B������W�F���_�[�ɂ܂���肪��������Ă���̂��Ƃ��낤�ƁA�ڂ��́A�v���B �@�������ˁA�ڂ��͍ŋ߁A���������s���S�ŁA�������炯�̕����ɁA�ǂ���������������悤�ɂȂ��Ă�����B�������낢�Ƃ������A�y�����Ƃ������B �@���Ƃ��Ήf��w�^�C�^�j�b�N�x�ɂ��Ă��A�W���b�N�ƃ��[�Y���������炱���A�������낢�f��ɂȂ����B�������̉f��̒��ɁA�W���b�N�ƃ��[�Y�����Ȃ���A���̉f��́A�����́A�{���ɂ����́A�D�̒��v�f��ł����Ȃ������B���������낤���B �@�܂�ˁA���̃W���b�N�ƃ��[�Y���A�u�j�v�Ɓu���v�Ƃ����킯�B�����Ă��̐�ɁA���O�g�C��������Ƃ����킯�B �@���Z�����A�A�����J�ł́A�A���o�C�g�ŁA�Ԃ�B�����𒅂Ă���B���O�́A��������������Ǝv���B�ڂ����A�����悤�ȋ^��������Ƃ͑����B���Ƃ��Ή����̃V���c�Ńz�e���̒���������Ƃ͂ł��Ȃ��B���������̃V���c�ɐF�����A�K����`���A�s�V���c�Ƃ����Ƃ���A�z�e���̒���������Ƃ��ł���B �@�����A�V���c�Ȃ̂ɂˁB �@�܂肱�ꂪ�A�ڂ��������A�i�����̖��Ɓj�̈�Ƃ����킯�B �@���������Ƃ����āA���������i���Ɓj�́A���ՓI�Ȃ��̂ł��Ȃ���A��ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B����ƂƂ��ɁA�ς肦����̂����A�ǂ�ǂ�ς��Ă��A���������������Ȃ��B���ɂ���Ă��A�������B���O�������悤�ɁA�u�p�����E�v���C�x�[�g�Ƃ�����̋@�\������ԁv�ɂ��Ă��悢�B �@���O���A���z�ƂȂ�A����������Ă����āA���ɖ₤�Ă݂�悢�B���Ƃ̔��f�́A��O�ɔC���邵���Ȃ����ǂˁB �@�������ˁA�ڂ��ɂ́A����ȋꂢ�o��������B �@����Ƃ��ˁA�j�q�g�C���̑�փ{�b�N�X�ɓ����Ă����Ƃ��̂��Ƃ���B�ڂ����AK��w�Ŋw���������Ƃ��̂��Ƃ���B �@���̃{�b�N�X�́A�ׂ̏��q�p�g�C���Ƌ����ɂȂ��Ă����B�܂肻�̈�������A���q�p�g�C���ɐH�����ތ`�ŁA�����ɂ������B �@���̃{�b�N�X�ɂ�����ł���ƂˁA���̑O�̃{�b�N�X�ɁA��l�̏��q�w���������Ă����B�g�C���̕ǂ̉��̂ق��ɁA���Z���`���x�̂����܂��������B �@�ڂ��́A�����o���̂͂܂����Ɗ����āA���̂܂ܐÂ��ɂ��Ă����B���ƂȂ��A���������̂��Ǝv���B �@�Ƃ��낪����A���̏��q�w���́A������̃{�b�N�X�ɂڂ�������Ƃ��m�炸�A�u���u���u�[�A�O�V���O�V���ƁA��ւ����n�߂��B �@���̏L�����Ƃƌ�������Ȃ������B�җ�Ȉ��L���A�ǂ̉��̂����Ԃ���A�e�͂Ȃ��A�ڂ��̃{�b�N�X�̂ق��ɗ��ꂱ��ł����B���̂��������L�������I �@���̏��q�w���́A���ꂩ��p�𑫂��āA�o�čs�����B�ڂ��́A���̂Ƃ��A�u����ȏL���̂�����̂́A�ǂ�ȃ��c���v�Ǝv���āA�}���ŁA�����̗p�𑫂��A�O�֏o�Ă݂��B �@�ڂ��́A���̏��q�w�������āA�A�R�Ƃ����ˁB �@�}���ŘL���ɏo�Ă݂�ƁA���̏��q�w���͂��܂����\��ŁA�L�����������ɕ����Ă����Ƃ��낾�����B �@�ŁA�Ȃ����R�Ƃ��������āc�c�H�n�n�n�B���́A���̏��q�w���́A�ڂ����D�ӂ������Ă����A���w���̂l���������炾��B�p���Ȃ̊w���łˁB�ڂ����A�f�[�g��\�����ށA���O�̏����������B �@�������ȁA�����������Ȃ�B�ڂ��́A���̓��ȗ��A���̂l����ɂ́A�ʂ̈�ۂ������Ă��܂����B������邽�тɁA���̈��L���v���o���A�ǂ����Ă�����ȏ�̃A�N�V�������N�������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B �@����ς�ˁA���O�g�C���́A�j���ʁX�̂ق���������B���O�́A�����ł��\��Ȃ��ƌ������ǁA�ڂ��́A�����́A�v��Ȃ��B�킩�邩�ȁA���̋C�����B �@���������ӎ��������Ƃ́A�ƂĂ��d�v����B�܂����O�̃G�b�Z�[�ɁA���ꂱ��R�����g�����Ă݂��B �@���������В��ɂ́A�������������ق���������B�����猩��ƁA�_�̏�̐l�Ɍ����邩������Ȃ����A�ォ�猩��ƁA���������ӂ��Ɍ�����̂��A����Ȃ��̂���B���������C���́A���̂��O�ɂ͂킩��Ȃ���������Ȃ����ǁc�c�B �@�u�n���[�A���������b�ɂȂ��Ă��܂��v���炢�́A���������̂��B �@�ł͂ˁB������́A��������A���Ղ�B�ɂ��₩�ɂȂ��B �@�g�������@���@���������@�������I �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�͂₵�_�i ���j�������Q�掖�� �b���A�����E�����Ă������A���������A�[���Ȗ�������B �@�j�Ə�����ʂ���̂́A���̐l�̏��肾���A�u�j�́A�d���A���͉Ǝ��v�ƍl����̂��A���̐l�̏���B �@�������A���ꂩ��̓��{�ł́A�������Ƃ��āA����Ȃ��Ƃ������Ă��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ�B �@�����܂ł��Ȃ��A���q���ɂ��J���͂̕s���ł���B���������[���Ȗ�肪�������ŁA�Ǝ��A�q��Ă���������ꂽ���������̔ߖ��A����܂��傫���B ���{�J���@�\�̒����ɂ��A��Ǝ�w�A�A�Ǝ�w�i��ٗp��w�j�ɂ�����炸�A��W�O�`�W�T���̏������A�u�玙�ɃX�g���X��s���������Ă���v�Ƃ����B���̒��ł��A�u�Ђ�ς�ɂ���v�Ɠ������l���A�R�O���O�������B �@�q��Ă͏d�J���ł���B��u����Ƃ��C�������Ȃ��B�����̂͂������q�ǂ������e�ɂƂ��ẮA�Ȃ�����ł���B������Ƃ������f���A�厖�̂ɂȂ���Ƃ������Ƃ��A���Ȃ��Ȃ��B �@���̖����������邽�߂̍őP�̕��@�́A�j�������Q�掖�Ƃ̊g�[�ł���B�j���̃J�x��j��A�W�F���_�[�i�����ʁj����������B�͂����茾���A�v�ɁA�����ƈ玙�S������B���̈ӎ��������Ă��炤�B���̈���ŁA���������ɂ��A�d�������Ă��炤�B �@�����Ő��{�́A�u�Q�O�Q�O�N�ɂ́A�w���I����ɂȂ鏗�����A�R�O���O��ɂȂ邱�Ƃ�ڕW�Ƃ���v�i�דc���[�����̎��I���k��j�Ƃ������j��ł��������B�v�ɂ��̕������A�Ǝ��A�玙�S���Ă��炨���Ƃ����킯�ł���B �i�����̎Љ�i�o�ɂ���āA�����̕��S�����炻���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���̕��A�j���ɂ��A�Ǝ���玙�ɁA�����Ɩڂ������Ă��炨���Ƃ����l�����ɂ��B�j���������̕��j�ɂ́A������A�d�v�ȈӖ����B����Ă���B �@�����̕��S�����炷���Ƃɂ���āA���ݐi�s���̏��q���Ɏ��~�߂������悤�Ƃ����킯�ł���B�����܂ł��Ȃ��A���q���̍ő�̌����́A�i��e�̕s���ƐS�z�j�B���̕s���ƐS�z����������Ȃ�������A���q���ɁA���~�߂������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@�݂�ȂŐi�߂悤�A�j�������Q�掖�ƁI�@���{�̂��߂ɁI�@�c�c�Ə����A�͂Ƃ���ŁA���������A����l���Ă݂悤�B ���������� �@�q�ǂ��́A��������ƂƂ��ɁA�����炵�����A���肠���Ă����B �@�킩��₷����Ƃ��ẮA�u�j�̎q�炵���v�u���̎q�炵���v������B �@�����A���̂̍l�����A�������ȂǁB�܂肱�����Ď����̂܂��ɁA�j�̎q�Ƃ��Ă̖����A���̎q�Ƃ��Ă̖������`�����Ă����B������u�����`���v�Ƃ����B �@ �@���������u�����v����������A���̖����ɂ����āA�e�́A�q�ǂ���L���Ă����B���ꂪ�q�ǂ���L���R�c�Ƃ������ƂɂȂ�B �@�q�ǂ����u���ԉ�����ɂȂ肽���v�ƌ�������A���������A�u����A�����ˁB���Ă��Ȏd���ˁv�ƁB���ŁA�u���Ⴀ�A���x�A��������Ԃł����ς��ɂ��悤�ˁv�Ȃǂƌ����Ă��̂��悢�B �@�������Ďq�ǂ��́A�g�̂܂��ɁA�u���ԉ�����炵���v�������Ă����B���R�ƁA�A���Ɋւ���{���ӂ��Ă������肷��B �@���������̖������A�������邱�Ƃ�����B �@���̂��������A���́A���Z�Q�N�̏I���܂ŁA�����ƁA�p���I�ɁA��H�ɂȂ�̂����������B���ꂪ�₪�āA�H�w���u�]�ƂȂ�A���z�w�Ȏu�]�ƂȂ����B���������Z�R�N�ɂȂ�Ƃ��A�S�C�ɁA�����ɁA���w���R�[�X�ւƁA�ς����Ă��܂����B�����́A�����������ゾ�����B �@�����Ŏ��́A�����ւ�ȍ�����ԂɂȂ��Ă��܂����B�H�w������A���w���ւ̑�]�g�ł���I �@�����́A�܂荂�Z�R�N�������̎ʐ^������ƁA���́A�ǂ̊���A�Â�����ł���B�S����Ԃ��ň��������B�����_�l�����āA�u���O���A�Ⴂ����ɂ��ǂ��Ă��v�ƌ����Ă��A���́A���̍��Z�R�N�������́A�f��B���ɂƂ��ẮA���ꂭ�炢�A����Ȏ��ゾ�����B �@���̖��������ɂ��āA����u����ŁA�b�������Ă�������B����ɂ��āA���̂��ƁA�����l�̒j�����A�����������B�u�����������āA�ǂ������S����Ԃł��傤���ˁH�v�ƁB �@���́A�Ƃ����̎v�����ŁA�����������B �@�u����Ȓj���ƁA���₢�⌋�����āA�����A���̒j���ƁA���������肠�킹�Ă���悤�ȐS����Ԃł��傤�ˁv�ƁB �@�������������ƁA�����ւ�I�������������ƁA�����ł́A�����v�����B �@�������Ȃ��Ȃ�A��������������������A�ǂ��v�����낤���B����ł��A����������Ԃ��������āA���Ƃ�����Ƃ��܂�����Ă������Ǝv�����낤���B����Ƃ��c�c�B ���������Ƃ����̂́A����������Ԃ������B�����āA�y���l���Ă͂����Ȃ��B �@�������ꌾ�B�悭�u�L����w�ցc�c�v�u�L�����Z�ցc�c�v�ƁA�q�ǂ���ǂ����ĂĂ���e������B �@�������L����w��L�����Z�֎q�ǂ�����ꂽ����Ƃ����āA���̎q�ǂ��̖������m������킯�ł͂Ȃ��B�u���i��������A�ǂ��Ȃ́H�v�Ƃ����������Ȃ��܂܁A�q�ǂ����w�֑��肱��ł��A�Ӗ��͂Ȃ��Ƃ������ƁB �@�����P�O�N�قǑO���낤���A����Ȃ��Ƃ��������B �@�Q�l�̏��q���Z�����A���̉ƂɗV�тɗ��āA�����������B �@�u�搶�A���������x�A�r�r��w�ɍs�����ƂɂȂ�܂����v�ƁB �@�֓��n���ł́A���Ȃ�L���ȑ�w�ł���B�����Ŏ����A�u�����Ƃ���֓���ˁB�ŁA�w���́c�c�H�v�ƕ����ƁA���������߂�����l�q�ŁA�u���ۃJ���P�C�w���c�c�v�ƁB �@�����ł���ɁA�u���A���̍��ۃJ���P�C�w�����āH�@���������́H�v�ƕ����ƁA��l�Ƃ��A�u�������ɂ��A�킩��Ȃ��c�c�v�ƁB �@��w�֓����Ă��A��������邩�A�킩��Ȃ��Ƃ����̂��I �@���������̎p�́A�����g�̎p�ł��������B���͍��Z�𑲋Ƃ���ƁA�j��w�̖@�w���i�@�w�ȁj�ɓ������B�����������Ŗ������������܂����킯�ł͂Ȃ��B���̂��ƁA��w�𑲋Ƃ������ƁA���Ђ֓��Ђ����Ƃ����A���������́A���̂܂܂������B �@�܂��Ɂi����ȏ��[�ƁA���₢�⌋�������悤�ȏ�ԁj�������B �@�܂�i�{���Ɏ����i�݂����R�[�X�j�ƁA�i�����ɐi�݂���R�[�X�j�̊Ԃɂ́A�傫�Ȃւ����肪�������B���̂ւ����肪�A���̐��_��Ԃ��A���Ȃ�s����ɂ����B�₪�āA���́A�c�t���ŁA�����̐����铹���݂������A���̓��ƂāA�����āA�y�ȓ��ł͂Ȃ������B �@�c�c�Ƃ������ƂŁA�q�ǂ��̖����`���ƁA�����������A�����āA���Ղɍl���Ă͂����Ȃ��B�����g���A���̋��낵�����A����Ƃ����قǁA�o�����Ă���B ���c��������Ɓc�c �@���T���邠���肩��A�q�ǂ������́A�}���Ɂu���v�ւ̊S�������n�߂�B����͂������A���I�s�ׂɂ��Ă��A����炪�������ʂȈӖ��������Ă��邱�Ƃ�m��B �@�j�����������ӎ����A�������j�����ӎ�����悤�ɂ��Ȃ�B�u�j�v�Ɓu���v���A��ʂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��Ȃ�B������e���j�ł���A��e�����ł��邱�Ƃ��m��B �@���̂��߁A���̎����A�d�v�Ȃ��Ƃ́A���́u���v�ɑ��āA������߂������������Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB���ɂ��āA�䂪�ӎ���A�Â��C���[�W���������Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB�j�Ə��̍��ʈӎ��i�W�F���_�[�j�ɂ��ẮA�������A�_�O�ł���B �@�c������ł́A�u�j�͂�����Ă���v�u���͌����v�Ƃ������������́A�^�u�[�ł���B�u�j�͋����v�u���͎ア�v���A�^�u�[�ɂȂ����B �q�ǂ��u�搶�́A�ǂ����ă`���[����́H�v ���u�`���[�C�i���Ӂj����̂��A���₾����ˁv �q�ǂ��u���ӂ̂ق���������v ���u���ӂ��Ă��A�ǂ����A�N�����́A�ڂ��̌������ƂȂǁA�����Ȃ�����v �q�ǂ��u�����A�����A�����ƁA�����v ���u�����H�@��������A�`���[�͂��Ȃ���v�ƁB ���W�F���_�[�́A�Ȃ����܂��̂��H �@�j�Ə��B���̊Ԃɂ́A�����I�ȈႢ�͂���B���̈Ⴂ�܂ŁA���z���āA�j�Ə��������ł���Ƃ������Ƃ́A���肦�Ȃ��B�u���~�v�̖�肪�A�����ɂ����ł���c�c�B �@�c�c�ƁA�l����̂��A�ŋ߂́A�ǂ����Ǝv���悤�ɂȂ����B �@�t�B�������h�ɗ��w���Ă���A�I�[�X�g�����A�l�̏��q�w��������Ȃ��Ƃ�b���Ă��ꂽ�B �@�ޏ��́A�t�B�������h�ŁA���z�w�̕������Ă���B�Q�Q�ł���B���킭�A�u�݂ȁA�T�E�i����D���B�T�E�i�ł́A�������A�ӂ��B�V��j���̋�ʂ͂��Ȃ��B�^�I���Ŕ����B�����肷�邱�Ƃ����Ȃ��v�ƁB �@���������b���ƁA�u�{���ł����H�v�ƁA���x�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǁA���{�l�̐��ӎ��ɂ́A�Ɠ��̂��̂�����B�܂�t�B�������h�ł́A�R�O�`�S�O�̒j���ƁA�P�O�`�Q�O�̏����Ƃ̍����i�T�E�i�j���A��������I�Ȃ��ƂƂ��āA���R�ƂȂ���Ă���Ƃ����B �@�ƂȂ�ƁA�i���ӎ��j�Ƃ́A�����H�@����Ɂi�����j�Ƃ́A�����H �@�����_�A��`�q�_�A�����_�Ȃǂ��A���݂��Ă���B�����Ă��ꂼ��̐l�������A�����̗���ŁA�u�W�F���_�[�́A���������v�u�W�����_�[�́A�K�v���v�ȂǂƁA�����B�ŋ߂ł́A�ނ���A�u�j�͎d���A���͉Ǝ��Ƃ����A���{���������Ɠ��̂悳�i�H�j���A�Ċm�F���悤�v�Ɛ����W�c�܂ŁA���ꂽ�B�����Ƃ̒��ɂ��A���������l����������l�͑����B �@���̍���ɂ́A���{�×��́A�Ɠ��̒j�����ڎv�z������B�u�j����A�������v�Ƃ����A���̒j�����ڎv�z�ł���B �@���̂Ƃ���A�c���̍c�ʌp�����������ŁA�W�F���_�[�_���A�ɂ��₩�ɂȂ��Ă����B����̐V���i�����V���j���A���̖��ɂ��āA���W�L������ׂĂ����B �@�ŁA���̌��_�B �@���������ɂ����āA�j�Ə����A�l�ԂƂ��ċ�ʂ���ق����A���������B�܂������A���������B�j�̎q�́A�j�̎q�炵����Ă�Ƃ��A���̎q�͏��̎q�炵����Ă�Ƃ����l�����A���̂��̂��A���������B �@����Ȃ��Ƃ́A���̎q�ǂ��������A���̂Ƃ��ǂ��̕����̒��Ō��߂Ă������Ƃł����āA�Љ�̖��ł��Ȃ���A����̖��ł��Ȃ��B �@���̖��ŁA�����Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃ́A�j�ł��邩��A���ł��邩��Ƃ������R�����ŁA�l�ԓI�A�Љ�I���ʂ��A�l�́A�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƁB���ׂẮA���̈�_�ɁA���_�͏W���B |
|
||
���s�X�n�������ɂ��āA�ЂƂ茾 �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �����P�O�N�A�Ƃ��ɒ��S���ɂ����� �l�f�p�[�g���|�Y���Ă���Ƃ������́A �u�s�X�n�������v���A���̂� ���ɂȂ�B ����Ȏs�̗\�Z���A�������ꂽ�B ���A�������A���������B�ւ�B �s���g���Y���Ă���B ��s���̗���ŁA�s�X�n�������� ���ɂ��āA�l���Ă݂����B �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �i���y���A�N���b�N�j�i�����́��ł͂Ȃ��A�����́����N���b�N���Ă��������j �@�܂��A�������B�u�X�֍s���v�Ƃ����A�������v�w�̂����́A�u�O�H�v���Ӗ�����B�ق��Ɂu�f��v�B���m�́A�߂����ɔ���Ȃ��B�u�X�͍����v�Ƃ�������ς��Œ艻����Ă��܂��Ă���B �@����ɊX�́A��҂ɐ�̂���Ă��܂����B�[�������ɂ����āA�X������Ă݂�ƁA���ꂪ�悭�킩��B�������̔N��̂��̂ɂ́A���ꏊ����A�Ȃ��B���������u���v�����A�̐S�́u�S�v���Ȃ��B���̂��Ƃ́A���Ƃ��Ύ��ꌧ�̒��l�̒��Ɣ�r���Ă݂�ƁA�悭�킩��B �@���l�̒��ɂ́A������Ƃ���Ɂu�y�����v������B���́u�y�����v���A���s�[�^�[�ށB�u�܂��s�������v�Ƃ����C�������������Ă�B�s�X�n��������������Ƃ������Ƃ͂ǂ��������Ƃ��A�����m�肽����A��x�A���l�̒�������Ă݂�Ƃ悢�B�����ł͎�҂������A�A���o�C�g�̓X���Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�u���̈���v�Ƃ��āA�����Ă���B���̈ӋC���݂Ƃ������A�M�C���A�K���K���Ɠ`����Ă���B �@�s�X�n�����������邱�Ƃɂ́A�ًc�͂Ȃ��B����͂���Ō��\�Ȃ��ƁB����������Ȑŋ����g��Ȃ�����ꂪ�ł��Ȃ��Ƃ����̂ł���A�u�H�v�}�[�N�Ƃ������ƂɂȂ�B���̂悤�ɁA�ŋ����^�������Ȃ���A���������ێ��ł��Ȃ��Ƃ����̂ł���A�������ȂǁA����������߂��ق����悢�̂ł́H�@���̗���A�l�̗���́A���̎���A����̐l�X���A�����Ō��߂邱�ƁB���܂ł��u�鉺���v�z�v�ɌŎ�����ق����A���������B �@�O���ȂǁA�ǂ�������Ă��A�w�O�ȂǂƂ����̂́A�ǂ����ՎU�Ƃ��Ă���B�u�w�O�v�ɂ������K�v�́A�Ȃ��B �@���A����ł��������A�Ƃ������Ƃł���A�����ł����u�y�����v��n�o���邵���Ȃ��B���A�����ł����Ă͂����Ȃ��B���Ƃ��d�S���̍��ˉ��𗘗p���āA���[���������Ȃ���̂����N�O�ɂł����B�܂��Ɂu���������v�����A���ł́A�ՌÒ������Ă���B�u�����v�u�܂����v�̂ق��A��肪�����ɂ��A�u�����v�B���̂��Ƃ��A���̒��l�̒��Ɣ�r���Ă݂�ƁA�悭�킩��B �@�ے���肵�Ă��Ă͂����Ȃ��B �@�ŁA�������v�w�̂悤�Ȏ҂��A�X�֍s���悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�ǂ�������悢���H �@�ЂƂɂ́A��ɂ��������悤�ɁA�u���ꏊ�v������Ăق����B���Ƃ��ΐ��s�́A�u�m�i����j�̓s�v�ƌĂ�Ă���B���̂��Ƃ�����킩��悤�ɁA���̋��ꏊ��������Ƃ���ɂ���B���N��V�N�̐l�����ł��A���C�ō����ċx�߂�悤�ȏꏊ���A����B �@�c�c�����������܂ŏ����āA�u������Ƒ҂Ă�v�Ƃ����A�u���[�L�������Ă��܂����B �@���́A���̋t�B�܂�A�s�́A���̎肱�̎���g���āA���������A�s�̒��S���ɏW�߂悤�Ƃ��Ă���B�R���T�[�g�z�[���ɂ��Ă��A�f��قɂ��Ă��A�X�̒��S���ɂ����Ȃ��B����ɖ@���ǂ��͂��߁A���⌧�̏o��@�ւɂ��Ă��A���ׂĊX�̒��S���ɏW�߂��B�������������͂�����u�s�ցv�Ɗ����Ă���B�i���ہA�������ĕs�ւɂȂ��Ă��܂����I�j �@�ł���A�R���T�[�g�z�[����f��ق��A�x�O�ֈڂ��Ăق����B���⌧�̏o��@�ւɂ��Ă��A�������B���̂ق����A�����ƕ֗��B�`���Łu�O�H�v�̂��Ƃ����������A�O�H�ɂ��Ă��A�x�O�̃��X�g�����̂ق����A�u�����v�u���܂��v�B �@�X���X�łȂ���Ȃ�Ȃ����R�ȂǁA�t�������Ă��o�Ă��Ȃ��B�s�����Ƃ���́A���ǂ́A�u�鉺���v�z�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�u�鉺���v�z�v���]���āA�u�w�O�v�z�v�ƂȂ����B�������鉺���ɂ��Ă��A�u����i���݁j�v����������Ă���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B��������߂�̂́A��͂�A�������A�s���Ƃ������ƂɂȂ�B �@�Ȃ��́A�X�J�{���[�Ղ�ɍs���̂��H �@�@�p�[�X���C�A�Z�C�W�A���[�Y�}���[�A���^�C���c�c �@�@�����ʼn�����l�ɁA��낵���l�B �@�@�Ȃ����āA�ޏ��́A���Ă͂ڂ��̐^�̗��l����������c�c�B �@�ǂ������킯���A���̌��e�������Ă���Ƃ��A�T�C�����ƃK�[�t�@���N�����̂��ėL���ɂȂ����A�u�X�J�{���|�E�t�F�A�v�i�r�������������������� Fair�j���v���o�����B �@�ǂ����Ă���H �@�X�J�{���[�́A�����̎��ォ��A�C�M���X���̏��l�̏d�v�Ȍ��Տ�ł������B�����ɂ͓����t���i�t���W�܂�A���N�W���P�T������A�S�T���Ƃ��������Ԃɂ킽���āA�����́u�s�v���J���ꂽ�Ƃ����B�̂́A�C�M���X�͂������A�嗤��������l�������W�܂����Ƃ����B �@���̃X�J�{���[�ցA���h����n�Ԃ������ɐς�ʼn^��ł����l�������̂��낤�B�p�[�X���C�A�Z�C�W�A���[�Y�}���[�A�^�C���Ƃ����̂́A���h���̖��O�ł���B������^��ł����l�ɁA���������j���A�u�X�J�{���[�ɏZ�ތ����l�ɁA��낵���v�ƁA��肩���Ă���c�c�B���̉̂́A����������i���̂������̂ł���B �@�c�c�܂�A���������u�y�����v���A�Ȃ��B�߂������ȁA���̕l���s�́u�s�X�n�v�ɂ́A�Ȃ��B�u�s�i�����j�v���̂��̂��A�Ȃ��B���ȂǁA�X��������тɁA�u����Ȃɐŋ������_�Ɏg���āc�c�v�Ƃ����{����肪�A��ɗ��B�܂������v���Ă���̂́A�������ł͂���܂��B�u���v�Ƃ����u���v�����A�������܂ō��ɂ���K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B �@�c�c�Ƃ������ƂŁA���̘b���A�����܂ŁB�����ꌾ�B��������ȏ�A�ŋ������_�Ɏg�����Ƃ����́A��߂Ăق����I �@�Ȃ����łȂ���A�s�́A�i�q�l���w�𒆐S�ɁA��P�T�O�w�N�^�[���i�P�T�O�w�N�^�[�������I�j���A�u���S�X�n�������d�_�n��v�Ƃ��A���̊�{�v��̔F����A���ɐ\�����Ă���B���̐\�����ʂ�A���͖@���ɂ��ƂÂ��A�s���d�_�I�Ɏx�����Ă����Ƃ����B �@���ށc�c�B���x���������A�l���s�͂��ẮA�H�Ƃ̒��������B�ǂ����čH�Ƃ̍Đ���������܂Ȃ��̂��H�@�s�X�n�����������邩�ǂ����́A���̌��ʂƂ��āA���܂邱�ƁB�����s���Ȃ�A�u�x�O�n�H�Ɗ������d�_�n��v�̔F����A���ɐ\������̂����c�c�H |
|
||
���߂����l�Ԃ̐S �@��e�ɋs�҂���Ă���q�ǂ�������B�ŁA���������q�ǂ����e����藣���A�{�݂ɕی삷��B�������قƂ�ǂ̎q�ǂ��́A����������Ԃł���Ȃ�����A�u�ƂɋA�肽���v�Ƃ��A�u�}�}�̂Ƃ���ɖ߂肽���v�ƌ����B�����b���Ă��ꂽ�A�j�s�̏��w�Z�̍Z���́A�u�q�ǂ��̐S�͔߂����ł��ˁv�ƌ������B �@���������u�߂��݁v�Ƃ����̂́A�q�ǂ������̂��̂ł͂Ȃ��B���������ƂȂ����āA�������̔߂��݂Ɨׂ肠�킹�ɂ��Đ����Ă���B���������߂��݂Ɩ����Ő����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ƒ�ł��A�E��ł��A�Љ�ł��B �@���͎Ⴂ����A�炢���Ƃ�����ƁA�����ЂƂ�ŁA���̉́i���c�r�Y�쎌�u��҂����v�j���̂��Ă����B �@��N�̍s�����́@�ʂĂ��Ȃ����� �@�@���̂ɂȂ��@������������ �@�@�N�͍s���̂��@����Ȃɂ��Ă܂� �@�������̂Ƃ���̏ォ��A�_�l���������Ă�����A�����Ƃ����������ɂ������Ȃ��B�u�����A�����Ă���̂���߂Ȃ����B�������邱�Ƃ͂Ȃ���B����ő����A���̎{�݂ɗ��Ȃ����v�ƁB���������́A�_�̎{�݂ɂ͓���Ȃ������B���邢�͓�������������ŁA���͂����Ƃ����������ɂ������Ȃ��B�u�͂₭�A���Ƃ̐��E�ɖ߂肽���v�u�݂�Ȃ̂Ƃ���ɖ߂肽���v�ƁB����͂Ƃ���Ȃ������A���̐��E���鎄�����l�Ԃ̔߂��݂ł�����B �@���A���͌����ɐ����Ă���B���Ȃ��������ɐ����Ă���B���A�݂Ȃ��݂ȁA�������肽�����̒��ŁA�K���ɕ�炵�Ă���킯�ł͂Ȃ��B���ɂ́A������̂�����t�Ƃ����l������B���邢�͐����Ă���̂��A�炢�Ǝv���Ă���l������B�܂��ɐl�ԎЉ�Ƃ������N�̒��ŁA�s�҂��Ă���l�͂�����ł�����B���A����ł��������͂��������B�u�ƂɋA�肽���v�u�}�}�̂Ƃ���ɖ߂肽���v�ƁB ���A�ꂵ���l�����ցA ��������ɉ̂��܂��傤�B ��������ɉ̂��āA���������܂��傤�I �@��҂��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�N�̍s�����́@�ʂĂ��Ȃ����� �@�@�@�@�@�@�@���̂ɂȂ��@������������ �@�@�@�@�@�@�@�N�͍s���̂��@����Ȃɂ��Ă܂� �@�@�@�@�@�@�@�N�̂��̐l�́@���͂������Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@���̂ɂȂ��@�Ȃɂ�T���� �@�@�@�@�@�@�@�N�͍s���̂��@���Ă��Ȃ��̂� �@�@�@�@�@�@�@�N�̍s�����́@��]�ւƑ��� �@�@�@�@�@�@�@��ɂ܂��@�z���̂ڂ�Ƃ� �@�@�@�@�@�@�@��҂͂܂��@�����͂��߂� �@�@�@�@�@�@�@��ɂ܂��@�z���̂ڂ�Ƃ� �@�@�@�@�@�@�@��҂͂܂��@�����͂��߂� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�쎌�F���c�@�q�Y �@���������A�w������A�m�v��F�Ƃ����F�l�������B��Z�N�قǑO�A���������o���Ŏ����A�~��i�����E�ꎵ���I�A�]�ˏ����̕��t�j�̌����ł́A���l�҂������B���̔ނƁA����̖�c�R��n������Ă���Ƃ��A�����ӂƁA�u�l�Ԃ͊�]���Ȃ�������A���ʂˁv�ƌ����ƁA�ނ͂����������B�u�ьN�A����͈Ⴄ��B���ʂ��Ƃ����āA��]����B���˂Ίy�ɂȂ��Ǝv���̂́A���h�Ȋ�]����v�ƁB �@���ꂩ��O�ܔN�B���͂m�v�N�̌��t���A���x�����x�����̒��Ŕ��������Ă݂��B���������A�����Ō����邱�Ƃ́A�u���ʂ��Ƃ͊�]�ł͂Ȃ��v�Ƃ������ƁB���͂������̐��ɂ��Ȃ��m�v�N�ɁA���������͎̂��h�Ȃ��Ƃ�������Ȃ����A�ނ͐������Ȃ��A�ƁB�����ǂ����邩�킩��Ȃ����A�ǂ��Ȃ邩�킩��Ȃ����A�������Ō�̍Ō�܂ŁA�����ɐ����Ă݂�B�����ɐl�Ԃ̑���������B�����������������B������A���ʂ��Ƃ́A�����Ċ�]�ł͂Ȃ��A�ƁB �c�c����A�{���̂Ƃ���A���������Ɍ����������Ȃ���A���ƂČ����ɂӂ���Ă��邾����������Ȃ��c�c�B�Ƃ��ǂ��u�m�v�N�̌��������Ƃ̂ق��������������̂��Ȃ��v�Ǝv�����Ƃ����̂Ƃ���A�����Ȃ����B�����A�u��҂����v���̂��Ă݂����A�O�Ԃ��̂��Ƃ��A�ӂƁA�S�̂ǂ����ŁA��R���o�����B�u��N�̍s�����́@��]�ւƑ����c�c�v�Ɖ̂����Ƃ��A�u�{���ɂ������Ȃ��H�v�Ǝv���Ă��܂����B �i�O�Q�|�P�P�|�Q�O�j |
|
||
���R�P�N�Ԃ�̖� �@���傤�ǎO�\��N�O�̑��ƃA���o���ɁA���͂����������B�u��Z�Z��N�ꌎ����A�ߌ�ꎞ�ɁA�i����́j�ΐ��̑O�ŌN��҂v�ƁB������������Ƃ��A���͔��Ώ�k�̂��肾�����B�����̎��͓�\��B���傤�ǃA�[�T�[�E�N���[�N����́u��Z�Z��N�F���̗��v�Ƃ����f�悪�b��ɂȂ��Ă�������ł�����B���ɂƂ��ẮA�O�\��N��̎����Ƃ����̂́A�F���̗��Ɠ������炢�A�u���肦�Ȃ������v�������B �@�������A���̎O�\��N���߂����B�ꌎ����ɋ���w�ɂ��肽�ƁA�̂�˂��h���悤�ȗ₽���J���~���Ă����B�u�~�̋���͂����������v�ƌ����ƁA���[���̂�k�킹���B�Ƃ���A�����̎v���o���ǂ��Ɠ��̒����P�����B�b���������Ƃ͂����ς�����͂��Ȃ̂ɁA���t�ɂȂ�Ȃ��B�ׂ��H�n�������������āA�₪�ċߍ]���s��̃A�[�P�[�h�ʂ�ɏo���B�����Ȃ�C�Y���邨�₶�̐��ŁA�ɂ��₩�ȂƂ��낾�B���A���̓��͋x�݁B�u������͌ܓ�����v�Ƃ������莆���A����߂����B�J�j�̏L���������A�����@�������B �@�����̏������������A�C�ɂȂ�n�߂��̂͐��N�O���炾�����B����܂ŁA�A���o�������邱�Ƃ��A�قƂ�ǂȂ������B�������̖{�I�̑O�ŁA����t�̋������͂��āA�w�ґR�Ƃ��Ďʐ^�ɂ����܂��Ă��鎩�����A�ǂ������₾�����B��������Z�Z��N���߂Â��ɂ�āA���̓������̐S�ɏd���̂�������悤�ɂȂ����B�A���o���Ƀ����������������u������v�Ƃ���Ȃ�A���̓��́u�o���v�Ƃ������Ƃ��B�������U��Ԃ��Ă݂�ƁA���̓�����Əo�����A��̃h�A�ł����Ȃ��B���̊Ԃɖ����̎v���o������͂��Ȃ̂ɁA���ꂪ�Ȃ��B�l���Ƃ��������ɓ����Ă݂���A���������̂܂o���������B����Ȋ����ŎO�\��N���߂��Ă��܂����B �@�u�ǂ����Ă��Ȃ��͋���֗����́H�v�Ə��[���������B�u�c�����ɑ���ӔC�̂悤�Ȃ��̂��v�Ǝ��B���̃������������Ƃ��A�S�̂ǂ����ŁA�u��Z�Z��N�܂Ŏ��͐����Ă��邾�낤���v�Ǝv�����̂��o���Ă���B���A���̎��������Ă���B�����Ă����B���̗���́A���ɔ������A�����Ď��ɕ��߂����B �@�t�����X�̎��l�A�W�����E�_���W�[�́A���Ă����̂����B�u���l������āA�܂�����c�v�ƁB�����I�ɂ����o���Ă��Ȃ����A������߂͂����������B�u�����Ď��́A���Ȃ��́A�ނ́A�ޏ��́A�����Ĕނ�̐l���������B�������������Ƃ��Ȃ��������̂悤�Ɂc�v�ƁB�����������悤�ŁA���ǂ́A���͉����ł��Ȃ������B���̗���͕��̂悤�Ȃ��̂��B�ǂ�����Ƃ��Ȃ������Ă��āA�܂��ǂ����ւƋ����Ă����B���ނ��Ƃ��ł��Ȃ��B�������Ǝv���Ă��A���̂܂w�̊Ԃ���R��Ă����B �@���ꌎ������A������݂���܂���̌������J���~���Ă����B�������͌��Z���̒ʂ�ɂ��钃���Œ��H���Ƃ�A�����Ĉꎞ�����O�ɂ������o���B���A�������o��ƁA�J�����ł����B��������ΐ��܂ł́A�����Đ������Ȃ��B�����āA�������͐ΐ��̉��ɗ������B�u���A�������v�ƕ����ƁA���[�����v�����Ȃ���u�ꎞ��c�v�ƁB���͂�����x�ΐ��̉��ő����ӂ���Ă݂��B�u�����ɗ����Ă���v�Ƃ����������ق��������B�w������A�l�N�Ԓʂ蔲�����ΐ�傾�B �@�ƁA���̂Ƃ��A���̒��قǂ����l�̒j�����Ȃ������Ă���̂ɋC�������B�����ɂ����납�琺��������j�������B����ɂ�����l�c�I�@���̂Ƃ���A���̖ڂ���A�Ƃ߂ǂ��Ȃ��܂����ӂ�o�����B  |
|
||
���������T (Buddah's Teaching) �����`������s�́u�������T�v�����E�̏��Ƃ���悤�ɂȂ��āA���낻��P�N�ɂȂ�B ���̖{�́A�ǂ��̗��ق�z�e���ɂ��u���Ă���B�����ł��̖{�̂��Ƃ�m�����B ��x�A����z�e���̃}�l�[�W���[�ɔ����Ă���Ȃ����Ɨ����Ƃ����邪�A�f��ꂽ�B �����ŋ���̂ق��֒��ڒ������āA�����B�����͌㕥���ł悢�Ƃ������Ƃ������B ���e�ɂ��ẮA���̂a�k�n�f��}�K�W���̂ق��ł��A���т��сA ���p�����Ă�����Ă���B �܂��u�����i����˂�j�v�ɂ��āc�c�B ���Ɖ��̂��Ƃ��A�u�����v�Ƃ����B ���Ƃ́A���ʂ������钼�ړI�����B���Ƃ́A�����������O�I�����ł���B ��������̂́A�����ɂ���Đ��ł���̂ŁA���̂��Ƃ��u���������v�ȂǂƂ����B ���̓��������Ȃ��Ɏ���邱�Ƃ��A�����ɓ����ȏ����Ƃ����B ���Ԃł͓]�p���āA�����Ӗ��ɗp�����邱�Ƃ����邪�A�{���̈Ӗ�����E�������̂� ���邩��A���ӂ�v����B �Ȃ����N�Ƃ����������A���l�ł���B�i�����A�o�R�P�W�j �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �������T�A���킭�A �w���̐l�Ԑ��E�͋ꂵ�݂ɖ����Ă���B �����ꂵ�݂ł���A�V�����A�a���A�����A�݂ȋꂵ�݂ł���B ���݂̂�����̂Ɖ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��A ��������̂ƕʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��A �܂����߂ē����Ȃ����Ƃ��ꂵ�݂ł���B �܂��ƂɎ����i���イ���Ⴍ�j�𗣂�Ȃ��l���́A���ׂċꂵ�݂ł���B ������ꂵ�݂̐^���A�u����i�������j�v�Ƃ����x�i�o�S�Q�j ���������ꂵ�݂��N���錴���Ƃ��āA�����́A�u�W���i���������j�v��������B �܂�́A�l�Ԃ̗~�]�̂��ƁB���̗~�]���A���܂��܂Ɏp��ς��āA�ꂵ�݂̌����ƂȂ�B �ł́A�ǂ����邩�B ���̋ꂵ�݂�łڂ����߂ɁA�����ł́A�W�̐���������������B ������u�������v�������B �����A���v�ҁA����A���ƁA�����A�����i�A���O�A����̂W�������āA�������Ƃ����B �i�P�j�����@�c�c���������� �i�Q�j���v�ҁc�c�������v�� �i�R�j����@�c�c���������t �i�S�j���Ɓ@�c�c�������s�� �i�T�j�����@�c�c���������� �i�U�j�����i�c�c�������w�� �i�V�j���O�@�c�c�������L�� �i�W�j����@�c�c�������S�̓���i�����j�������B �������T�ɂ́A��������B �w�����̐^����l�͂�������Ɛg�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �Ƃ����̂́A���̐��͋ꂵ�݂ɖ����Ă��āA���̋ꂵ�݂��瓦��悤�Ƃ�����̂́A ����ł��ϔY��f����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B �ϔY�Ƌꂵ�݂̂Ȃ��Ȃ������n�́A���Ƃ�ɂ���Ă̂݁A���B������B ���Ƃ�͂��̂W�̐��������ɂ���Ă̂݁A�B��������i�����A�o�S�R�j�B �ȑO�A�u��v�ɂ��ď��������Ƃ�����B �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �����ׂāu��v �@��敧���Ƃ����A�u��i�����j�v�B���̋�̎v�z���A��敧���̍������Ȃ��Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�܂�A���̐��̂��ׂĂ̂��̂́A���z�ɂ����Ȃ��A���̂̂�����̂́A�����Ȃ��A�ƁB �@���̘b�́A�ǂ����A�f��A�w�}�g���b�N�X�x�̐��E�Ǝ��Ă���B���邢�́A�R���s���[�^�̒��̐��E��������Ȃ��B �@���Ƃ����A�ڂ̑O�ɁA�R���s���[�^�̉�ʂ�����B��������������Ă���̂́A���̖ځB���̃L�[�{�[�h�ɐG��Ă���̂́A���̎�̎w�A�Ƃ������ƂɂȂ�B�����Ă��̉�ʂɂ́A�����̌��̐M�����W������Ă��邾���B �@�������͂�������āA�������A�Ƃ��ɓ{����o�����肷��B �@�������ڂ�������Ă��鎋�o�I�h�����A�w�ŐG���G�o�I�h�����A���ׂĐ_�o����݂��āA�]�ɓ`����ꂽ�M���ɂ����Ȃ��B�u����v�Ǝv������A�����ɂ��邾���i�H�j�B �@���������u��v�̎v�z�����������̂́A���́A�߉ނł͂Ȃ��B�߉ޖŌ�A���S�N����o�āA�I����Q�O�O�N����A�����i��イ����j�Ƃ����l�ɂ���āA�������ꂽ�ƌ����Ă���B�߉ނ̐��a�N�ɂ��ẮA���������邪�A���{�ł́A�I���O�S�U�R�N����Ƃ���Ă���B �@�Ƃ������Ƃ́A�����������݁A�u��敧���v�ƌĂ�ł���Ƃ���̂��̂́A�߉ޖŌ�A�U�O�O�N�ȏ�������Ă���A���̌`���ł����Ƃ������ƂɂȂ�B���̂���A�ʎ�o��@�،o�Ȃǂ́A���o�T���A�ł��������Ă���B �@�����������̒m�b�����܂ł��Ȃ��A�������̂Ƃ���A���ׂĂ̂��̂́A��ł͂Ȃ����Ǝv���n�߂Ă���B���Ƃ������݂ɂ��Ă��A���̂�����Ǝv���Ă��邾���ŁA���́A�Ђ���Ƃ�����A�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�ƁB �@���Ƃ��A�������ƌċz�ɍ��킹�ď㉺���邱�̑̂ɂ��Ă��A�Ƃ��ǂ��A�ǂ����Ă��ꂪ���Ȃ̂��Ǝv���Ă��܂��B �@�����悤�ɁA�ӎ��ɂ��Ă��A�����A���Ƃ������A���łȂ����̂ɂ���āA��������Ă���B�����ł��A�����������ӎ����A���ߎ��i�܂Ȃ����j�A����ɂ��̉��[���ɂ�����̂��A�����ߎ��i����₵���j�ƌĂ�ł���B�S���w�ł����A���ӎ��A�������͐[�w�S���ƁA�����ɍl���Ă悢�̂ł́i�H�j�B �@�����l���Ă����ƁA���̂ɂ���A���_�ɂ���A�u���v�ł��镔���Ƃ����̂́A�ق�̌���ꂽ�����ł����Ȃ����Ƃ��킩��B������u���͎����v�Ɛ����ɋ���ł݂Ă��A���ꂩ�ɁA�u�{���ɂ������H�v�ƕ����ꂽ��A�u���v���̂��̂��A���ڂ�ł��܂��B �@����ɁA���O�̎����A����̎������v�����Ƃ悢�B���O�̎����́A�ǂ��ɂ����̂��B���N�̉��{�̉ߋ��̊ԁA���́A�ǂ��ɂ����̂��B�����Ă����������˂A���͊D�ƂȂ��āA���̑�n�ɏ�����B�ƁA�����ɁA���̉F������Ƃ��A���ׂĂ̂��̂��A���ƂƂ��ɏ�����B �@����Ȃ킯�ŁA�u���ׂĂ���v�ƌ����Ă��A���̎��́A���Ȃ��ɁA�u�������낤�ȁv�Ǝv���Ă��܂��B�����A������Ȃ��łق����̂́A������Ƃ����āA���ׂĂ̂��̂����Ӗ��ł���Ƃ��A���i�ނȁj�����Ƃ������Ă���̂ł͂Ȃ��B�������������̂́A���̋t�B �@�������́i���j�́A���܂�ɂ��A���Ӗ��ŁA���������̂ɓł���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƁB���ł����āA���łȂ����̂ɁA�U��܂킳��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƁB�����������̂ɐU��܂킳���ΐU��܂킳���قǁA�������́A�����̎��Ԃ��A���ʂɂ��邱�ƂɂȂ�B ���������݂��� �@�����ŕ����ł́A�C�s���d��B���̕��@�Ƃ��āA���Ƃ��A�������i�͂����傤�ǂ��j������B����ɂ��ẮA���łɉ��x�������Ă����̂ŁA�����ł͏ȗ�����B�����A���v�ҁA����A���ƁA�����A�����i�A���O�A����̂W�������āA�������Ƃ����B �@���A����ł͑���Ȃ��Ƃ��Đ��܂ꂽ�̂��A�Z�g�����Ƃ������ƂɂȂ�B�Z�g�����ł́A�z�{�A�����A�E�J�A���i�A�P��A�m�b���A�U�̓��ڂƈʒu�Â���B �@���������A�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���Ȓb�B�̂��߂̏C�s�@�ł���̂ɑ��āA�Z�g�����́A�u�z�{�v�Ƃ������ڂ����邱�Ƃ�����킩��悤�ɁA��藘���I�ł���B �@���������́A�������Ă��̂��Ƃ��A����I�ɕ��ނ��čl����̂́A���܂�D���ł͂Ȃ��B�������������ŁA���ׂĂ����������Ƃ͎v��Ȃ����A�t�ɁA����ȊO�́A���̂̍l�������ے肳��Ă��܂��Ƃ����댯��������B�u�܂��A���������l����������̂��ȁv�Ƃ������x�ŁA�悢�̂ł͂Ȃ����B �@�ŁA�����ł́A�u�C�s�v�Ƃ������t���悭�g���B�ŁA���̏C�s�ɂ́A���낢�날��炵���B���ɂ́A�킴�Ƒ̂�S��ɂ߂��Ă�����̂�����Ƃ����B�Ӂi�Ȃ܁j�����̂ɂ́A���������C�s���K�v��������Ȃ��B�������A���́A���߂�B �@��Ȃ��Ƃ́A�����ӂ��̐l�ԂƂ��āA�����ӂ��̐��������A���̐�����ʂ��āA���̒��ŁA�������݂����Ă������Ƃł͂Ȃ����B�Y��A�ꂵ�肵�Ȃ��炵�āA�������݂����Ă������Ƃł͂Ȃ����B����Ă�����C�s����������Ƃ����āA���̐l�̐l�i����簁i�����܂��j�ɂȂ�Ƃ��A�����������Ƃ͂��肦�Ȃ��B �@���̈��Ƃ����킯�ł��Ȃ����A�悢�Ⴊ�A�J���g���c�̐M�҂����ł���B�M�҂ɂȂ����Ƃ���A�ǂ��������ꂵ���悤�ȏ݂��ׂāA���������́A�����ꂽ�l���ł��Ƃ����悤�ȕ��͋C��Y�킹��B�u���O�����A�}�l�Ƃ́A�������̂��v�ƁB �@�����玄�����́A�����Ǝ��R�ɍl����悢�B��������A�Z�g�������Q�l�ɂ��Ȃ���A�������́A�������ŁA����ȏ�̂��̂��A�l����悢�B�����������t�̗V�сi����I�j�ɁA�������K�v�͂Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A���́A������������ł͂Ȃ��B �@�������́A�����ɍl���Ȃ��琶����B���ꂪ�������Ƃ��A�܂������Ă���Ƃ��A����Ȃ��Ƃ��l����K�v�͂Ȃ��B���̌��ʂƂ��āA���s�����邾�낤�B�w�}�����邾�낤�B�܂����������Ƃ����邩������Ȃ��B �@���������ꂪ�l�Ԃł͂Ȃ����B�s���S�Ŗ��n��������Ȃ����A�����̑��ŗ��Ƃ���ɁA�u���v������B�����̃h���}���������琶�܂�邵�A���̃h���}�ɂ����A�l�Ԃ��l�ԂƂ��āA������Ӗ�������B �@���́A���̒��x�̂��Ƃ����킩��Ȃ��B���̂Â��́A�������������₵�Ă���A�l���Ă݂����B �i�O�T�O�X�Q�T�L�j �i�͂₵�_�i�@�������@�Z�g�����@�����@��敧���@���ߎ��@�����ߎ��j �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �������̒��ł��A���́A�����i�������A �����Ƃ��d�v���Ǝv���B �Ƃ��ɁA���̎��̂悤�ɁA���N�ŁA����� �s���R�̂Ȃ����������Ă�����̂ɂƂ��ẮA �����ł���B �������č��̏��A�ӑĂɉ߂����Ă͂����Ȃ��B ���Ԃɂ͂����肪����A�l���ɂ��A����䂦�� ���E������B ���ꂱ������鍐����Ă���A�������߂Ă��A �x���Ƃ������ƁB ���Ƃ��Δx�K����鍐����Ă���A�^�o�R����߂���A �݃K����鍐����Ă���A��������߂Ă��A�x���B ���N�ł���Ȃ�A����ɍ��̐������������肽���̂ł���Ȃ�A �Ȃ�����A�������́A���i�ɐ��i���d�˂�B ��u�A��b����Ƃ��A���ʂɂł��鎞�Ԃ͂Ȃ��B �܂����ʂɂ��Ă͂����Ȃ��B �����i�ɂ��ď��������e������B �ꕔ���e���_�u�邪�A�����Ăق����B �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �������i �@�߉ނ̋������A�����Ƃ��킩��₷���܂Ƃ߂��̂��A�u�������i�͂����傤�ǂ��j�v�Ƃ������ƂɂȂ�B���̓��Ɏ���A�C�s�̊�{�ƍl����ƁA�킩��₷���B �@���A�����ł����u���v�́A�u�������v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�߉ނ��������u���v�́A�u�����v�́u���v�ł���B�܂蔪�����Ƃ����̂́A�u���̒����Ȃ�C�s�̓��v�Ƃ����Ӗ��ł���B �@�ӑĂȏC�s�������Ȃ����A����ƂāA���`�����`���ɂ��т����C�s���A�����Ȃ��B�u�قǂقǁv���A�����Ƃɂ����Ă��A�D�܂����Ƃ������ƂɂȂ�B���A�������A����������Ƃ����Ӗ��ł��Ȃ��B �@�ŁA���̔������Ƃ́A�i�P�j�����A�i�Q�j���v�ҁA�i�R�j����A�i�S�j���ƁA�i�T�j�����A�i�U�j���O�A�i�V�j�����i�i�W�j����A�������B�L�����ɂ́A�u���Ȃ킿�A�����������A���ӁA���t�A�s�ׁA�����A�w�́A�v�O�A�ґz�v�Ƃ���B �@���̂����A���́A�Ƃ��Ɂi�W�j�̐����i���A���ɍl����B�߉ނ����������i�Ƃ����̂́A���X�̐₦�܂Ȃ��w�͂ƁA�^���ւ̒T���S�������B�����ɂ́A�����A�ǂ��߂�ꂽ�悤�ȋٔ������Ƃ��Ȃ��B���̋ٔ������ɂ���B �@�S�[���́A�Ȃ��B���ʂ܂ŁA�w�͂ɓw�͂��d�˂�B���ꂪ���i�ł���B�ŁA���̐��i�ɂ��Ă��A��͂�A�u�قǂقǂ̐��i�v���A�D�܂����Ƃ������ƂɂȂ�B���Ȃ��Ƃ��A�߉ނ́A���������Ă���B �@���@�Ƃ��ẮA�����V�������Ƃɋ����������A�T���S��Y��Ȃ��B�w�͂���B�����B���A���̂ǁA���y������A�G���������A�{��ǂ肷��B���A�������d�v�Ȃ̂́A�����̓��ŁA�����ōl���邱�ƁB�u�l����v�Ƃ����s�ׂ����Ȃ��ƁA�����������������A���̂������o�P�c���琅�����ڂ��悤�ɁA�ǂ����ւ��ڂ�Ă��܂��B �@���������x�������Ă������A�l����Ƃ����s�ׂɂ́A�����̋�ɂ��Ƃ��Ȃ��B�������ɁA�W���M���O�ɍs���O�Ɋ�����悤�ȋ�ɂł���B�����炽���Ă��̐l�́A���ӎ��̂����ɂ��A�l����Ƃ����s�ׂ�����悤�Ƃ���B �@���̂��Ƃ́A�q�ǂ�����������Ƃ킩��B�����̐��w�p�Y�����o���Ă�����Ƃ��A�u���I�v�u��肽���I�v�ƐH�����Ă���q�ǂ�������A�������ɂȂ�q�ǂ�������B���ɂ́A�ƂȂ�̎q�ǂ��̓�����������ƁA��������q�ǂ�������B �@�q�ǂ�������A�l����̂��D���ƌ��߂Ă�����̂́A����ł���B�����Ă₪�āA���̍l����Ƃ����s�ׂ́A���̐l�̏K���ƂȂ��āA�蒅����B �@�l���邱�Ƃ��D���Ȑl�́A���ꂾ���ŁA������ӎ����Ȃ��Ă��A�߉ނ��������i���A�����̒��ł��Ă��邱�ƂɂȂ�B�����łȂ��l�́A�����łȂ��B�����Ă��������K���̂��������A�P�O�N�A�Q�O�N�A����ɂ͂R�O�N�ƁA�ς���ɐς����āA�傫�ȍ��ƂȂ��Č����B �@�����A�����ő傫�Ȗ��ɂԂ���B�����Ȑl����́A�o�J�Ȑl���킩��B�����l����́A�����Ȑl���킩��B�l����l����́A�l���Ȃ��l���킩��B�������o�J�Ȑl����́A�����Ȑl���킩��Ȃ��B�����Ȑl����́A�����l���킩��Ȃ��B�l���Ȃ��l����́A�l����l���킩��Ȃ��B �@�����ɏZ�ޖ쉎�ɂ��Ă��A�쉎�����́A���������́A�l�Ԃ��A����Ă���Ƃ͎v���Ă��Ȃ����낤�B�Ђ���Ƃ�����A�l�Ԃ̂ق����A�o�J���Ǝv���Ă��邩������Ȃ��B�G�T���悱���ƁA�L�[�L�[�Ɛl�Ԃ��Њd���Ă���p������ƁA����������B �@�܂肱���ł����u���v�Ƃ����̂́A�����܂ł��A�����Ȑl�A�����l�A�l����l���A�S�̒��Ŋ����鍷�̂��Ƃ������B �@���āA�����Ŏ߉ނ́A�u�����v�Ƃ������t���g�����B���͂Ƃ�����A���́A���̌��t���A�J���g���c�ŁA�M�҂̊l���ɋ��z���Ă���M�҂̕��ɁA�킩���Ă��炢�����B�ނ�́A�u���������͐�ΐ������v�Ƃ����M�O�̂��ƁA���̕Ԃ����ŁA�u���Ȃ��͂܂������Ă���v�ƁA�������Ď̂Ă�B �@���������}�i���A���������A���M���́A���������߉ނ������u�����v�Ƃ́A�َ��̂��̂ł���B�Ƃ��Ɍ�����`�ɂ������A�R�`�R�`�̓��ɂȂ��Ă���l�قǁA���ӂ�����悢�B �i�͂₵�_�i�@�������@���i�@�����i�j �y�⑫�z �@�q�ǂ��̋���ɂ��Č����A�����ɂ���A�l���邱�Ƃ��D���Ȏq�ǂ��ɂ��邩���A��̏d�v�ȃ|�C���g�Ƃ������ƂɂȂ�B�v����Ɂu�l���邱�Ƃ��y���ގq�ǂ��v�ɂ���悢�B �i�͂₵�_�i�@�ƒ닳��@�玙�@�玙�]�_�@����]�_�@�c������@�q��ā@�͂₵�_�i�@Hiroshi Hayashi education essayist writer Japanese essayist �����A���v�ҁA����A���ƁA�����A�����i�A���O�A����̂W�������āA�������@�������T�@�͂₵�_�i�j Hiroshi Hayashi�{�{�{�{�{�{�{�{�l�`�q�D�O�W�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�͂₵�_�i�� �y���E�V�E�a�E���z �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �����Ă����̂������ւ�B �V���Ă����̂��A����܂������ւ�B �a�C�͂��킢�B ���ʂ̂́A����ɂ��킢�B �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ ���������邱�Ƃ̔��� �������邱�Ƃ̔����B �ŋ߁A���̂��炵�����A�悭�킩��悤�ɂȂ����B ���̂����A�Ƃ��ɁA���K�ʂɂ����ẮA�����肵�Ă����B �����A���Ă���B �����Ŏ��s�����Ƃ��A�����������Ƃł͂Ȃ��B ����A���K�ʂœ��������Ƃ����b�́A�Ȃ��B ������x�����A���C�t�̎������Ȃ��Ȃ����Ƃ��A �����ŁA�P�O���~�̈�Y�����������Ƃ�����B ���Ƃɂ���ɂ��A���������`�ŁA�u���H�v�������̂́A���ꂾ���B �������������́A���̂P�O���~�ŁA������B �`���̎v���o�Ƃ������ƂŁA���������B �����Ȃ��Ă���ƁA�킸���ȑ����ȂǁA�ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă��܂��B ����ɂȂ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B �ǂ��ł��悭�Ȃ��Ă��܂��B ���̂����A�i���ԁj�Ƃ������i���j�̑�����A�悭�킩��悤�ɂȂ����B �ǂ������˂A���̐�����Ƃ��A���ׂĂ̂��̂��A���̖ڂ̑O���������B ���������A�q�ǂ��̂���A����Ȃ��Ƃ��������B ���̂Ƃ����������́A�o���Ă��Ȃ����A���Ԃ�A�������w�T�A�U�N���� ����̂��Ƃł͂Ȃ��������B ���͖��̒��ŁA�������ق����������̂���ɓ��ꂽ�B ���ꂪ���������̂��͖Y�ꂽ���A�ق����������̂���ɓ��ꂽ�B ���A���̂Ƃ������ɁA�ǂ������킯���A���ꂪ�����ƁA�킩�����B �u����͖����v�u����͂킩���Ă��邪�A���������ꂪ�ق����v�ƁB �����Ŏ��́A���́i���́j���A��������Ǝ�ň������B ���̒��ŁA�������B�ڂ����܂��Ă�����A������Ȃ����߂ɁA�ł���B ���A�ڂ����߂Ă݂�ƁA���́i���́j�͏����Ă����B�i���R�ł���I�j �����̎���������A���́i���́j�͂Ȃ������B ���̐��E�̂��̂��A���ׂāA����Ɠ����ƍl���Ă悢�B �u���̐�������v�ƐM���Ă���l�����邩������Ȃ����A��������A �Ȃ�����A�����ł���B �����ɂ���i���m�j�ɂ��Ă��A���ƕ��q���D��Ȃ����o�ł����Ȃ��B ��Ȃ̂́A����������A���A���Ă���Ƃ����i���ԁj�B �����Ă��́i�����j�B ���́i���ԁj�́A���ꍏ�Ƃ����Ă����B ���̑���ɁA�a�C�ɂȂ��Ă���C�Â��Ă��A�x���B �V���Ă���C�Â��Ă��A�x���B �������Ȃ������A�Ⴍ�Č��N�Ȃ�A������A����ɋC�Â��B �����č��Ƃ������́i���_�j����A���̂�����A������R�₷�B �R�₵�ĔR�₵�����B ���A����ł��A�i�^���j�ɋ߂Â����Ƃ͂ނ��������B �s�\��������Ȃ��B ���������̑O�����Ȏp�������A��B �����ɐ�����Ӗ�������B���l������B �ŁA�u�V�v������Ă�����A�ǂ����邩�H �������̓�����ɗ������킯�����A�������̂Ƃ����N�ł���Ȃ�A �V�ȂǁA�C�ɂ��Ȃ��Ă��悢�B �N��Ƃ����̂́A�����́i�����j�ɂ����Ȃ��B �i�a�C�j�ɂ��ẮA�ǂ����H ���ꂪ�ꎞ�I�Ȃ��̂ł���A�����悢�B �S�̕a�C���A�����B �����a�C�Ƃ����̂́A�����܂ł��i�ߋ��j�̌��ʂƂ��Ă���Ă�����́B �������A���Ȃ������N�Ȃ�A�u���N�Ƃ͍����̂ł͂Ȃ��A�����́v�� �l���āA�^�����ɂ�����悢�B �^��������K�����ɂ�����悢�B �ӑĂȐ������J�肩�����Ă��āA�ǂ����Č��N���ێ��ł���Ƃ����̂��B �P�O�N��A�Q�O�N��������O���ɒu���Ȃ���A�^�����ɂ���B �������^�o�R�͋z��Ȃ��B���͈��܂Ȃ��B ����������ƁA���������^���������A�i���A�������J�肩�����Ă���Ȃ�A �a�C�ɂȂ��Ă��A����ĂȂ����ƁB���ꂱ���g����Ƃ������́B ���Ƃ́A���̓�������܂ŁA�����A���ӂ��Đ�����B ���ӂ��Ȃ���A���̐S���A�Љ�ɊҌ����Ă����B �u���v������Ă�����A���̂Ƃ��́A���̂Ƃ��B ���������Ȃ��B �@��o�̒��ɂ�����Ȉ�߂�����B ������߉ނ̂Ƃ���ֈ�l�̒j������Ă��āA���������˂�B �u�߉ނ�A���͂����������ʁB���ʂ̂����킢�B �ǂ�������̎��̋��|���瓦��邱�Ƃ��ł��邩�v�ƁB ����ɓ����Ď߉ނ́A���������B �u�����̂Ȃ����Ƃ�Q���ȁB�����܂Ő����Ă������Ƃ���ׁA���ӂ���v�ƁB ������x�A�]��ᇂ��^���āA�����o�債�����Ƃ�����B ���̂Ƃ����́A���̎߉ނ̌��t�ŋ~��ꂽ�B ���ꂩ�炷�łɂR�O�N�ɂȂ邪�A���ꂩ��̂R�O�N�Ԃ́A�܂��Ɂi���炢���́j�B ���́i���炢���́j�Ɣ�ׂ���A���K�I�ȁi���j�ȂǁA���ł��Ȃ��B �ނ��둹�����邱�Ƃɂ���āA�i�����j����A��������������邱�Ƃ��ł���B ���̉���������܂�Ȃ��B �`���ŁA�u�������邱�Ƃ̔����v�Ə������̂͂��������Ӗ������A �������邱�Ƃ�����Ȃ����ƁB �����Ď������瑹������K�v�͂Ȃ����A���ׂ����Ƃ͂���B ���̌��ʂƂ��āA��������Ȃ�A�������邱�Ƃ�����Ȃ����ƁB �ނ��딽�ɁA���Ԃʂɂ��Ă���l�����邽�тɁA���́A�����v���B �u�����A���������Ȃ����Ƃ����Ă���I�v�ƁB ���̐l���Ⴍ�āA���N�Ȃ�A�Ȃ�����ł���B ���ꂼ��̐l�́A�i���ׂ����Ɓj�������Ă���B ����͐l�ɂ���āA�݂Ȃ������B �S���w�̐��E�ł́A�^�E�P�E���̒Nj����A����ł���Ƌ�����B ���A����ɂ������K�v�͂Ȃ��B�����A��������Ă��Ȃ��B ���łɁu��]�_�v�ɂ��āB �l�͉����Ȃ��Ă��A��]��������ΐ����Ă������Ƃ��ł���B ���������́u��]�v�Ƃ͉����B �����̒��ɁA����Ȑ��b���c���Ă���B �m�A���A�u�ǂ����Đl�Ԃ̂悤�ȁi�s���S�ȁj���������������̂��B �i�^���Ŗłڂ����炢�Ȃ�A�ŏ�����A���S�Ȑ������ɂ���悩�����͂����j�v�ƁA �_�ɕ������Ƃ��̂��ƁB �_�͂��������Ă���B�u��]��^���邽�߁v�ƁB �����l�Ԃ����ׂēV�g�̂悤�ɂȂ��Ă��܂�����A�l�Ԃ͂��悢�l�ԂɂȂ�Ƃ��� ��]���Ȃ����Ă��܂��B �܂�l�Ԃ͈������Ƃ����邪�A�w�͂ɂ���Ă悢�l�Ԃɂ��Ȃ��B �_�̂悤�Ȑl�ԂɂȂ邱�Ƃ��ł���B �����̒��̐_�́A�u���ꂪ��]���v�ƁB �i�͂₵�_�i�@�ƒ닳��@�玙�@�玙�]�_�@����]�_�@�c������@�q��ā@�͂₵�_�i�@ Hiroshi Hayashi education essayist writer Japanese essayist ���E�V�E�a�E���@�l��_�@�� �_�@��]�_�j |
|
||
| ���s��p�Ȑ����� �@�s��p�Ƃ����Ă��A���̕s��p���̂��Ƃł͂Ȃ��B�������̕s��p�����A�����B �@���n��̂��܂��l������B���A���̈���ŁA���n��̃w�^�Ȑl������B�����ŁA�E�\�����Ȃ��B�����w�^�B���������l���A�s��p�Ȑl�Ƃ����B �@�Z�ʐ��ɂ�����B�Ջ@���ςɑΏ��ł��Ȃ��B�����������B���B�N�\�܂��߁B���������ŁA�d�ׂ�w��������ł��܂��B�������邱�Ƃ́A�����Ă��A�������邱�Ƃ͂Ȃ��B�f��́w��т��߂��݂����N���x�̒��́A���c�[����A�L��l�Y�ɁA���̃C���[�W�����v�������ׂ�B���炵���f�悾�����B���ł��A���̉̂��������ނƁA�ړ����W���ƔM���Ȃ�B �@�ēA����A�r�{�́A�؉��b��B���y�́A�؉����i�B �@�Ō�̃V�[���ŁA�����̗L��ƁA���v�w�����D�D���A�������ɋD�J�����킵�����Ƃ��낪����B�����ł́A�ϋq�́A�݂ȁA�l�ڂ��͂��炸�A�܂𗬂����B �@�c�c�ƁA�l���Ă����ƁA�s��p�ł��邱�Ƃ́A����A�p���ׂ����Ƃł͂Ȃ��B�ނ���A�����l����U�肩�����Ă݂��Ƃ��A�s��p�������l�̂ق����A�S�ɂʂ������^���Ă����B���������l�قǁA�l�������ł��邩���A�����Ă����B �@���A����Љ�ł́A�s��p�Ȑl�قǁA�����ɂ����B�Љ����c����邾���ł͂Ȃ��A�Љ�̃X�~�ɁA�ǂ�����Ă��܂��B���̈���ŁA���n��̂��܂��l�قǁA�����҂Ƃ��āA���Ă͂₳���B �@�l������ڂƂ������A���l�ς��̂��̂��A�Y���Ă��܂����B���ɂ́A����Ȋ���������B�����ŏd�v�Ȃ��Ƃ́A�������P�l�ЂƂ肪�A���̃Y�������̂̍l�������A�������A�O���C�����Ă������ƁB�݂Ȃ��A�������A���������A�₪�Ă��ꂪ�傫�ȗ͂ƂȂ�B �@�������A����͉\�Ȃ̂��H �@������s���Ȃ̂́A���̖؉��b����A�ӔN�ɂȂ�Ȃ�قǁA���͂ւ̎u�����������Ȃ����Ƃ������A�ǂ����A���������Ȃ����Ă������悤�Ɏv���B����͂����܂ł��A���̈�ۂȂ̂ŁA�٘_�̂�����������Ǝv���B�������ӔN�̍�i�ɂ́A�w��т��߂��݂����N���x�Ɍ���ꂽ�悤�ȁA���̓����Ƃ���悤�ȏ������́A�����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B �@�c�c�Ƃ������Ƃ��A���C�t�ɘb���ƁA���C�t�́A�����������B�u���̊ḗA���Ƃ��ƁA��p�Ȑl�������Ƃ������Ƃ�v�ƁB�܂�u�ēɂȂ�悤�Ȑl������A�s��p�Ȑl�ł́A�ēɂ͂Ȃ�Ȃ��v�ƁB�i���z�h�I �@�b�͂��ꂽ���A�������w��т��߂��݂����N���x�́A���쒆�̖���ł��邱�Ƃ́A����̖ڂɂ��^���悤���Ȃ��B�������̉f��������̂́A�q�ǂ��̂Ƃ��������B����Ȏ��ł���A�v�w�Ƃ����̂́A�����������̂��Ƃ������Ƃ��A������ꂽ�B �@���̌��_�Ō���P���Ă���̂��A��͂�A�L��l�Y�̕s��p���A�ł���B���q�̗ՏI�̍ۂɂ��A�L��l�Y�́A�����������B���e�Ƃ��āA�ǂ�����ׂ����������Ƃ������Ƃɂ��ẮA�c�_�����邾�낤�B���A�L��l�Y�ɂ��Ă݂�A��������o���āA�a�@�ւ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B �@���������s��p���́A���̎��ɂ́A�ɂ��قǁA�悭�����ł���B���������A�L��l�Y�̗��ꂾ������A�����A�����悤�ɂ������낤�B �@��p�ɐ�����c�c�B���̓T�^�I�ȗႪ�A���𑛂����Ă���A���t�H�[�����\�ł���B�u���t�H�[������v�ƌ����ẮA�V�l���������܂��A���z�̃��t�H�[����𐿋�����B���������������u�r�W�l�X�v�ƌĂ�ł�����̂́A������A���Ȃ���A���̃��t�H�[�����\�̂悤�Ȃ��́B�u���̂��Ă���d���́A���t�H�[�����\�Ƃ͂������v�ƁA�����Č�����l�́A���������A���l���邾�낤���B �@�������́A�����Ă�����ŁA�����A�S�̂ǂ����ŗǐS���˂��܂��A���ӂ��]���ɂ��A���������܂����Ă���B�܂��A�����łȂ��ƁA���̌���Љ�ł́A�����Ă������Ƃ���A���ڂ��Ȃ��B �@���ꂪ���C�łł���l�̂��Ƃ��A��p�Ȑl�Ƃ����B�����łȂ��l���A�s��p�Ȑl�Ƃ����B���A�s��p�ł��邱�Ƃ������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�s��p�����A�����̂悤�Ȃ��̂ɁA�������́A���������A�h�ӂ��Ă��悢�ł͂Ȃ����낤���B���ꂪ�A���̃G�b�Z�[�̌��_�Ƃ������ƂɂȂ�B �y�t�L�z���ł��A��p�Ȏ��قǁA�X�C�X�C�ƁA�Љ��n������Ă����B���������Ȃ��B�������ł��Ȃ��B���̒��́A�Z���^�[�����̐������炯�B �@����A�s��p�Ȏ��Ƃ����̂��A����B���ɓ������Ƃ����̂ɁA�w�Z�Ղ̂��߂ɁA���ӁA�w�Z����A���Ă���̂́A�^�钆�B�ŁA����Ǝn�߂����ɂ��Ă��A�ǂ����A�g���`���J���B�v�̂��킩��Ȃ����߂ɁA��蓹���肵�Ă���B �@�u���O�Ȃ��A����ȂƂ���́A�����ɂ͏o�Ȃ���v�Ƌ����Ă��̂����A�u�搶�A������A������v�ƌ����ẮA������������Ă���B�܂�́A���̒i�K����A���ݎЉ�ł́A��p�Ȏq�ǂ��͓������A�s��p�Ȏq�ǂ��͑�������B�������������݂��A���łɂł��������Ă��܂��Ă���B �@����Ȋ���������B �i�͂₵�_�i�@�s��p�@��p�j |
|
||
�����Ȃ̓����� �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �ǂ�����A�i�����̂��ׂ����Ɓj�ƁA �i���Ă��邱�Ɓj����v�����邱�Ƃ� �ł��邩�B ���ꂪ�������̖��Ƃ������ƂɂȂ�B ���A������ꌾ�Ō����\�����l�������B �}���`���E���[�T�[�E�L���O�ł���B �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �@�}���`���E���[�T�[�E�L���O�E�i���́A�����q�ׂ��B If a man hasn't discovered something that he will die for, he isn't fit to live. �[ Martin Luther King Jr. ���ʂ��߂̉��������邱�ƂɎ��s�����l�́A������̂ɓK���Ă��Ȃ��Ƃ������ƁB�i�}�[�e�B���E���[�T�[�E�L���O�E�i���j �@�����Ŏ��₵�Ă݂�B���ɂ͍��A�������ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ����邩�A�ƁB�����āA���͍��A�������ł��Ă��邱�Ƃ����邩�A�ƁB �@�V��̖��Ƃ́A�܂��ɁA���́i�������j�̖��ƌ��������Ă��悢�B�̂�ׂ��ƁA�����A�ނ��������Ă���l���ȂǁA�Ƃ�ł��Ȃ��l���ŁA�����������l������́A�������܂�Ȃ��B�c��Ȃ��B�n�C�f�b�K�[�̌��t�����Ȃ�A���������l�́A�u�����̐l�v�B�n�C�f�b�K�[�́A�y�̂̔O�����߂āA�����������B�u�c�`�r�@�l�`�m�m�i�����̐l�j�v�ƁB�i�킩�������A�w�ނ�o�J�����x�̕l�����I�j �@�������V��̓������Ƃ����̂́A���́A�����ւ�Ȗ��ƍl���Ă悢�B���x���������A�꒩��[�Ɋm���ł���悤�ȑ㕨�i������́j�ł͂Ȃ��B���ꂱ���P�O�N�P�ʁA�Q�O�N�P�ʂ̏n�����Ԃ��K�v�ł���B���̏n�����Ԃ��o�āA�n�߂āA�����ɍ������낷�B����o���B�Ԃ��炩���邩�ǂ����́A����܂��ʖ��B �@�������ł��Ă��A�Ԃ��炩���Ȃ��܂I����l�ƂȂ�ƁA�S�}���Ƃ���B����A�����͂A�����ł͂Ȃ����H �@�u���͂����̖}�l�v�Ƌ�����O�ɁA�݂Ȃ�����A���ЁA�����Ɉ�x�A�₤�Ă݂Ăق����B�u���ɂ́A�������ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�������邩�v�ƁB �@�����܂ŏ����āA�̌����f��A�w������x���v���o�����B��7���f��R���N�[���i���{�f���܁j��܂�����i�ł���B�����f��R���N�[���̂����������A���e�����āA���̂܂܂����ɏЉ���Ă��炤�B �u�c�c�s�����̎s���ے��ł���n粊����i�u�����j�͂R�O�N�ԁA�������������A���̓��A���߂Č������B�a�@�ň݃K���Ɛf�@����A���ƂS�����̖����Ɛ鍐���ꂽ����ł���B�����͐e���v��Ȃ����q�E���j�i���q�M�Y�j�v�w�ɂ���]���A�a�������낵�ĊX�ɏo��B �@�����͉���̈��݉��Œm�荇���������Ɓi�ɓ��Y�V���j�ƈӋC�����A�����Ƃ́A�����ɍŊ��̉��y�𖡂���Ă��炨���ƃp�`���R���A�L���o���[�A�X�g���b�v�Ɠn������B�����A�����̐S�͖�������Ȃ��B���A�肵�������́A�s���ۂ̏����������c�Ƃ�i���c�݂��j�Əo��B�ޏ��͑ސE�͂��o���Ƃ��낾�����B �@�u����ȑދ��ȂƂ���ł͎���ł��܂��v�Ƃ́A�Ƃ�̌��t�ɁA�����͎��Ȃ����`�̎����̎d���ȁB�ڂ̐F��ς��Ďd�����ĊJ����B���̊����̖ڂɎ~�܂����̂��A�����̈��u�̌����ƂȂ��Ă����q���������c�c�v�ƁB �@���̉f��́A���V���ē̌���Ƃ��āA�P�X�T�R�N�A�x�������f��ՂŁA��F�܂���܂��Ă���B ���̂��Ɠn粊����́A�c���ꂽ�l�����A���̐l�̂��߂ƁA�����Ȍ������ɁA�������������߂�B�Ō�ɁA�����̃u�����R�ɏ��Ȃ���A�u�����邱�Ƃ̈Ӗ�������Ď���ł����v�i�u���ꂢ�m�����v�j�ƁB �@���ł����̉́A�u�S���h���̉́v���A���̎��ɁA���݂��݂Ǝc���Ă���B �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ ���S���h���̉́i�g��E�쎌�A���R�W����ȁj �P�@���̂��Z���@�����扳�� �@�@�邫�O�@�ʊԂ� �@�@�M�������́@�₦�ʊԂ� �@�@�����̌����́@�Ȃ����̂� �Q�@���̂��Z���@�����扳�� �@�@��������Ƃ�ā@��(��)�̏M�� �@�@�����R���j���@�N���j�� �@�@�����ɂ͒N����@���ʂ��̂� �R�@���̂��Z���@�����扳�� �@�@�����̐F�@�ʊԂ� �@�@�S�̂ق̂��@�����ʊԂ� �@�@�����͂ӂ����с@���ʂ��̂� �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �@�����A���낻��A���������N��ɂȂ����B�����܂��I |
|
||
���D�c�M���_ �@������e���r�����Ă�����A�����������m���i�l���j�������B�u���͐M���̐������ɋ������o���܂��B���̓��{�ɕK�v�Ȃ̂́A�M���^�̐����Ƃł��v�ƁB �@�M���̂��ƂŁA�����ɑ����̑P�ǂȏ������ꂵ�݁A�]���ɂȂ������Ƃ��B���s�̐쌴�ł́A�����l�Z�`�܁Z�l���̐l�����Y���ꂽ�Ƃ����L�^���c���Ă���B������Âɗ��j������A�ނ��܂Ƃ��Ȑl�ԂłȂ��������Ƃ́A����ɂ����Ă킩��͂����B �@�������͂Ƃ�����A���̎�����A�M���̖ڂł������Ȃ��B���A��x�ł��悢����A�M���ɃN�r����鏎���̗���Ō��Ă͂ǂ����낤���B���m���Ƃ����A���͂̃g�b�v�ɗ������悤�Ȑl�ɂ́A�M���͗��z��������Ȃ����A���������̓S�����B�������A�M���^�̐����Ƃ��o�Ă�����A�O��I�Ɏ��͐키�B �@���{�ȊO�̑����̍��X�ł́A�O���̐��͂ɂ���āA�����ɋꂵ�Ƃ������j������B�����������X�ŁA���������O�����͂���������悤�ȃh���}�𗬂������̂Ȃ�A���ꂾ���őܒ@���ɂ����B���̃I�[�X�g�����A�ł����A�p�����{����̃C�M���X��������邾���ŁA�ܒ@���ɂ����B �������M���₻��ɂÂ������̎傽���̂��������́A�A���n�̓����҂ł����Ȃ������悤�Ȉ����ł���B�E�\���Ǝv���Ȃ�A��x�A�V�����i�É����l���̐��ɂ��钬�j�̊֏��Ղ֍s���Ă݂邱�Ƃ��B�����͊֏��j��������Ƃ��������ŁA�ꑰ���ׂĂ����Y���ꂽ�B����ȋL�^���c���Ă���B �����͈����ł��A�M���͓��{�l���������狖�����Ƃ����_���́A���ꎩ�́A���������B�������ɐM�����A���N�̗����̏o�g�҂�������A������͂ǂ��]������Ă��邱�Ƃ��B�ق�̏��������ł��悢����A�����z�����Ă݂Ăق����B����Ƃ����Ȃ��́A����ł��M�����������邾�낤���B���������Ȃ�A���q����ɁA���{���P�����A�Ẫ`���M�X�n���i�����S���鍑�̑n�n�ҁA���̑��c�j������������悢�B�M�����A�����ƃX�P�[�����傫���B �@���j�͗��j������A����Ȃ�̕]���͑�ł���B����������ȏ�ɑ�Ȃ��Ƃ́A���̗��j���Âɕ]�����邱�Ƃł���B���̃i�|���I���́A�u���j�݂͂Ȃ����ӂ̂��Ƃɂ������A���b�ł���v�i�i�|���I���u��^�v�j�Ə����Ă���B�Ƃ��ɂ́A����������߂��ڂ���ł���B�ŁA�Ȃ��ƁA�u���j�͌J��Ԃ��v�i�c�L���f�B�f�X�u���j�v�j�Ƃ������ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B |
|
||
���P�O���R�P���i�����j �@�����́A�V���s�܂Ńh���C�u�����B�r���A�`�Z�ƁA�s�搶�̉ƂɊ��B�x�m�s�̗F�l�������Ă��ꂽ�A�T�c�}�C�����A�����������邽�߁B �@�V���s�̃V���b�s���O�Z���^�[�ŁA���ٓ����w���B����������āA�i�ӂ��܂��j������ցB�����Œ��H�B �@�悭�������ꂽ�A���ꂢ�Ȍ����������B�ቺ�ɁA�V����B�ӂƁA�c�a�쎌�A������Y��Ȃ́u��r��̌��v���������ށB �@�u��t�A���O�́A�Ԃ̉��c�c�v�ƁB �@���������̉̎��́A���삾�����Ƃ�����������B�u�����̊����ɁA�悭�����̂�����v�ƁB���N�O�ɁA������w�E�����]�_�Ƃ������B�����̎G���ŁA�����ǂ��Ƃ�����B �@����Ȃ��Ƃ����C�t�ɘb���ƁA�u�t�Ƃ����̂��A����������ˁv�ƁB�u�r��̌��v�Ƃ������炢�Ȃ�A�H�̂ق����A�ӂ��킵���A�ƁB �@�i���z�h�I �@�u��H�A���O�̉Ԃ̉��A�߂���t�i���������j�c�c�v�̂ق����A���͋C�Ƃ��ẮA�悭�����B ���C�t�u�c�a���A���삵���Ƃ����́H�v ���u����������������Ƃ������Ƃ��B���������A�w�t�A���O�̉Ԃ̉��c�c�x�Ƃ����̎��́A���{��̔��z�ł͂Ȃ��B�ǂ�����ǂ��ǂ�ł��A�����̂ɂ���������B����ł��������^�f�����܂ꂽ�̂����c�c�B�ڂ��ɂ́A�ǂ��ł��������Ƃ����ǁA�ˁv�ƁB �@�Ӗ��̂Ȃ���b���Â��B �@������������^�f�́A���̐��E�ł͂悭�N����B�ŋ߂ł��A���O��ƂƂ��Ēm����A�s��������B�s���́A���ꂪ���o����ƁA�J�����̑O�ŁA�������Ⴍ��Ȃ���A�u����̐l�ɋ����Ă��炦�܂����v�Ɗ��ł����B �@���������̂��Ƃ��A�s���́A���C�Ȋ�����āA�e���r�ɏo����A�u�������肵�Ă���B����Ȃ��Ƃ������āA���́A�ǂ����Ă����̂s�����D���ɂȂ�Ȃ��B�s���́A�ǂ��������邻���Ȗڂ������Ă���i�H�j�B �@�u�ڂ��ȂA�܂������̖��������ǁA���������ɁA���l�̕��͓��܂Ȃ���B���ꂩ���ڂ��������Ă��邱�ƂƓ������Ƃ������Ă�����A�ڂ��̂ق����A�����̈ӌ����A�����������v�ƁB �@���A�Ƃ��������A��́A���́u�r��̌��v���̂��́B���ɂ������o�������ȁA�H�̒Ⴂ�_�B�X�X�L���A�₳�����A���������ɗh��Ă����B �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �r��̌� �@�@�t����̉Ԃ̉� �@�@�߂���u���������� �@�@���̏����}�킯���ł� �@�@�̂̌����܉��| �@ �@�@�H�w�z�̑��̐F �@�@���s����̐������� �@�@�A���陙�ɏƂ肻�Ђ� �@�@�̂̌����܂��Â� �@ �@�@���r��̂�͂̌� �@�@�ւ��ʌ��������߂� �@�@�_�ɟk��͂������� �@�@���ɉ̂ӂ͂������炵 �@ �@�@�V��e�͑ւ�˂� �@�@�Č͈͂ڂ鐢�̎p �@�@������ƂĂ������Ȃ� �@�@�čr��̂�͂̌� �@�@�i�����̂܂܁j �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{ �@���炵���̎��ł��邱�Ƃɂ́A�������Ȃ��B�ڂ���Ɖ��������Ȃ���A���́A���݂��݂ƁA���̉̂��������B |
|
||
| ���j�̂x�_�ЎQ�q �@�����āA�������悤�B �@���̎��o�̋`���́A�`����ƂŁA���Y����Ă���B�h���̕ߗ����e���ŁA�ߗ����A�s�E�����Ƃ����߂ŁA�ł���B �@����������͔G��߁i���ʁj�ł���B���S�ȁA�G��߂ł���B�`���̏㊯�������l���A�߂��`���ɂȂ�����āA�����́A�����Ă��܂����B�`���̗F�l�i������F�j���A�`���̎���A����̖{�������A������ؖ������B �@����ɂ��ẮA�����ڂ����A�����Ă݂����B �@�ŁA���̋`���́A���A���̂x���_�ЂɁA�Ղ��Ă���Ƃ����B���̂��Ƃɂ��āA�o�ɁA�u�x���_�ЂɎQ�������Ƃ͂���́H�v�ƕ����ƁA�u��x���A�Ȃ��v�Ƃ̂��ƁB �@�u����́A�����ƁA������ɂ��邩��v�ƁB �@�O�S�N�P�P���B �@���{�̂j�́A�r�G���`�����s���Œ����̉��ƕ�Ɖ�k�����B ���͏���̖����_�ЎQ�q���ɂ��āu���j�F���̖�肪����A�����_�Ђ̖�肪����B��������K�ɏ������Ă������������v�ƎQ�q���~��v�������B����ɑ�����́u�i�Q�q�́j�S�Ȃ炸�����œ|�ꂽ�l�ւ̈ԗ�̋C��������ł���A�s��̐�����V���ɂ�����̂��v�Əd�˂Đ��������B �l�i�̊����x�́A���̐l�̎��Ȓ��S�����݂āA���f����B���Ȓ��S�I�ł������قǁA���̐l�̐l�i�̊����x�͒Ⴂ�Ƃ݂�B�d�p�_�ł́A���҂ւ̋����Ŕ��f����B �@���ƂƂ��Ă̐l�i�̊����x���A�����ƍl����B�����ɑ���̗���ŁA���̂��l���邱�Ƃ��ł��邩�B���̎��_�̐[���ŁA���ƂƂ��Ă̊����x���A���܂�B �@���̓��{�B��O�A�����Ɏ��ӂ̍��̐l�����ɁA����ȋ��|��^�������Ƃ������Ƃ́A������A���߂Ă����ɏ����܂ł��Ȃ��B���̈��Ƃ��āA�싞�s�E����������B �i�싞�s�E�����j �@���؎��ς̍Œ��A�P�X�R�V�N�i���a�P�Q�N�j�̂P�Q���P�Q�`�P�T���B�����̂j���t�́A�싞�U���ɑ��āA�O������W�J���Ă����B �@�O�����Ƃ����̂́A�i�E�������A�D�������A�Ă������j�Ƃ������������B �@���̌��ʁA���{�R�́A�����S�y�ŁA�����A�s�E�A���D���ق����܂܂ɂ����i�G�h�K�[�E�X�m�[�u�A�W�A�̐푈�v�j�B���́u�A�W�A�̐푈�v�ɂ��A�싞�����ŁA�S���Q�O�O�O�l�ȏ�A�܂��싞�ւ̐i���r���ŁA�R�O���l�ȏオ�A���{�R�ɎE���ꂽ�Ƃ����B �@�����A���̂قƂ�ǂ��A�u����R�̕w�l�A�q�ǂ��ł������v�i�����j�Ƃ����B �@�ǂ����A���̂����肪�A�ő���{���I�Ȏ����̂悤�ł���B����ɂ��āA�P�O�N�قǂ܂ŁA����Ȃ��Ƃ������Ă��������i�����A�R�T���炢�j�������B �@�u�搶�A�ǂ����Ē����l�́A�����܂œ��{�����������̂ł����I�@���͋����܂���B���{�R���싞�ŎE�����̂́A�R�O���l�ł͂���܂���B���������A�R���l�ł��I�v�ƁB �@�����Ŏ����A�u�R���l�ł��A���ł��傤�B�R�O�O�O�l�ł��A�R�O�O�l�ł����ł��傤�B�ǂ����Ă��̂Ƃ��A���{�R�������ɂ��āA�O������W�J�����̂ł����v�ƁB �@���ꂱ��c�_���������ƁA�Ō�ɁA���̏����́A�������B�u���́A����ł��A���{�l���I�v�u�����A����҂���߂�I�v�ƁB �@�������싞�s�E���������ł͂Ȃ��B�����S�y�͂������A����A�W�A�i�}���[�V�A�A�V���K�|�[���j�ł��A���{�R�͓����悤�Ȃ��Ƃ����Ă���B���������{�́A��x�����āA�A�W�A�̐l�����Ɍ����āA���̐푈�ӔC��F�߂����Ƃ͂Ȃ��B�i�[�i�[�ł��܂��Ă��܂����B �@�푈�ӔC�Ƃ������ƂɂȂ�A���̐ӔC�́A�V�c�܂ōs���Ă��܂��B�V�c���ō����ЂƂ��āA�܂���{�����@�̏ے��Ƃ��Ă��������{�Ƃ��ẮA����͂܂��ƂɁA�܂����B �@���A�������A���̂��Ƃ́A�t�̗���ōl���Ă݂悤�ł͂Ȃ����B �@����Ƃ��A���a�ɕ�炵�Ă������{�ɁA�ƂȂ�̌R���卑�j�����A�N�����Ă����B����ȌR���͂����A�j���ł���B �@�����Ă��̂j�����A�j���̌��t�����v���A���w�w�_�ЎQ�q�����v���A����ɏ]��Ȃ����{�l���A�e�͂Ȃ����������B�O�����Ƃ��ŁA���̐l�������A�R�O���l�߂��A�E���ꂽ�B���̂قƂ�ǂ��A�w�l��q�ǂ������ł���B �@�c�c�Ƃ������̂悤�Ȉӌ����A���݂̕����Ȋw�ȑ�b�́A�u���s�I�j�ρv�ƌ����炵���B�u���{�l���A�ǂ����ē��{�����������̂��v�ƁB �@�������ǂ���Âɍl���Ă��A���͂j�̌����Ă��邱�Ƃ̂ق����A���������Ǝv���B�킩��₷�������A�h�C�c�̃V�����[�_�[���A�q�b�g���[�̕�Q�������悤�Ȃ��Ƃ��J�肩�����Ȃ���A�u�s��̐�����V���ɂ�����̂��v�Ƃ́I�@������k�فi���ׂ�j���A�͂����āA�ʂ�̂��낤���B�i���Ȃ��Ƃ��A�؍��A�����̐l�����́A�������Ă���B�j �@���������ɂ����āA���̎o�v�w�ł���A���e���x�_�Ђ̍Ղ��Ă���i�H�j�ɂ�������炸�A��x���A�x�_�Ђ��Q�w���Ă��Ȃ��B�ނ���A�����̍߂ŁA���Y������ꂽ���Ƃ��A�����ł���I�@������u�s��̐����v�Ƃ́c�c�I�H�@�ނ���A�j�̍s�ׂ́A�����l��؍��l�̋t�ɐG��A�푈�̉Ύ�ɂ���A�Ȃ肩�˂Ȃ��B �@���{�R�ɂ��嗤�N���푈���A�m�肷��l�́A���܂��ɑ����B�u���{���A���H��S����~���Ă�����B�w�Z������{�݂�����Ă�����v�u���{�̂������ŁA������؍��͔��W�����ł͂Ȃ����v�ƁB �@�����������A����Ș_�����܂���ʂ�Ȃ�A���{��A���{�l��A�t�ɁA���̔��̂��Ƃ�����Ă��A���������Ȃ����Ƃ��B���̒����ɂ��Ă��A�T�T�O�O�N�̗��j������B�؍��ɂ��Ă��A�Q�O�O�O�N�ȏ�̗��j������B �@���������g���Ă��錾�t�́A�؍����o�R���ē��{�֓����Ă����B�����́A�܂��ɒ�����B���̊�������A�Ђ炪�Ȃ����܂�A�J�^�J�i�����܂ꂽ�B�����̗D�ʐ��Ƃ������Ƃ������Ȃ�A���{�́A������؍��ɁA���Ƃ���A���Ȃ������Ȃ��̂ł���B �@�c�c���́A���A���Ȃ�ߌ��Ȉӌ��������Ă���B�����ł��A���ꂪ�悭�킩���Ă���B �@���������ꂾ���́A�悭�o���Ă����Ƃ悢�B �@�������ꂾ���̌x���ɂ�������炸�A�j���A�x�_�Ђ��Q�q����悤�Ȃ��Ƃ�����A�����W����؊W�͂��납�A�A�W�A�̍��X������A���{�́A���X�J����H�炤���낤�Ƃ������ƁB����A���X�J���ǂ���ł́A���܂Ȃ���������Ȃ��B��ɂ��������悤�ɁA�u�푈�̉Ύ�v�ɂ���A�Ȃ肩�˂Ȃ��B�j���ɁA���{�U���̌�����^���邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��B �؍��̂m�哝�̂ł���A�����̏�ŁA�j�̂x�_�ЎQ�q�ɐG��A�u���{�l��A�����C�ɂȂ�ȁv�i�O�S�N�t�j�ƁA�j���������̂̂����Ă���B �܂�A���̖��́A���ꂭ�炢�f���P�[�g�Ȗ�肾�A�Ƃ������ƁB �@���{�̎����邱�Ƃ�����A���Ȃ��⎄���A���̐ӔC�����ƂɂȂ�B�u���ɂ͊W�Ȃ��v�ł͂��܂���Ȃ��B �@�Ō�Ɉꌾ�B�j�́A�u�S�Ȃ炸�����œ|�ꂽ�l�ւ̈ԗ�̋C�����v�Əq�ׂĂ���B��������A�Ȃ��A�u�S�Ȃ炸�����{�l�ɎE���ꂽ�l�ւ̈ԗ�̋C�����v�ƌ���Ȃ��̂��B�������ɂR�O�O���l���̓��{�l���A���̐푈�Ŏ���ł���B �@����͎��������A���������̓��{�l�́A�������R�O�O���l���̊O���l���E���Ă���B�������A���{�̊O�ŁI �@��T���A�؍��̐V���́A�Ԉ��w���ɂ��Ă̍ō��ٔ����A���{�̕����Ȋw��b�́A�u�i���ȏ�������{�ᔻ�̋L���������āj�A�悩�����v�����Ȃǂ��A�g�b�v�ŏЉ�Ă���B���A���{�ł́A�����m��l����A���Ȃ��B �@����ł��j���A�x�_�ЎQ�q���Â���Ƃ����̂Ȃ�A�ǂ����A������ɁB���́A�����m��Ȃ��I�@�m�������Ƃł͂Ȃ��I�@ �@���łɁA�����ꌾ�B�g���̂P���~����������肪����B���{�r��t�A������A���g�h�ւ̂P���~�̏��؎肪�n���ꂽ�B���ꂪ�ǂ����Ă����C���Ȃ̂����A�g���́A�u�L���ɂȂ����A�����Ȃ낤�v�i�O�S�P�P�R�O�j�Ɠ����Ă��܂����B �@�������������Ƃ����邽�тɁA���͈����S�Ƃ͉����낤�ƁA�l���Ă��܂��B�����A�푈�Ƃ��Ȃ�A��҂�������ɗ������A���������́A�C�̈�ԂɁA���̐�ꂩ�瓦���Ă��܂��B�g���́A�j���}���Ə���������Ă���ƁA����Ȋ���������B �������������Ƃ̑�̒��Ԃ��A�u���`�v���Ƃ��A�u�s��̐����v���Ƃ���������A���������B�{���ɁA���������B �i�O�S�N�P�Q���P���L�j �i��L�j �@���̋L�����A�}�K�W���ɍڂ���̂́A�N�������āA�P���R���Ƃ������ƂɂȂ�B���̂���A���{�̂j�́A�x�_�Ђ��Q�q���Ă���̂��낤���B����Ƃ��A���Ă��Ȃ��̂��낤���B �@�������c�c�B���̖��͊��́A���������A�ǂ����痈��̂��H�@�u�����A�l����̂��A����ɂȂ����v�Ƃ����v������A����B �@�����u�s��̐����v���炢�Ȃ�A�x�_�Ђ֍s���Ȃ��Ă��A�ł���͂��B���������ɂ����āA�u�s��̐����v�Ƃ́A�����H�@���ɂ́A�j���A�܂������A�����ł��Ȃ��B �i��L�j �@���{�r��t��i�����j�����玩���}���g�h�ւ̂P���~���~���������ŁA���������K���@�ᔽ�i�s�L�ځj�̍߂ɖ��ꂽ���h�����c�́u�g�r������v�i�������j�̌���v�ӔC�ҁE�s�s�퍐�i�T�T�j�̔������P�Q���R���A�����n�قł������i�O�S�N�j�B�n�c�ٔ����͋łP�O���A���s�P�\�S�N�i���Y�E�łP�O���j�������n�����B �@�`���ɍ߂��Ȃ�����A�����͓������A�㊯�B�����ĕ����ɍ߂��Ȃ�����A�����͓������A�g���B�Ƃ��ɁA��邱�Ƃ́A�悭���Ă���B |
|
||
����V��ɂ��i�����@�͂₵�_�i�j�n���̃o�X��ЁA�d�o�X�̂a�c�A�[���s�L
 �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�����́A��V��Ɍ������B
�u���v�Ƃ������B
�u��̍�v�Ƃ������B
�����o�X���s�B
�������疼�_��ʂ�A�����i�d�A���j���o�āA
����A�|�c��ցB
�����̖�́A�ێR�쉷��Ɉꔑ�B
��V��ւ́A������A�����B
�y���݁B�{���N���N�B
�u�꒼�Ƃ́u��V��ɂāv�̏�V��B
���Z�Q�N���̂���A���͎u�꒼�Ƃɖ����ɂȂ����B
�u�꒼�Ƃ̖{���A�Ђ��[����A�ǂB
���̏�V��B
�����딼���I�߂����O�̂��ƂŁA���e��
�悭�o���Ă��Ȃ��B
�u�꒼�Ƃ��ǂ����̗��ق̈ꎺ�ŏ�����
�G�b�Z�[�������B
�u�c�c���Î₾�����v�u�c�c���Î₾�����v�Ƃ����A
�\������ۂɎc���Ă���B
��x�́A�K��Ă݂��������ꏊ�B
�t�ɁA�����֍s�����I�[�X�g�����A�̗F�l�������B
���̗F�l���A���������Ă����B
�u�悩�����v�ƁB
������A���̖������Ȃ��B
�u���O�͎u�꒼�Ƃ̖{��ǂ��Ƃ����邩�v��
�����ƁA�u�E�`���A�ǂ��Ƃ�����c�c�v�ƁA
�ǂ����A����������ȕԎ��B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
����V��i�w��̍�ɂāx�u�꒼��
�E�B�L�y�f�B�A�S�Ȏ��T�ɂ́A�u��̍�ɂāv�̂��炷�����ڂ��Ă����B
��������̂܂Љ���Ă��炤�B
�w�����R����̓d�Ԃɂ͂˂�����������u�����v�́A��{���ɏ�艷���K���B�u�����v�͈�C�̖I�̎��[�ɁA�₵�����Â��Ȏ��ւ̐e���݂������A��ɋ����h�������l���𓊂����A�K���ɓ����f���Ă���p�����Ď��̒��O�̓��������낵���Ȃ�B����Ȃ�����A���C�Ȃ���������̐̏�ɃC�����������B
���������Ɠ����������̂�����ɓ����Ď���ł��܂��B����݂�������Ɠ����ɐ������̗҂����������Ă���u�����v�B�����̓����B�̎��Ɛ����Ă��鎩���ɂ��čl���A�����Ă��邱�ƂƎ���ł��܂��Ă��邱�ƁA����͗��ɂł͂Ȃ������Ƃ������S�����B�����Ė��E�������u�����v���Ȃ݂�x�i�E�B�L�y�f�B�A�S�Ȏ��T���j�ƁB
���u�꒼��
���łɁA�u�꒼�Ƃɂ��āA�E�B�L�y�f�B�A�S�Ȏ��T�ɂ́A���̂悤�ɂ���
�w�u��̍�ɂāv�i���̂����ɂāj�́A�u�꒼�Ƃ̒Z�ҏ����B1917�N�i�吳6�N�j5���ɔ����h�̓��l���w�����x�ɔ��\�B
�S�������̑�\�I�ȍ�i�Ƃ����B�u�꒼�Ƃ�1910�N�i����43�N�j�Ɂw�����x��n������i�\���Ă���A�����Ƃ̑Η�����L���������ɏZ�݁A�Ėڟ��̏��߂ɂ���Ɂw�Ö�s�H�x�̌��^�ƂȂ�u���C����v�����M���Ă����B
1913�N�i�吳2�N�j4���ɂ͏㋞���Ă������A���N8���ɗ������ƎʼnY�֗��݂ɍs���A�f�l���o�����ċA��r���A���H�̑�������Ă��ĎR����̓d�ԂɌォ��͂˔����d�����B
�����a�@�Ɏb�����@���ď����������A�×{�̂��ߏ�艷��i�u�O�؉��v�Ƃ������فi�����j�ɏh���j��K���B���̌�͏��]�⋞�s�ȂNJe�n��_�X�Ƃ��A1914�N�i�吳3�N�j�ɂ͌�������B1917�N�i�吳6�N�j�ɂ́u���X�̏ꍇ�v�u�D�l���̕v�w�v�u�Ԑ��y���̗��v�Ȃǂ̍�i�\���A���N10���ɂ͎����Ƃ̘a�����������Ă���B
���̂ɍۂ�������̑̌�����O�ꂵ���ώ@�͂Ő��Ǝ��̈Ӗ����l�����M����B�ȑf�Ŗ��ʂ̂Ȃ����̂ƓK�ȕ`�ʂŖ��ނ̖����Ƃ���Ă���x�i�E�B�L�y�f�B�A�S�Ȏ��T���j�ƁB
�@���������\���m���������ė��ɏo��̂́A�y�����B
���̉��s�����A�{������B
���W���P�W��
�@�u�꒼�Ƃƌ����A�w�Ö�s�H�x�B
�ǂ͂������A���e���v���o���Ȃ��B
������x�A�E�B�L�y�f�B�A�S�Ȏ��T�̏��������B
��������B
�w��l�����C����i�Ƃ��Ƃ������j�́A�����̖����𑗂鏬���ƁB����Ƃ������ɗ��ɏo���ނ́A�c���̏����h�ƌ����������Ɩ]�ނ悤�ɂȂ�B����Ȑ܁A���͌��삪�c���ƕ�̕s�`�̎q�ł��������Ƃ�m��ꂵ�ށB�悤�₭�����q�Ƃ��������ƌ������邪���q���]�Z�Ɖ߂���Ƃ������ƂōĂы�Y��w�����A����̑�R�Ɉ�l������B�厩�R�̒��Ő��_�����߂��Ă��ׂĂ������S���ɒB���A�u�Ö�s�H�v�ɏI�~����łx�ƁB
�@�i���z�h�I
�v���o�����I
���������b�������B
���W���P�X��
����́A���C�t�ƂQ�l�̂Q�l���B
�n���̃o�X��Ђ��^�c����A�a�c�A�[�𗘗p���邱�Ƃɂ����B
���������N��́u��Ƃ�́`�`�v�Ƃ������A�R�[�X�B
�����������Q�{�́A�㋉�̃R�[�X�B
���Ȑ����A�Q�O���قǁA���Ȃ��B
�@�V�C�͓܂�B
�l����n��Ƃ��A���F�̒Ⴂ�_���A�d�ꂵ�����ɋ���Ă����B
��ɍL�������J�_�B
�V���̓V�C�\��ɂ��A�����ʂ́A�J�B
�悩�����I
���̂Ƃ���̖ҏ��B
�ҏ��͂��育��B
���T�Q�O�h����
����i�W���P�X���j�A�j���[���[�N�̊����s�ꂪ�A�T�Q�O�h�����\�������B
�����Ƃ̎w�W�������������ƁB
���ƕی��̐\���������ӂ������ƁB
�@���������Ƃ��́A�u���v�Ɏ���o���Ă͂����Ȃ��B
�v���Ƃ������A���{�b�g���A�P�O�O�O���̂P�P�ʂŁA�R���s���[�^�[���������J��Ԃ��B
���{�b�g�������Ƃ������B
�f�l�̎����������荞�ރX�L�͂Ȃ��B
�c�c�Ƃ������A�J���ɂ����̂́A�������B
���v�I�ɂ��A�X�T���̌l�����Ƃ́A�������邱�Ƃ��킩���Ă���B
���������ӂ��ɁA����������Ƃ��́A����Ɋ댯�B
���a�c�A�[������H
�o�X������o���ƁA�K�C�h�������������B
���܂킵�Ȍ��������������A�u������ׂ�͐Â��Ɂv�ƁB
���R�̂��Ƃ����A�a�c�A�[���i�������B
����������ۂ��������B
�@���̂S�O�N�ԁB
�����́A�i���͎��R�B
�J���I�P�͒�ԁB
�o�X�ɏ��ƁA�܂����ȏЉ�B
���ꂪ���X�ɏ��Ȃ��Ȃ��āA���Ɏn�܂����̂��A�r�f�I��f�B
�ŁA�Ō�̎c�����̂��A�u������ׂ�v�B
�K�b�n�n�n�A�Q���Q���A�M���[�M���[�B
���̂�����ׂ�ɁA���ӂ�����悤�ɂȂ����B
�������������Ԃ������B
���v�w����
�@�L�����߂��邱��A�������J������@���n�߂��B
�����ԁA���̊O���A�^�����ɂȂ����B
�J�������l���������A���͍D���B
�S�����������B
�]�݂��̓������A�悭�Ȃ�B
�@�c�c�������O�A�w���䌧�z�O���ւ̗��x�ɂ��ď������B
���C�t�ƌ��܂����A�Əo�������B
�Əo�����A�z�O���܂ōs���Ă����B
���A�����́A���C�t�Ƃ�������B
�����肵���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
����ɁA�߂����B
�����b�́A�ǂ����������ł��܂����B
�@�������v�w�́A�������̃p�^�[�����J��Ԃ��Ă���B
���T�C�N��
�@�v�w�_�Ƃ����̂�����B
�͂₵�_�i���ɉ��߂���ƁA�����Ȃ�B
�i������j���i�s������j���i�ْ����j���i���������������j���i��p���j���i�C�����j���i������j���c�c�B
�@�ŁA���́A��p������C�����B
��������A�i�����傰�����ȁH�j�A���́A�������Ă�������ɁA��V��ɗ��Ă���B
���x�̂��Ƃ�����A������������̗����b��{�C�ɂ��Ȃ��B
�`�Z�ł���A�u���炠��A�����낤���܁v�Ȃǂƌ������肷��B
�ŁA���������Ƃ��A���́A�����i����B
�u���x�́A�{�C�ł��B����ȃ��c�Ƃ́A���T���ɗ������܂��v�ƁB
�@���A���ʂ́A���̃U�}�B
�����Â��āA�Q�`�R���B
�R��������ƁA�܂����ɖ߂�B
�����̃^�C�����O�͂��邪�A�܂����C�t�̂ق�������ɖ߂�A�Â��Ď��̂ق����ӂ�B
����ł����܂��B
�i�ѕv�w�́A�ǂ��Ȃ�낤�H�A�Ɗ��҂��Ă����l���������肳���āA���߂�c�c�B�j
����V��
��V��ɂ́A�ߌ�R������A�������B
�ꌩ���Ă킩��B
���C������B
�s����������q�B
�V��j���A���܂��܁B
�q�w���L���B
�����ȓX�܂ŁA�{�C�I
���̖{�C���A����Ɠ`����Ă���B
�@�ŁA�����������܂������ق́A�w��ԁx�B
�x�O�̊C�����ɂ��邪�A���̏�V��ł��A���ꋉ���ق��������B
�@�e�����̒��ɉ�����B
�����̃x�����_���L���B
���낢��ȗ��قɔ��܂������A����������Ȃ��̂T���́A�����������B
�u��ɂ͏オ������̂��v�ƁA���Q�̂��ߑ��B
���X������́A�ԉΑ��
��A�X������ԉΑ�����Ƃ����B
���傤�ǐ�������̃z�e���̉�����ł��グ����Ƃ����B
���A���̂X����҂��Ă���Ƃ��B
�����́A�W�F�T�V�B
���ƂR���B
�@�r�f�I�J�����́A�X�^���o�C�B
���ԉ͏I�����
�������̔��܂��Ă��镔���́A�P�O�P�����B
�����̖��O�́A�u���Ɓv�B
�u�꒼�Ƃ́u���Ɓv�B
���C�t�́A��������āA�u���Ȃ������ʂɗ��́H�v�ƁB
���A���͗���łȂ��B
���R�B
�������A�ǂ������킯���A���ꂵ�������B
�@���ɂ́A�����̖ړI������Ƃ悢�B
����ɂ��ẮA��ɏ������B
���A����͐�����u�ړI�v�ɂ����ʂ���B
�����������̂łȂ��Ă��悢�B
���ׂȂ��̂ł悢�B
�������́A����ɂ����݂��āA������B
������
�Ƃ���ō����A�����֗���r���A�o�X�̒��ł���Ȏ������������B
�����@���p�\�R���̉������邳���A�ƁB
�K�C�h����̂ق��ɁA����ꂽ�B
���A����Ȍo���́A�͂��߂āB
�@�����Ă����p�\�R���́A�s�n�r�g�h�a�`�̂l�w�B
�����̒��Œ@���Ă��Ă��A�����ƌ����킯�ł͂Ȃ����A�Â��B
�قƂ�lj��͂��Ȃ��B
�܂����̂Ƃ��́A�p�\�R�����������A���[����ǂ�ł��������B
���ǂ��A��s�@�̒��ł��A�d�Ԃ̒��ł��A�p�\�R���͕K���i�B
���ꂪ�u���邳���I�v�ƁB
���͂��Ȃ��ɎӍ߂��A�p�\�R�����J�o���̒��ɂ��܂����B
�@�����������l�́A�V�O�ΑO��̘V�v�w�B
�ʘH���͂����Α��̐Ȃ̐l�����������B
�����A�p�\�R���ƌg�ђ[���i�g�ѓd�b�j�̋�ʂ����Ȃ��l�����ł͂Ȃ��������B
���邢�̓p�\�R���ɑ��āA���x�̌������������Ă���i�H�j�B
���������l�͑����B
�����������Ȃ�����A����������l���A�O��I�ɖь�������B
�p�\�R���Ŏd�������Ă���l���A�O��I�Ɍy�̂��Ă݂���B
���������l�́A���Ȃ��̎���ɂ��A�P�l��Q�l�͂���͂��B
�U�O�Έȏ�̐l�ɑ����B
�@�u����Ȃ��̎g���Ă���l�ԂɁA���N�Ȃ̂͂��Ȃ��I�v�ƁB
�ȒP�ɂ������߂��Ă��܂��B
�����o�X�̒��ʼn�����V�v�w���A����Ȑl������������������Ȃ��B
�@�T�[�r�X�G���A�Ŕ����Ă����A�u����v���Q�A�����^���A�u���݂܂���ł����v
�Ǝӂ�ƁA��u�˘f�������A���̏u�Ԃɂ́A�₳�����Ί���������B
���W���Q�O��
�@���}�Ȓ��B
�Â��Ȓ��B
�ڊo�܂��́A���A�U���ɃZ�b�g�����B
���͂P�O�����돰�ɓ������̂ŁA�������Ԃ͂W���ԁB
�@���̊O�́A���Y�p�ɂȂ��Ă��āA���D�����ǁA�E���獶�֒ʂ�߂��Ă������B
�u�ǂ��炪�C�Ȃ̂��낤�H�v�ƁB
��V�肪�����ʂɂ��邩��A�����ʂ��C�H
�悭�킩��Ȃ����A�g�͐Â��B
�R�̊Ԃ𗬂��_���Ⴍ�A�����B
���a�c�A�[
�@�a�c�A�[�𗘗p����̂́A�P�N���Ԃ�H
����܂ł́A�����̂悤�ɗ��p���Ă����B
���A�Ō�ɁA������ׂ�I�o������ƌ��_�����A�������茙�C���������B
�@�ŁA������A�����v�����B
�֗��ŗ������������A��͂莄�����ɂ͌����Ȃ��A�ƁB
���C�t���������f�����B
�@�o�X��Ђ̃T�[�r�X�͂悢�B
�K�C�h���悢�B
�R�[�X�����ق��A�悢�B
�������q�w���悭�Ȃ��B
�����A��ȗ�����H�ׂȂ���A�K�n�n�E�Q���Q���ƁA�T�ᖳ�l�ɑ����ł���I�o������������B
���̐����A�����̒[����[�܂ŕ������Ă����B
�L��������Ă���Ƃ����A�����B
�����̒��܂ŁA���̑吺���������Ă����B
�c��̂Q�O���l�͐Â��ł��A���������I�o����Q�`�R�l�ł�����ƁA���s���䖳���B
�@
�@�u������߂悤�ˁv�Ǝ��B
�u�����ˁv�ƃ��C�t�B
�@
����V��ɂ�
�@�u�꒼�Ƃ́w��̍�ɂāx�B
�͂₵�_�i�́w��V��ɂāx�B
���͂������l�̎���ł͂Ȃ��B
��y�����l�����A�����ɂ���B
�u�꒼�Ƃ̐̂ɂ́A���ׂĂ̌�y�����w�ɏW�������B
���l�ɂƂ��ẮA�Â��ǂ�����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�����܂����Ƃ͎v��Ȃ��B
�����u�꒼�Ƃ̎���ɐ����Ă����Ƃ��Ă��A���͂����̂��̏����B
���ɏ������Ƃ���ŁA�ڂɗ��߂Ă����l�����Ȃ��������Ƃ��낤�B
���A��
�@�W���Q�O���A�ߌ�W�������ɁA�l���֖߂��Ă����B
������A�^�̈������ƂɁA�i�{���ɉ^�̈������ƂɁj�A�^������̐ȂɁA�Q�g�̕v�w�B
���ǂ����A�Q�l�̂���������w������B
�Ƃ��ɂV�O���炢�B
�������v�w�́A��납��Q��ڂ̐ȁB
�@�Q�x�A���ӂ������A�A���Ă����̂̓C���~�B
�u�A�`���A���邳�����Ē��ӂ��ꂽ����A��������̐Ȃɂ����܂���I�`�v�ƁB
�킴�Ƃ݂Ȃɕ�������悤�ȑ吺�ŁA�Ȃ𗣂�Ă������B
���A����ŐÂ��ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��B
�����s���R�Ȃ̂��A���̒��̂P�l���A����I�ɑ吺�ł���ׂ�܂���B
���A����̐��͕������Ȃ��炵���B
���肪�������������тɁA�u�����A���H�v���J��Ԃ��Ă����B
�@�ق��̂قƂ�ǂ̋q�͐Â��������B
�݂ȁA���ꂼ��̗����y����ł����B
���A������A�^�����������B
�@�a�c�A�[�ցF
�u��Ƃ�́`�`�v�ł́A�U�l�ȏ�̒c�̋q�͐\�����݂�f���Ă���Ƃ��B
�����ւ炵�����Ƃ����A�ł���A�R�l�ȏ�ɂ��Ă͂ǂ����H
��������A���������q��r�����邱�Ƃ��ł���B
�@�����Ƃ��A���C�t�̈ӌ��ʂ�A�a�c�A�[�́A���炭�̓R���S���B
���������q�����Ă��A�K�C�h�͉������ӂ��Ȃ��B
�m��ʊ�B
�őO��ɍ����Ă��邩��A�㕔���Ȃ̂��Ƃ͂킩��Ȃ��B
�@���A�����Č����Ȃ�A���̐i�������҂��āA���͂����v�]����B
�i�P�j�|�C���g�K�C�h�c�c�K�v�Ȃ��Ƃ������K�C�h����Ƃ����̂́A�悩����
�i�Q�j�a�f�l�c�c���邳���r�f�I���Ȃ��Ȃ����̂́A�悩����
�i�R�j�c�̋q�̐����c�c�悩�������A������ׂ肪�ړI�̂������ɂ́A���т������Ăق����B
�i�S�j���Ԃ̎����c�c�������Ƃ��Ă��āA�悩�����B
������
�@�w�����ォ��̔O�肪���Ȃ����B
�u�꒼�Ƃ䂩��́u��̍�v�������̖ڂŌ��邱�Ƃ��ł����B
���C�t�����������������B
�@���̃I�o��������Â���������A���͂S�́A���������B
���̃I�o������̂������ŁA�o�X���̂��̂��A���⎺�ɁB
�o�X���~�肽�Ƃ��A�ق��Ƃ����̂́A��������������ł͂Ȃ��B
�I�o������ƕʂ�邱�Ƃ��ł�������B
�i���������A�I�o������̂�����ׂ��s�����Ɏv���Ă���̂́A�����������ł͂Ȃ������B
��x�A�������ӂ����Ƃ��A�O�̐Ȃ̐l���U������āA�����������B
�u���肪�Ƃ��������܂��v�ƁB
�i�������A�ǂ����Ă��̓��{�ł́A���������I�o������̘b���������́A������ɂȂ��Ă���̂��H
�g�ѓd�b�ɂ͂��邳���B
�������I�o������́A������B
���������B
���{�����ł͂Ȃ��B
�����������{�l���A���E���֏o�����Ă����A���{�l�̒p�����炵�Ă���I�j
�@�Ȃ��^�]��ƃK�C�h�́A�����ւ����������B
�u��Ƃ�́`�`�v�Ƃ������ƂŁA�I�肷����ꂽ�l�����Ȃ̂��낤�B
�Ƃ��ɗ��m�I�ŁA�C�����̂悢�l�����������B
���ꂾ���ɁA����̗��s�́A�c�O�I
�u�o�X�̒��œǏ��c�c�v�ƍl���Ă������A���̗]�T�́A�Ō�܂łł��Ȃ������B
�i�͂₵�_�i�@�ƒ닳��@�玙�@����]�_�@�c������@�q��ā@Hiroshi Hayashi �э_�i�@BW�@�͂₵�_�i�@�c�������@�玙�@����_�@Japan�@�͂₵�_�i�@��̍�ɂā@��V��@���@�u�꒼�Ɓ@�Ö�s�H�j
Hiroshi Hayashi�{�{�{�{�{�{�`����.�@�Q�O�P�P�{�{�{�{�{�{�͂₵�_�i�E�э_�i
���u�ڂ��͐����ی�邩��A���܂ւ�v�i�䉮����E�u�T������v�Q�O�P�P�N�X�E�R�j
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�G���u�T������v�ɁA����ȋ�������L�����ڂ��Ă����B
�䉮���ꎁ���A�Βk�`���̋L���̒��ŏq�ׂĂ���B
�w�c�c���܂���s�ł́A�P�W�l�ɂP�l�������ی��
�Ă��āA���{�̋��琅���́A�S���S�V�s���{����
���ł��A�S�T�ԖځB
�Ȃɂ���A���w���ňꌅ�̂����Z�A�܂��オ�ł��Ȃ�
�q�ǂ����P���������ł��ˁB
���������q�ǂ��ɐ搶���A�u������������Ȃ��ƁA
���ƂȂɂȂ��č��邼�v�ƌ����ƁA�u�ڂ��͐����ی�
�邩�炩�܂ւ�v�Ɠ�����Ƃ�����ł��v�i�o�U�Q�j�ƁB
�䉮���ꎁ�́A����������āu�ϗ��I����v�Ƃ������t��
�g������B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
���V�тق��钆���l���w���i���t�[�E�m�d�v�r�j
�@����A����ȋL�����ڂɂƂ܂����i�Q�O�P�P�N�W���Q�O���j�B
�肵�āu����ݕĒ����l���w���A�����ɋ�J�̐e��K�ڂɁA�Q��V�щ��v�B
�����V�����A�ĉ؎������|�����̂炵���B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�ȉ��A���t�[�E�m�d�v�r���]�ځ{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
2011�N7��22���A�ĉ؎����E����ɂ��ƁA�č��֗��w���Ă���Ⴂ�����l�w���̒��ɂ́A���ɂ܂������g����ꂸ�A�e����������������Ŗ����V�тق����Ă���P�[�X������B
���T���[���X�ɏZ�ނ���ؐl�����̉Ƃɂ́A��C���痯�w�̂��ߓn�Ă��Ă��������q���Z��ł��邪�A��w�����߂��Ă����т͒�������܂܁B�����e����s�ɐU�荞��ł���Ă���4000���i��5���~�j�̐�����͊O�H��u�����h�i�AiPhone�ȂǃV���b�s���O�ł��ׂėV�тɎg���ʂ����A����ɃN���W�b�g�J�[�h�����x�z�܂Ŏg���Ă��܂��Ă���Ƃ����B
���e�͏��������Ă��邪�����ł͂Ȃ��A��ςȎv�������Ďq�ǂ��̊w��������H�ʂ��Ă���ɂ�������炸�A�u�l��LA�ɗ������ė����Ǝv���Ă���́H�@LA�Ȃ�ēc�ɂ������đ債�����ƂȂ�����Ȃ����B��C�̕��������Ɨǂ��v�u���e���ނ��藯�w����������A������������̂���J����̂����e�������őI���Ƃł��傤�v�ƁA�Ƃ�����܂��Ȃ���Ԃ��Ƃ����B�i�|��E�ҏW/���c�j
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�ȉ��A���t�[�E�m�d�v�r���]�ځ{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�����{�̌���
�@���w�P�N���ŁA�����Z�̋�オ�ł��Ȃ��Ƃ����b�́A���łɂQ�O�N�߂����O�̘b�ł���i�����s�j�B
�@�����Ō�����Ă����Ȃ��̂́A�����Z�̋��Ƃ����Ă��A���x��������B
�u�j�C�`�K�Q�A�j�j���K�S�c�c�v�ƈËL���郌�x���B�c�c���x���P
����Ȃ�c�t�����ɂ��ł���B
�@�Â��ă����_���ɁA�u�V�T���H�v�ƕ�����āA�����ɁA�u�P�Q�v�Ɠ����郌�x���B�c�c���x���Q
������̈Ӗ��i�S�{�S�{�S���S���R�j���킩���Ă��Ă̘b�ł���B
�Q�O�N�O�ł����A���x���P�͂ł��邪�A���x���Q���ł��Ȃ��B
����Ȓ��w�P�N���ŁA�Q�O���߂��������i�����s�j�B
�@�䉮���ꎁ�̘b�ɂ��A�u���w���ňꌅ�̂����Z�A�܂��オ�ł��Ȃ��q�ǂ����P���������ł��ˁv�Ƃ������Ƃ炵���B
���������q�ǂ��������A��w���ɂȂ��Ă����B
���Q�O�O�W�N�V���̌��e���
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�Q�O�O�W�N�V���ɁA���̂悤��
���e���������B
���̒��ŁA�w���ł͕����̑����Z�A
�����Z���ł��Ȃ���w���ȂǁA�����������Ƃ��Ȃ��B
�u���w�����x���̖��ŁA���𗦂͂T�X���v
�i�������n��w�@���ɂ��Ē����A���s��w�����a�Y���j�v
�i���Q�j���������x�Ƃ����Ƃ���ɒ��ڂ��Ăق����B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
���������u�]
�@���̐��N�A�呲�̏A�E��l�C�Ǝ�̃i���o�[�������A���������B
�Ȃ������Ȃ̂��Ƃ����Ƃ���Ƀ��X�����Ȃ�������A������v�ȂǁA���������Ă����_�B
�����A�������āA���̔N��ɂȂ��Ă͂��߂Ă킩�������A�������ɂȂ��Ă����悩�����I
�@���ʂ܂ŏA�E��ƁA�N�����ۏ���Ă���I�@�c�c�ƁA���������s�������A���{�̐e�����͂���Ƃ����قǁA�v���m�炳��Ă���B
������q�ǂ��̎ɋ��z����B�����狳����v�͂������s����B
�@�����ꕔ�́A�ق�̈ꕔ�́A�����������A���������̌����ƊNJ��ɂ����݂��A���{���x�z���鎞��͏I������B
������v�ǂ��납�A�o�ω��v���O�����A����ɔ_�����������A���ׂă{���{���B
�������������قǁA����挊���@���Ă����B
���̋�����v�ɂ��Ă��A�h�C�c��J�i�_�A����ɂ̓A�����J�̂悤�Ɏ��R������悢�B
�w�Z�͎��R�I�𐧂̒P�ʐ��x�ɂ��āA�ߌ�̓N���u���ɂ���悢�i�h�C�c�j�B�w�Z���A�n�������̂ɃJ���L�������A�w�����j�ȂǔC����悢�i�A�����J�j�B
�ݗ����ݗ����������R�ɂ���悢�i�A�����J�j�B
������ł����K���ׂ����{�͂���ł͂Ȃ����I
�@���A���Đ�i���ŁA���Ƃɂ�鋳�ȏ��̌��萧�x���������Ă��鍑�́A���{�����B
�I�[�X�g�����A�ɂ����萧�x�͂��邪�A�B���{�̈ϑ��������Ԓc�̂��A���̌�������Ă���B
����������͈͂́A�I���Ȑ��`�ʂƖ\�͓I�\���̂݁B���j�ɂ��ẮA���������A���肵�Ă͂����Ȃ������݂ɂȂ��Ă���B
���E�̋���́A���S�Ɏ��R���̗���̒��Ői��ł���B
���Ƃ��A�����J�ł́A��w���w��̊w���A�w�Ȃ̕ύX�͎��R�B�܂��������R�B
��w�̓]�Ђ��玩�R�B
�܂��������R�B
�w�Ȃ͂������̂��ƁA�w���̃X�N���b�v�A���h�r�����h�i�n�݂Ɣp�~�j�́A���풃�ю��B
�Ȃ̂ɂȂ����{�̕����Ȋw�Ȃ́A�����������R���ɂ͔w�������A���R���������������̂��H�@
���邢�͎��������̊NJ��ƌ������k������邱�Ƃ��A����Ȃɂ����킢�̂��H
�@���v�����邽�тɁA���������ɂق���т��ł���B�����ł܂��V���ȉ��v�����݂�B�u���v�v�Ƃ��������A�u�ق���т�D�����߂̎��]�ԑ��Ɓv�Ƃ����ɂӂ��킵���B
�������łɓ��{�̋���͂ɂ������������������Ȃ��Ƃ���ɂ��Ă���B
���̂܂܂����A���ƈ�Z�N��҂������āA���̋��烌�x���́A�A�W�A�ł��Œ�ɂȂ�B
���邢�͂���ȑO�ɂł��A�Œ�ɂȂ�B�����w�Z�⍂�Z�̘b�ł͂Ȃ��B
��w���炪�A���B
�@����Ȃ��ƂɁA��������w�ł��A���Ȍn�̊w���͂Ƃ��������A���Ȍn�̊w���́A�قƂ�Ǖ��Ȃǂ��Ă��Ȃ��B
���Ă��Ȃ����Ƃ́A�������Ȃ�����w���o�Ă���Ȃ�A��Ԃ悭�m���Ă���B
���̕��Ȍn�̊w���̒��ł��A�����Ƃ��h��ɗV�тق��Ă���̂��A�o�ϊw���n�̊w���ƁA����w���n�̊w���ł���B
���̂��Ƃ��A�������Ȃ�����w���o�Ă���Ȃ�A��Ԃ悭�m���Ă���B
�����⎄����w�̊w������I�@���������w�����A�����w�Z�ŕ�K���ƂƂ́I
�@���{�ł͑�w���̃A���o�C�g�́A��������I�Ȍ��i�����A����������A�����J�̑�w���͂����������B
�u�ڂ������ɂ͍l�����Ȃ��v�ƁB��w���x���̂��̂��A���{�̏ꍇ�A�敾���Ă���I
�@�������Ƃ����Ă��A�u�v���A���낤���ē��{�̋�����x���Ă���B
�������̓��{������x����������A�i�w�m�͂������̂��ƁA�w�Z���炻�̂��̂�����B
�m���Ɉꕔ�̊w���͖җ�ɕ�����B����������͂����܂ł��u�ꕔ�v�B���t�{�̒����ł��A�u����͈��������Ɍ������Ă���v�Ɠ������l�́A��Z��������i��Z�Z�Z�N�j�B
�㔪�N�̒��������������ӂ����B�ނׂȂ邩�ȁA�ł���B
�@������K������Ƃ����ȂƂ��������x���̘b�ł͂Ȃ��B
���{�̋�����v�́A�O�Z�N�͒x�ꂽ�B
���������A���v�i�H�j���Ă��A���̌��ʂ��o��̂́A����ɓ�Z�N��B
���̂��됢�E�͂ǂ��܂Ői��ł��邱�Ƃ��I�@
���{�̕����Ȋw�Ȃ́A���܂��ɑ�{�c���\��낵���A�u���{�̋��烌�x���͂���قǒႭ�͂Ȃ��v�i���P�j�ƌ����Ă��邪�A���������b�͉L�ۂ݂ɂ��Ȃ��ق����悢�B
���ł͕����̑����Z�A�����Z���ł��Ȃ���w���ȂǁA�����������Ƃ��Ȃ��B
�u���w�����x���̖��ŁA���𗦂͌܋こ�v�i�������n��w�@���ɂ��Ē����A���s��w�����a�Y���j�i���Q�j���������B
�@���邢�͂���ȃV���b�L���O�ȕ�����B
���E�I�ȕW���ɂ��Ȃ��Ă���A�s�n�d�e�k�i���ۉp�ꌟ�莎���j�ŁA���{�l�̐��т́A��Z�܂������A��܁Z�ʁi���N�j�B
�A�W�A�œ��{��萬�т��������́A�����S�����炢�B
�k���N�ƃu�[�r�[�𑈂����x���v�i�T���V���j���������B
�I�[�X�g�����A������ł��A�ǂ̑�w�ɂ��A�m�[�x����҂��S���S�����Ă���B
���������{�ɂ͐�����قǂ������Ȃ��B
���̓V���̓���ɂ́A��l�����Ȃ��B���Ȃ݂ɃA�����J�����ł��A��܁Z�l���̎�҂�����B���[���b�p�S�̂ł́A�����Ƒ����i�c�ی��w�E�E�Q�O�O�W�N�����j�B
���u�����̎q�ɂ������āc�c�v�́A���z
�@�قƂ�ǂ̐e�́A�����l����B
�u�����̎q�ɂ������āc�c�v�ƁB
����������͌��z�B
�܂������̌��z�B
�@�q�ǂ��Ƃ����̂́A�����Ȃ�A�z�����̋����z����莆�B
�Љ�Ƃ����u�F���v�̒��ɗ��Ƃ����A���̂܂܂��́u�F�v���z�����Ă����B
�Љ�̐F���u���F�v�Ȃ̂ɁA�����̎q�ǂ��������u���F�v�ɂ��悤�Ƃ��Ă��A���ʁB
�q�ǂ��Ƃ����̂́A�q�ǂ��̂ǂ����̉e���͂̂ق����A�͂邩�ɋ�����B
�����ĂقƂ�ǂ̒����Z���́A�u�e�̂悤�ɂȂ肽���Ȃ��v�Ɠ����Ă���i���t�{�����j�B
���ł́A�w�e�̉�����Y����x�B
�قƂ�ǂ̎�҂����́A�����l���Ă���B
�@���A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���������ƁA��҂����́A�җ�ɔ�������B
�u���́A�������I�v�ƁB
�܂�A�����Ɉӎ��̃Y�����A�N����B
���e�ւ̎d����
�@�U�O��A�V�O��̐l�����ɂƂ��āA�e�ւ̎d����́A���R�������B
��������s��Œm�荇�����j�f����i�����A�U�X�j�́A�����������B
�u���̏��C���͂R�O�O�O�~�ł����B�����A�P�O�O�O�~���A�������Ƃ֑���܂����v�ƁB
�@���������������B
�����O����A�����̖�T�O�������Ƃ֑����Ă����B
�܂����ꂪ�����̏펯�������B
�@���A���́A�������B
�u�A�E������Ԃ��v�u����������������Ԃ��v�ƌ����Ȃ���A���������Ƃ���A�u���������Ȃ��I�v�ƁB
����������҂��A�җ�ɔ�������B
���ƂA�Ȃ��Ă��A�݂₰�̂ЂƂ�������Ă��Ȃ��B
��{�I�ȕ����ŁA�ӎ����̂��̂��Y���Ă���B
����w���Ƃ͖�����
�@�����̏��q��w�𑲋Ƃ��������i�Q�V�j�������B
�p���Ȃ𑲋Ƃ����Ƃ����B
�ŁA�����ɂ��������Ă݂��B
�u�r�u�n�n�̍\�����A�r�u�n�̍\���ɂȂ����ɂ́A�ǂ������炢���́H�v�ƁB
����ɓ����āA���̏����́A�����������B
�u���A����H�v�ƁB
�@�������Ƃ̒��w���Ȃ�m���Ă��邱�Ƃł��A��w�̉p���Ȃ��o���Љ�l���m��Ȃ��B
�����Ƃ����ł́A��w�̉p���ȂƂ����Ă��A������B
���Z�����g�����ȒP�ȃe�L�X�g���g���A���Ƃ͗V�тق��Ă���B
�����{�̌���
�@���������A�����Ƃɂ���A��ʎЉ�ɂ���A����ɐe�����ɂ���A���������������A�ǂ��܂Œm���Ă���̂��H
����́A�����{���{���I
�ϗ��ς��̂��̂��A���Ă���I
�@�ŁA�䉮���ꎁ�̘b�͗�O�ł���ƐM���������A�ЂƂC�ɂȂ邱�Ƃ�����B
�w�P�W�l�ɂP�l�������ی���Ă���x�Ƃ��������B
�@�P�W���тɂP���тƂ����Ӗ��Ȃ̂��B
����Ƃ��P�W�l�ɂP�l�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂��B
�����u�P�W�l�ɂP�l�v�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�v�w�{�q�ǂ����킹�Ă̂S�l�Ƒ��Ƃ���Ȃ�A�u�S���тłP���сv�Ƃ����v�Z�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�{�����낤���H
�@�����Œ��ׂĂ݂�ƁA�u�����ی엦�v�́A���{�̂����A�Q�T�E�V�i�P�^�P�O�O�O�j�i�Q�O�O�V�N�x�j�Ƃ������Ƃ��킩�����i�����ȓ��v�ǁj�B
������P�O�O�������Z����ƁA�Q�E�T�V���Ƃ������ƂɂȂ�B
���Ɂu�@�s���{���ʂ̐����ی엦�i�����ł͐��т̔䗦�łȂ��A�ی�l���̐l����l������̔䗦�j��}�������v�Ƃ��邩��A���ї��ł͂Ȃ��A�P�O�O�O�l������̔䗦�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�Q�E�T�V���Ƃ����A�P�O�O�l�ɂ��A��R�l�B
�t�Ɍ����A�u�R�R�l�ɂP�l�v�ƂȂ�B
���A���݁A����ɕs���̗��͂͂������Ȃ��Ă���B
��͂�䉮���ꎁ���w�E����悤�ɁA�u�P�W�l�ɂP�l�v�Ƃ����̂́A���̂܂܁u�P�W�l�ɂP�l�v�Ƃ������ƂɂȂ�̂��B
�@�������ꂼ��ɉƑ�������Ȃ�A�u�P�W���тɂP���сv�ƂȂ�B
�i�������Ƒ������Ȃ��l���������c�c�B�j
�ǂ��ł���ɂ���A���A���̓��{�́A�����܂ŕn�����Ȃ��Ă���I
��������Ƃ���܂ŗ�����
�@�܂����A���{�͑�s�����B
�勰�Q�͂��łɎn�܂����B
���̐�A���̓��{�́A����^���ÁB
�₪�ē��{�l���A�O���֏o�҂��ɍs���˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B
�P�O�N�ǂ��납�A�T�N��҂������āA�����Ȃ�B
�����ł͂Ȃ��B
�����̏�ŁA�����Ȃ炴������Ȃ��^���ɂ���B
�@�����Ȃ����Ƃ��A���̎�҂����́A�ǂ�����̂��낤�B
����ł��e�̃X�l��������Â������Ȃ̂��낤���B
�u����ȃI���ɂ����̂́A�e���G���낤�I�v�ƁB
���邢�́u����ȓ��{�ɂ����̂́A�e���G���낤�I�v�ƌ�����������Ȃ��B
�@��ɏ������j�f����������������B
���ɕv�����āA���̕v�������������B
�u���{��������Ƃ���܂ŁA��x�A�����邵���Ȃ��ł��傤�ˁv�ƁB
�@���̂Ƃ���A�����g���A�����l���n�߂Ă���B
������Ƃ���܂ŗ����A�����ŋC���������Ȃ��A�ƁB
�ƂĂ��ߊϓI�Ȍ��������A���ꂪ���̋���̌���Ƃ������ƂɂȂ�B
�i���P�j
�@���ۋ��瓞�B�x�]���w��i�h�d�`�A�{���I�����_�E�����N�j�̒����ɂ��ƁA���{�̒��w���̊w�͂́A���w�ɂ��ẮA�V���K�|�[���A�؍��A��p�A���`�ɂ��ŁA��܈ʁB�ȉ��A�I�[�X�g�����A�A�}���[�V�A�A�A�����J�A�C�M���X�Ƒ����������B���Ȃɂ��ẮA��p�A�V���K�|�[���Ɏ����ő�O�ʁB�ȉ��؍��A�I�[�X�g�����A�A�C�M���X�A���`�A�A�����J�A�}���[�V�A�A�ƁB
���̌��ʂ��݂āA�����Ȋw�Ȃ̓��v���F���w�Z�ے��́A�u���ʂ͂����������A�i���{�̋���́j�����������ۓI�ɂ݂ăg�b�v�N���X���ێ����Ă���ƌ�����v�i�����V���j�ƃR�����g���Ă���B������w��w�@�����̊��J���F�����A�u���̉��v�ł������傤�ԂƂ������b�Z�[�W��^����͖̂�肪�c��v�Əq�ׂĂ��邱�ƂƂ́A�ΏƓI�ł���B
���Ȃ݂ɁA�u���w���D���v�Ɠ����������́A���{�̒��w�����Œ�i�l�����j�B�u���Ȃ��D���v�Ɠ����������́A�؍��ɂ��Ńr����ł������i�؍��ܓA���{�܌܁��j�B�w�Z�̊O�ŕ�����w�O�w�K���A�؍��Ɏ����Ńr����B����A���̕��A�O��i��ܔN�j�Ɣ�ׂāA�e���r��r�f�I�����鎞�Ԃ��A��E�Z���Ԃ���O�E�ꎞ�Ԃɂӂ��Ă���B
�ŁA���ۂɂ͂ǂ��Ȃ̂��B�������ȑ�w���w�����V�c���v�������A�������钲�����ʂ����\���Ă���B���������ׂ��u�w�͒����̖���Ɛ������v�ɂ��ƁA���̂悤�Ȍ��ʂ��������B
���̓�Z�N�ԁi��㔪��N�����Z�Z�Z�N�j�����ŁA�ȒP�ȕ����̑����Z�̐��𗦂́A���w�Z�N���ŁA���Z�E��������A�Z��E�����ɒቺ�B�����̊���Z�́A��Z�E��������Z�Z�E�܁��ɒቺ�B�����̊|���Z�́A�����E���玵�Z�E�ɒቺ�B��������Ɗ|���Z�̍����v�Z�́A�O���E�O������O��E�����ɒቺ�B�S�̂Ƃ��āA�Z���E�こ������E�܁��ɒቺ���Ă���i�������Œ����j�A�ƁB
�@���낢��ى����܂����ӌ���A�����Ȋw�Ȃ�i�삵���ӌ��A���邢�͕����Ȋw�Ȃ�ᔻ�����ӌ��Ȃǂ��������Ă��邪�A���{�̎q�ǂ������̊w�͂��ቺ���Ă��邱�Ƃ́A�����^���悤���Ȃ��B�����V�c�����̒��������A���w�Z�N���ɂ��Ă݂�ƁA�u�Z���������v�Ɠ������q�ǂ����A��Z�Z�Z�N�x�ɎO�Z�������i��㎵���N�͈�O���O��j�B
���Ɂu�Z�����D���v�Ɠ������q�ǂ��́A�N�X�ቺ���A��Z�Z�Z�N�x�ɂ͎O�܁��サ�����Ȃ��B�����͂��낢�날��̂��낤���A�u���{�̋��炪���̂܂܂ł����v�Ƃ́A������l���Ă��Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A�u�i���{�̋��炪�j���ۓI�ɂ݂ăg�b�v�N���X���ێ����Ă���ƌ�����v�Ƃ����̂́A���͂⌶�z�ł����Ȃ��B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�i���Q�j
�@���s��w�o�ό������̐����a�Y�����i�o�όv��w�j�̒����ɂ��A���̂悤�ł������Ƃ����B
�����͈����N�Ɠ�Z�Z�Z�N�̎l���Ɏ��{�B�g�b�v���x���̍����ܑ�w�Ōo�ϊw�Ȃǂ����������w�@�����O�Z�l�ɁA���w�A���Z���x���̖������������B���ʁA��ܓ_���_�ŕ��ς́A��Z�E���ܓ_�B���������A�w���̊w���ɂ������������A���鍑����w�̕��w����N���ŁA���E��l�_�B�����̑�w�̊w�������A��w�@�����D���т��Ƃ����Ƃ����B
�i�͂₵�_�i�@�ƒ닳��@�玙�@�玙�]�_�@����]�_�@�c������@�q��ā@�͂₵�_�i�@�w�́@���{�̎q�ǂ��̊w�́@�q���̊w�́@�p��́@�i�͂₵�_�i�@�ƒ닳��@�玙�@�玙�]�_�@����]�_�@�c������@�q��ā@�͂₵�_�i�@Hiroshi Hayashi education essayist writer Japanese essayist ����̎��R���@��Ƃ苳��@��Ƃ苳��̕��Q�@�t�s������{�̋���@���M���Ȃ������{�̎�҂����@�����ی�@�͂₵�_�i�@�����ی쐢�с@�͂₵�_�i�@�����̌v�Z�@�����Z�̋��@�|���Z�̋��@�w�͒ቺ�@���{�̌���j2011/08/21�L
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|
||
�y����A�H��i�͂����j�ցz
 �{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
�x�ɂ��c��A�Q���B
����ɂȂ��āA���C�t���A�ˑR�A�t�e�n���������ƌ������B
�t�e�n�H
�\�o�����ɉH��s�i�͂������j�Ƃ�����������B
�����Ɂu�t�e�n��فv�i�������̂́u�F���Ȋw�����فv�j������B
�u�H��֍s�������H�v�Ɛ���������ƁA�u����v�ƁB
�����ō����́A���É����A����s���̃o�X�ɏ�荞�B
�ߑO�W���R�O�����B
�̂́u�������v�ƌ������B
�w������A�悭���p�����Ă�������B
�r���A�������̊ό��n���A���̂܂ܒʂ�B�c�c�ʂ����B
���������������B
�����́A���É��������܂ŁA�W�`�X���Ԃ����������B
���́A�S���ԁI
�����Q�l���ŁA�����͍����A�P���P�O�O�O�~�B
�i���A�P���A�Q�V�T�O�~�I�j
�i�q�̖z�B
�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{�{
���t�e�n
�@�t�e�n��قƂ����Ă��A���܂���҂��Ă��Ȃ��B
���҂��Ă��Ȃ����A���҂��Ă���H
�ꉞ�A�H��s�͂t�e�n�̏o�v�n�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���炵���B
�̂��炻�������`�����c���Ă���B
�A�_���X�L�[�^�t�e�n���v�킹������A���̂ЂƂB
���͏������A�܂艹�̏o��������A�A�_���X�L�[�^�t�e�n�ɂ�������B
�y���݁c�c���A��͂�ߏ���҂͋֕��B
���̎�̔����ق́A���������Ă����҂͂���B
�킩���Ă��邪�A�v����ɁA�������y���߂悢�B
���Ƃ́A�H���B
�@�z�e���͊m�ۂ������A�[�H�͂Ȃ��B
�ǂ����ʼn�����H�ׂ悤�B
�ł���ΊI�����B
���������������ȁH
����ѐ�
�@�t�e�n�͒��팻�ۂł͂Ȃ��B
�S�쌻�ۂƂ͈�����悷�B
�u�Ȋw�v�ł���B
�܂������������x���Ř_������ׂ��B
�@�c�c����ɂ��Ă͂����A���x�������Ă����B
���̗��R�̑��B
�_���I�Ȉ�ѐ�������B
�f�^�����ȃC���`�L�͕ʂƂ��āA�t�e�n�����@�艺���Č������Ă����ƁA�����Ɉ�ѐ��������Ă���B
�܂�_�����ɖ������Ȃ��B
�@���C�t�Ǝ��́A��x�A����Ȃt�e�n��ڌ����Ă���B
���������o�������n�ɂȂ��Ă���B
���W�W�L��
�@�u���ʂ܂łɁc�c�v�Ƃ����������́A���ꎩ�́A�W�W�L���B
�悭�킩���Ă���B
���������̂Ƃ���A�����ɂ��A�����l���邱�Ƃ��A�����Ȃ����B
�H��̂t�e�n��ق��A���̂ЂƂB
�Ȃ�A���{���яo������c�c�Ƃ����ӌ�������B
���Ƃ��A�����J�̃��Y�E�F���B
�P�X�S�V�N�A�A�����J�̃��Y�E�F���ɁA�t�e�n���ė����Ă���B
���̃��Y�E�F���B
���A���͑�̔�s�@�����B
�Q�X�̂Ƃ���s�@���̂ɑ������Ă���A�����Ȃ��Ă��܂����B
����܂ł́A���T�̂悤�ɔ�s�@�ɏ���Ă������c�c�B
�@���ʂȗ��R�ł��Ȃ�������A��s�@�ɂ͏��Ȃ��B
���̓_�A�t�e�n�́A���͕s���B
���Y�E�F���֍s��������Ƃ����āA�t�e�n��K��������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�A�����J���{���A���Ղ́u�R�v�̎����c��Ȃ��قǁA�؋��ނ����łɎn�����Ă��܂����Ƃ����B
�@�Ƃ��������A�������́A���̖錩�����̂����ł��邩�A��������ʂ܂łɒm�肽���B
���̂��߂ɂ��H��֍s�����Ƃɂ����B
�@
���A�N�Z�X��
�@����A�[���߂��A�a�k�n�f���t�o�����B
�ŁA�����A�A�N�Z�X����������A�����{�ȏ���������B
�[���ɂt�o�������Ƃ��l����Ȃ�A�����̂S�{�ȏ�Ƃ������ƂɂȂ�B
�����ł����A���v�ŁA�T�O�O�O�`�U�O�O�O���I
�������B
����A�w�{���{���̓��{�̋���x�Ƃ����e�[�}�Ō��e���������B
�܂��Ƀ{���{���B
���{�̋���́A������Ƃ���܂ŗ������B
����ɂ��ď������B
�܂肻�ꂾ�������̐l�������A���{�̋���ɁA��@���������Ă���l���������Ƃ������B
�@�������Ɂu�H�v�B
���ꂾ���ł͂Ȃ��B
�{�����]�|������B
�����Ȃ�A�܂��[���ł���B
���A���́A�c�����e���A����q�ǂ��Ɍ������āA�u���߂�v�u���߂�v�Ǝӂ鎞��B
�c�����e���A�u���߂�v�u���߂�v�Ǝӂ�Ȃ���A����q�ǂ�����ĂĂ���B
�@�����A�̂͐e���A�q�ǂ������������B
�e�ɂ��A�܂��͂��������B
���ꂪ�t�]�����B
���́A���q�►�̂ق����A�e�Ɍ������ĉ����B
�u�Q�A�R�O�N��������A���O�������Ă��I�v�ƁB
�i���̐�A�Q�A�R�O�N�������Ă���e�͂��Ȃ��I�j
���o��
�@��������������A�l�b�g�Ōo�σj���[�X���E�����Ƃ��ł���B
���T�i�W���Q�Q���E���j���j�́A�ǂ��Ȃ邩�B
���E�s���́A�[���x�𑝂��Ă���B
���̓��{�ɂ��Ă��A�ُ�ȉ~�����Â��Ă���B
�@��T���̗���������p���Ƃ���A���T���A��g���B
�悢�ޗ��́A�����Ȃ��B
���̂Â��́A�����������Ƃɏ����B
���i�q���C�o�X
�@���C�t�͖ڂ���A����n�߂��B
�i�F�ƌ����Ă��A������͍̂������H�̕ǂ����B
���K�ɂ͂Ȃ������A�����A���̑���Ȃ��B
�@�o�X�̃V�[�g�J�o�[�ɂ́A�u�i�q���C�o�X�v�Ə����Ă���B
�Ō���ɂ́A�g�C��������B
���Ȃ̕����L���B
���E�ɂP�O��B
����́A�S�O���B
����Ă���q�́A�������v�w���܂߂āA�P�X�l�B
�u�Ă���Ȃ́A�����R�ɂ��g�����������v�ƁA
���Ԃ���O�A�^�]�肪�����������B
���ċx��
�@���̉ċx�݂ɂ́A�R�x�A���s�������ƂɂȂ�B
�i�P�j�z�O���A
�i�Q�j��V�艷��A
�i�R�j�����č���̐ΐ쌧�E�H��B
�@�I�[�X�g�����A�Ƃ���C���l�������A��s�@���������z���邾���̃p���[�������Ȃ������B
���N�R���ɂ́A�F�l�̖����������邱�ƂɂȂ��Ă���̂ŁA�I�[�X�g�����A�֍s�����ƂɂȂ��Ă���B
�������Ƃ�����A�������Ă��ꂽ�B
���Δ����Ĕ����������ŁA����ɗ��m�I�B
���݂́A�����{�����s���̃y���M���u�b�N�X�ŁA�ҏW�������Ă���B
���E�����щ���Ă���B
�@���̂Ƃ���A��s�@�ɏ��\��́A���ꂾ���B
�����[�g
�@�ڂ̑O�ɍ����R�������Ă����B
���R���瑽�����̂ق��֔�����炵���B
���̎����A�X�̖X�͔Z��������Ƃ܂��B
�Ƃ������͍��ɋ߂��B
�Z�ΐF�B
�����ɉ_�Ԃ���R�����������A�������܂���͗l�����B
�@�_���A����Ɉ�i�A�Ⴍ�Ȃ��Ă����B
�����_���������Ă���ƁA�܂�Ŕ�s�@�̑�����O�����Ă���悤�B
������Ȃ��߂Ȃ���A�����A���̂��̂�Y���B
�@�c�c����A�������B
���[�g���������B
���́A�̖̂������̂悤�ɁA�{�B���c�ɏc�f���ċ�����������̂Ƃ���v���Ă����B
���A���ۂɂ́A���É����Č����։ꁨ���䁨����ƁA��ԘH���Ɠ������[�g�����ǂ��Ă���B
�@�m��Ȃ������I
���o�ςQ
�@��قǃl�b�g�ŁA�������̃j���[�X�����ǂ��Ă݂��B
���̂ЂƂA�k�C���ł��n�k���������Ƃ��B
���͕l���Ǝv���Ă������A�k�C���B
�@����Ƌ��i�S�[���h�j�ƃv���`�i���A����ɍ������B
�v���`�i���O�����T�O�O�O�~�A�����S�W�X�P�~�B
�����͗l�q���B
�s�������������ʂ̎������A�E���������Ă���B
���ɂ́A����������B
�����R
�@�o�X�͕��䌧�ɓ������c�c�炵���B
���K�B
�n���o�X��Ђ̎�ɂ���a�E�c�A�[���A�͂邩�ɉ��K�B
������ׂ�ȃI�o����������Ȃ��B
���邳���K�C�h�����Ȃ��B
�Ȃ́A�K���K���B
�@���C�t�͐�قǂ܂ŁA�����̖{��ǂ�ł����B
���͂P���ԂقǁA�������B
���ɂ��A���낢��Ȏd��������B
���A�����������@���A�������v�w�ɂ́A�������Ă���B
�@�킴�ƃV�[�Y�����͂����A�o�X���d�Ԃňړ�����B
�h�́A�l�b�g�őI�ԁB
�ړI�n�́A�P�ł��イ�Ԃ�B
����ł������́A�a�E�c�A�[�̔��z���x�B
�@
�@���A�{���̂Ƃ���A���������ł͂Ȃ��B
�����ŗ������Ă���Ƃ����A���̖��������y�����B
�܂��Ɋw���C���I
���ЎR��
�@�܂��܂������Ȃ��Ă����B
�o�X�̃G���W�������A�Â��ɏ��̉����狿���Ă���B
���܍��Ȃ��A�����݂ɃS�g�S�g�Ɨh���B
������̂ق��ŊP������l�ȊO�A�q�̋C�z����Ȃ��B
�@�c�c�o�X�́A���������u���O�v�ɓ�������Ƃ����B
���������A����ȃA�i�E���X�����ꂽ�B
�u���O�i���܂�����j�v�B
���Ƃ������Ȓn���ł͂Ȃ����B
�@�c�c�Ƃ������ƂŁA�ډ��A�v�l�͂̓[���B
�����ɉ��������������Ƃ�����͂��Ȃ̂ɁA���ꂪ�]�݂��̒��ɗN���Ă��Ȃ�
�����Č����Ȃ�A���x�����A�V�^�p�\�R���B
�P�O���̒a�����ɂ́A��ɓ��ꂽ���B
�b�o�t�́A�R�E�S�O�f�g���ȏ�B
�R�E�U�O�f�g���Ƃ����̂��A����B
�@�c�c���C�t���u�����A�C���I�v�ƌ������B
����ƍ���ɊC���L�����Ă����B
���{�C�B
���̉��ɁA�u�ЎR�Áv�Ƃ����������W�����������B
���e�P�T
�@���肩��A������Ȃ��W�F�b�g�퓬�@�������オ���Ă����B
�e�P�T�A�g���L���b�g�ł���B
�l�������ь����A���̗��K�@�Ƃ͔��͂��������B
�S�[�Ƃ��������܂����������A�o�X�̒��܂ŕ������Ă����B
�@�����͓��{�̖h�q�A�őO���B
���̏������ƁA�o�X�́A�u�k�����q�v�Ƃ����Ƃ���ŁA��܂����B
�q�́A��������Ȃ������B
���o������E�C
�@�O�ɏo��B
�l�ɉ�B
����ŁA����܂Œm��Ȃ��������E������B
�@�]�݂��̊������A�܂�{�P�h�~�̂��߂ɂ́A�����ւ�d�v�ł���B
�ƂŃS���S�����Ă������Ƃ����C�������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B
���A����ł͂����Ȃ��B
�����Łu�o������E�C�v�B
�����O�A����ŏo������l���A����Ȍ��t�������Ă��ꂽ�B
�@����Ɏ��Ă��邪�A�ŋ߁A���́A�悭����Ȃ��Ƃ��l����B
�@���Ƃ��Β��A�ӂƂ�̒��Ŗڂ��o�܂��B
�N���オ��ɂ́A�܂����������B
���A����ł��N���オ��B
�u���̂܂܉��ɂȂ��Ă���̂��A�R�O���B
�������E�H�[�L���O�}�V���̏�ŁA�����̂��A�R�O���v�ƁB
�@���̂Ƃ��S�̂ǂ����ŁA�ӂƁA�u�N���オ��E�C�v�Ƃ������t���l����B
�E�C���o���āA�N���オ��B
�ق��ɂ����낢�날��B
�@���X�֍s���B
���̂Ƃ����A���̖{�����ǂ����ŁA�����B
���A���������Ď����Ɍ�����������B
�u�����E�C�v�ƁB
���@���Ԃ�
�@�܂�l�Ԃ́A��{�I�ɂ́A�ӂ��ҁB
���炭�l�Ԃ͉��̎��ゾ�������납��A�����ł͂Ȃ��������B
�̏�ŁA�a��H�ׂ邾���̐l���B
���Ƃ͏I���A�Ђ����璋�Q�B
������l�ԂɂȂ��������A�y�����邱�Ƃ����A�l���Ȃ��B
�u�Ɋy�v�́u�y�v���A�����\���Ă���B
�@������u�o������E�C�v�Ƃ����̂́A���������ӂ��S�Ɠ����E�C�Ƃ������ƂɂȂ�B
�Ƃ��Ɏ��̂悤�ȁA�ǂ����ΐl���|�ǂۂ��A����𐫏�Q�ۂ��l�ԂɂƂ��ẮA�������B
�v�����ė��ɏo��B
���������ӂ��S��@���Ԃ��B
�ނ��������b�͂��Ă����A���̂ǁA�ӂ��S�Ɠ����B
���ꂪ�E�C�B
�����i����j
�@�����Ƃ����Ԃ̂S���Ԃ������B
�u���͕В��v�ƕ\�����ꂽ�B
����s�C�`�̔ɉ؊X�B
�w������́A�悭�V�B
���A���i�͈�ς����B
�w������̖ʉe�́A�ǂ��ɂ��Ȃ��B
�ߑ�I�ȃr���ɂ���ꂽ�X�B
�@���A�������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B
�ق�̏��������A�S�����̂��������B
���̒��ɂ͂S�N�Ԃ̎v���o�����݂���ł���B
�o�X�́A���������A�Ґ��n��͂��B
�����g�����d�����đ҂B
�@�n���[�A����B
�Ґ삾���́A�w������̂܂܂������B
������
�@����́A���̐̂́A�w���̒��������B
�ǂ��֍s���Ă��A�w���������B
�ڂ������B
�������̋���̋����w�̊w���������B
���̋���隬�ɂ������w�ɂŁA�S�N�Ԃ��߂������B
���A���́A�����w��������ǂ��o����A�p�ԂƂ����Ƃ���Ɉړ]�����B
�ǂ��ɂł�����V����w�̂ЂƂɂȂ��Ă��܂����B
���R�̂��ƂȂ���A���x�����������i����I�j�B
�@�������́A�����V���̋���Ƃ����B
�@�����A���܂��܂m�g�j�̑�̓h���}�ŁA�O�c���Ƃ��e�[�}�ɂȂ����B
���ꂾ���ł͂Ȃ����A����隬���A����s�͊ό��n�ɂ��悤�Ƃ����B
���̂��߂ɋ����w���A����隬����ǂ��o�����B
���A����͐��E�̏펯�ł͂Ȃ��B
�@���E�̑�s�s�́A�s�̒��S���ɍō��w�{��u���B
�u�m�v�̕{��u���B
�����w�A�����{������w���ɂ�����܂ł��Ȃ��B
���ꂪ���̎s�̌ւ�ł�����A�V���{���ɂ��Ȃ��Ă���B
���̊w�{���A���S�̂̒m�I�����������グ��B
�D����������Ȃ�A���{��������B
����s�́A�D����I�сA���{���̂Ă��B
���̌��ʂ��A���B
�@����s�́A�ό��s�s�Ƃ��āA�u�m�v���̂āA���������B
�c�c�����l���s�Ɉڂ�Z�Ƃ��A���͂��̕������̂Ȃ��ɋ������B
�l���s�́A�H�Ɠs�s�B
�Q�O�N�قǑO����A�u���y�̒��v�Ƃ��Ĕ���o���Ă��邪�A���Ƃ��Ƃ́u�y��̒��v�B
�u���y�v�Ɓu�y��v�Ƃł́A�u���w�v�Ɓu����@�v�قǂ̂�����������B
�@���̕l���ɏZ��ŁA�S�O�N�B
���x�͋���ɗ��Ă݂�ƁA���̕l���Ƃ���قLj��Ȃ��̂ɁA�����B
�t�̗���ŋ����B
����قNj����������u���v�́A�����Ȃ��B
�l���������s�s�ɂȂ����Ƃ͎v���Ȃ��B
�܂肻�̕������A����́A���������B
�@�ŁA�̐S�̊ό������́A�ӂ����̂��H
�����́A�u�m�n�I�v�B
�������̒��ɂ́A����s�����ɋ߂��̂�����B
�ΐ쌧���ɓ������̂�����B
�݂ȁA���ɂȂ��Ă��������Ă���B
�@�u�܂������̎��s�������v�ƁB
���T���_�[�o�[�h�P�R���i����A�P�R�F�O�R���j
�@����̓T���_�[�o�[�h�P�R���i���}�j�ŁA�H��܂ŁB
�u�T���_�[�o�[�h�v�Ƃ������O���悢�B
�Ȃ������B
���A�ǂ��l���Ă��A�k���𑖂��Ԃ炵���Ȃ��B
�u�Ґ��P�R���v�Ƃ��u�Ґ�P�R���v�Ƃ��B
�����������O�̂ق�����������āA�悢�B
�ǂ��ł��悢���Ƃ����c�c�B
�@�H��܂ł́A�S�O���B
�w������ɂ́A�@�����k���̏����Ƃ��āA�����̂悤�ɒʂ����B
�u�����v�Ƃ����Ƒ傰���ɕ������邩������Ȃ����A�v����ɃC���^�[���̂悤�Ȃ��́B
��w�̋����Ƃ�������ɒʂ����B
�s���Ή������v���o�����낤���A�ʐ^���������A�c���Ă��邾���B
���ƂȂ����̂́A�ǂ����̐_�Ђ̎������B
���̂Q�K�B
�c���Ă���ʐ^�́A���̐_�Ђ̑O�ŎB�������́B
�@�H��o�g�̗F�l�������͂��B
�r�g�N�Ƃ������O�ł͂Ȃ��������B
���w������
�@����ł̊w������́A���̂��Ƃ̃����{������w�ł̊w������̉A�ɉB��āA�L���̒��ł͂�����ł��܂��Ă���B
�����{������w�ł̊w���������A����قǂ܂łɋ������Ƃ������Ƃ��B
���A�������l����B
�@�������̂܂܁A�܂��߂Ɂi�H�j�A�����w�𑲋Ƃ��A���Ѓ}���ɂȂ��Ă�����A���͂ǂ��Ȃ��Ă������낤���A�ƁB
�Q�N�قǑO�A������ɏo���Ƃ��A�u�ɓ����������N�܂ŋ߂܂��āc�c�v�ƌ������F�l�������B
��������ɓ��Ў����ɍs�������Ƃ̂��钇�Ԃ������B
���̒��Ԃ����Ȃ���A���͂����v�����B
�u�����A�����Ȃ��Ă������낤�ȁv�ƁB
��Ќ����̊�Ɛ�m�B
�o���o�������āA��N�ސE�B
���A������z���͂����Ă��A����ȏ�̂��Ƃ����ɕ�����ł��Ȃ��B
�����́A�����̃o�J������
�@�u���v���A�˂Ɂu���ʁv�ł���Ƃ���Ȃ�A�ł́A����ł̂S�N�Ԃ́A���������̂��Ƃ������ƂɂȂ�B
����͂��傤�ǃ{�P���V�l������Ƃ��̎����Ɏ��Ă���B
����Ȑl�ɂ��A���ꂼ��A�����̉ߋ����������͂��B
���A�{�P��ƁA���������ߋ����A�ǂ����������ł��܂��B
�ςݏd�˂Ă����͂��́A�l���̔N�ւ������Ă��܂��B
�@���̎��ɂ��Ă��A�������B
�w������̎��́A�������Ƀo�J�������B
�������A�����̃o�J�B
���A���̎����A���̃o�J���甲���o�����Ƃ����ƁA����͂Ȃ��B
�ނ��낳��Ƀo�J�ɂȂ����̂�������Ȃ��B
�{�P�V�l�A�����O�B
�@�ƂȂ�ƁA�u����ł̂S�N�Ԃ́A���������̂��v�Ƃ������ƂɂȂ�B
�A�E�̂��߂́A�ꗢ�ˁH
�����l���邱�Ƃ͂��݂������Ƃ����A���ɂ����炸�A�����̊w���݂͂ȁA�����l���Ă����B
�������͂����A�����ɒǂ����Ă��Đ����Ă����B
���̂S�N�Ԃɂ��Ă��A�������B
�u��w�֓���̂́A���̐�̏A�E�̂��߁v�ƁB
�������������A�u���v�����̂́A�ق��Ȃ�Ȃ��A�����{�����ł̂��Ƃ������B
���u�����A���₾�I�v
�@���͂��̃����{�����Ƃ������ŁA���܂�Ă͂��߂āu���R�v�Ƃ������̂�m�����B
�{���́A���R���B
�����炱���A�O�䕨�Y�Ƃ�����Ђ��A�������Ƃ��Ȃ��A��߂邱�Ƃ��ł����B
�u�����A���₾�I�v�ƁB
�@���̉�Ђł́A�����v�����N���ƂɁA���ѕ\�̂悤�ɔ��\�����B
����ł��̎Ј��́u�́v���]�������B
�����m�����Ƃ��A���́A�u�����A���₾�I�v�ƁB
�@���A�������̂܂܃����{������m��Ȃ��ŁA���{�̉�Ђɓ����Ă����Ƃ�����c�c�B
���̒��Ԃɂ͈������A�S��A�]�[�b�Ƃ���B
���͂��̈ӎ����Ȃ��܂܁A��x�����Ȃ��l�����A�_�ɐU���Ă����B
����B�i�ق����j�@
�@��Ԃ́A���ꂿ������Ԃ�҂��߁A��B�i�ق����j�Ƃ����w�ɒ�܂����B
�T���̒�ԂƂ����B
���тꂽ�c�ɒ��i����I�j�B
�����S�z�ɂȂ��Ă����B
�u�H��s�͂������傤�Ԃ��낤���H�v�ƁB
���̂S�O�N�ԂŁA����Ȃ�ɔ��W���Ă��邱�Ƃ��肤����c�c�B
�@���X�g�������Ȃ��悤�ȓc�ɒ���������A�ǂ����悤�H
��قǃ��C�t�ɁA�u�a�q����ɂ���悩�����v�ƌ������B
�a�q����ւ́A���x�����܂������Ƃ�����B
��͂�@�����k���̏����Ƃ��āA���̒��֍s�����Ƃ��̂��Ƃ������B
�ق��ɁA�\�o�A��F�i�����j�A�x���i�Ƃ��j�ȂǂȂǁB
�\�o�����ŁA�s���Ȃ������Ƃ���͂Ȃ��B
�ċx�݂ɂȂ邽�тɁA���k�Ƃ����̂ŁA�e�n�Ɉꔑ�����Ȃ���A�\�o����������B
�@�c�c���A�����Ȃ�A�Z�@�S�������ׂẮA�����܂��Ȃ��A�⍓�ȑ��k���B
�����I�ɑ��k���A�����I�ɑ��k�ɓ����Ă����B
������v���ƁA����Ȋ���������B
����������
�@�������\�o�͂悢�B
�ق��̒n���ɂ͂Ȃ��A�Ɠ��̕������B
���̐̂́A�l���ʂ�Ȃ��A���̂ւ��n�B
�Ǔ��B
����x�R���ʂ֍s���l�͂�����������Ȃ��B
�������\�o�܂ʼn��l�͂��Ȃ������B
�@�����玄�̂悤�Ȃ����Ȃ��w���ł��A�A�\�o�𗷂���ƁA�y�n�̐l�����́A�w���̂��Ƃ��A�،h�̔O�����߂āA�u��������v�ƌĂ�ł��ꂽ�B
����Ȃʂ����肪�A���̔\�o�ɂ͎c���Ă���B
���R�X���A�C���H��i�t�e�n��فj
�@�H��֒����ƁA�����A�u�R�X���A�C���H��v�i�t�e�n��فj�ցB
�u�R�X���A�C���H�v�B
�u�b���������@�h�������i�F���̓��j�v�̂��ƁH
�l�[�~���O�������B
����ł͋L���Ɏc��Ȃ��B
�ό��q���W�߂��Ȃ��B
��͂�Y�o���A�u�t�e�n��فv�̂ق����A�悢�̂ł́H
�@���A���́A���Ȃ茩���������������B
�F���D�̓W���������h�B
���炵���B
�{�C�x�𐏏��Ɋ������B
���A�̐S�̂t�e�n�e���A�����H
�܂��R�K�ł́A�v���l�^���E�����̊ȒP�ȉf��������Ă��ꂽ���A������̓K�b�J���B
�܂�Ȃ��M���V���_�b�ƁA�n�b�v���]�����̏Љ���B
���A�S�̂Ƃ��ẮA�������Ȃ����t�e�n�t�@���Ȃ�A��x�͖K��Ă݂鉿�l�͂���B
�i���{�ɂ́A�����ȊO�ɁA����炵���ꏊ�Ȃ����Ƃ����邪�c�c�B
���̖�Ǐ��ꎁ���A���_�ْ��ɂ��Ȃ��Ă���B�j
�@�ŁA�����̏h���z�e���́A�u���K�[�f���z�e���v�B
���}�ɗ\�����ꂽ�B
����������āA�H���̗p�ӂ͂ł��Ȃ��Ƃ̂��ƁB
�@�ŁA�w�O�̃^�N�V�[�^�]��ɕ����ƁA�u�ڂ��ڂ��v�Ƃ����X�����߂Ă��ꂽ�B
�u�ڂ��ڂ��v�Ƃ����̂́A�u���v�̂��ƁB
�u���̂�����ł́A����ʂ̂��Ƃ��A�ڂ��ڂ��ƌ����܂��v�ƁA�X�̏����������Ă��ꂽ�B
�@���́u�ڂ��ڂ��v�ŁA�[�H�B
�T�V�~�̐��荇�킹�A�V�Ղ�̐��荇�킹�A����Ɓu�̂Ǎ��v�Ƃ������̏Ă����B
��̓��̓��������X�`�A���͂�A���r�[���c�c�B
���߂ĂS�R�O�O�~�B
�����I
�v���X�A�������������B
�u�������{��I�v�ƁA���C�t���喞���B
�@���肪�Ƃ��A�u�ڂ��ڂ��l�v�B
����Ǐ��ꎁ
�@��Ǐ��ꎁ�̂悤�ȗL���l�ɂ��Ȃ�ƁA�u���������������Ƃ�����v�ƁA�����o��l�́A�����B
�������̂P�l��������Ȃ��B
��������ǎ��̂ق��́A���̂��ƂȂǖY��Ă��܂��Ă��邾�낤�B
���������������A�v���o���Ă��炦�邩������Ȃ��B
�@�l���ŁA�j���������Ă����f�搶�̂Ƃ���ʼn��x��������B
�����̃z�e���E�j���[�I�I�^�j�ł��A���x��������B
�t�e�n��ڌ������Ɠd�b�œ`�����Ƃ��A�ʐ^���Q�O�`�R�O�������Ă��ꂽ�B
�I�[�X�g�����A���̎����^�o�R�𑗂�ƁA���Ԃ��ɂƁA���{�e���r�̃��S�̓������K�X���C�^�[�𑗂��Ă��ꂽ�A�ȂǂȂǁB
�@�ق��Ɋo���Ă���̂́A���鎖���Ɋ������܂�A��ǎ����j���[���[�N�֓����Ă������Ƃ��̂��ƁB
�d�b�ŁA�u���̂������l���������v�ƁA�j���[���[�N����A�������ꂽ�B
���́u���̂������l�v�Ƃ����̂��A���̃����E�Q���[�������B
�����͂t�e�n�f�B���N�^�[�Ƃ������́A���\�̓f�B���N�^�[�������i�u�P�P�o�l�v�j�B
�@��x������Ǝv���Ă��邪�A���̂��ƂȂǁA�Y��Ă��܂��Ă��邾�낤�B
�����́A������ǎ����A�Ⴉ�����I
���̒����g�����`�R�[�g���A�ǂ������킯��������ۂɎc���Ă���B
���̖�ǎ����A���̐��E�ŁA����قǂ܂ł̐l�ɂȂ�Ƃ́A���͖��ɂ��v���Ă��Ȃ������B
���O�����^
�@�Ƃ���Łu�t�e�n�v�ƌ������蕨�i�H�j�̂����l���ɂ͋����B
�܂��ɁA���ł�������B
�`���A���܂��܁B
�l�Ԃ̏�蕨�ƌ����A�����ԁB
��s�@�B
�ő���I�ɁA���́u�`�v���܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���B
���A�t�e�n�ɂ��Ă����A���ꂪ�ł��Ȃ��B
�@�ٓ��ł�������p���t�ɂ��A�u�t�e�n�̊�{�I�Ȍ`�́A�傫��������ƂP�Q��ނɕ������邻���ł��v�Ƃ���B
���C�t�Ǝ����ڌ������̂́A���̒��ł��A�u�O�����^�v�Ƃ������ƂɂȂ�B
�܂�u�[�������^�B
��s�p�^�[�����Љ��Ă��邪�A�����p���t�ɂ��A�P�W��ނ�����Ƃ��B
�v����ɔ�ѕ������`�����`���Ƃ������ƁB
�@�ł́A���̐��̂́A�����H
��͂蓯���p���t�ɂ��A
�i�P�j�R�������
�i�Q�j���R���ې��i�v���Y�}���j
�i�R�j�G�C���A���E�N���t�g���i�F���l�̏�蕨���j
�i�S�j���m�̐������́A�S������Ƃ����B
�@�����͐s���Ȃ��B
�����K�[�f���z�e���i�H��s�j
�@�痢�l�i����͂܁j���h���C�u�������ƁA�z�e���ɓ������B
���H�݂̂ŁA�X�U�O�O�~�i�Q�l���j�B
�ǂ������g�����́A�Â��ŗ����������z�e���B
�@���C�t�́A���炭����炵�Ă������A���́A�x�b�h�̏�Ŗ����Ă���B
�܂��O�͔����邢�B
�������ꎞ�B
�@���Ƃŋ߂��̉���ɍs�����ƂɂȂ��Ă��邪�A�����A�s���Ȃ����낤�B
���͖{��ǂ�A�p�\�R����@�����肵�Ă���ق����y�����B
�������Ď����́u���v���߂����B
������
�@�b���o���o���ɂȂ�A�܂Ƃ܂�Ȃ��B
�e�[�}�Ƃ������A�œ_����܂�Ȃ��B
�Ƃ��ǂ����[�����̂�������A�l�b�g�ł��������̃T�C�g��ǂ肵�Ă���B
���A�ǂ���ǂ�B
����ɂ��ď��������Ƃ��ɂ́A�r���r���Ɠd�C�V���b�N�̂悤�Ȃ��̂�������B
���A���́A���ꂪ�Ȃ��B
���₩�B
���a�B
������ԁB
�y�������������邪�A�����Ɍy�����ɂ�����B
�����́A���Q�����Ă��Ȃ��B
���̂����H
�ŁA�����痢�l�i����͂܁j�ɂ́A����Ȏv���o������B
�@���h�̐�y�ƃh���C�u�����Ă��āA���̂ɑ������B
�Ԃ��Ɖ��]�����B
�L���̒��ł́A�R�]�قǂ����Ǝv���B
�Ŏ����̑̂��N���N���Ɖ���Ă���̂��o���Ă���B
�@���̂��Ƃ��قǃ^�N�V�[�̉^�]��ɘb���ƁA�����������Ă��ꂽ�B
�u�g���A�Ƃ��ǂ��i��������ĂˁB���̒i���Ƀ^�C���������ƁA���]���邱�Ƃ������v�ƁB
������w�Q�N���̂Ƃ��̂��ƁB
��y�́A�R�N���������B
��y�́A����Ŕw����܂����B
���͕s�v�c�Ȃ��ƂɁA�܂������̖����������B
�����s
�@����̉ċx�݂ł́A�P�������ɁA�R�̗��s�������B
�R���S���̗��s���A�R�ɕ������Ƃ������ƂɂȂ�B
���ꂼ��̗��s�ɂ́A���ꂼ��̐��i������B
�@���䌧�̉z�O���֍s�����Ƃ��ɂ́A�u���͈�l�ڂ����v�Ƃ������Ƃ��A�����v���m�炳�ꂽ�B
���Ɍ��̏�V��֍s�����Ƃ��ɂ́A�̂̎����ɉ���悤�ȉ����������o�����B
�܂�����A���̉H��֗����Ƃ��ɂ́A�u�����v�Ƃ������́A�u�Ñ��֖߂��Ă����v�Ƃ������o�ɂƂ��ꂽ�B
�^�N�V�[�ɏ���Ă���Ƃ��A���܂��܁u�x���s���v�Ƃ����o�X�Ƃ��ꂿ�������B
�������C�Ȃ��A�u��������x���i�Ƃ��j�ւ��s����̂ł����H�v�ƕ����ƁA�^�N�V�[�̉^�]��́A�����Ă����������B
�u�x���i�Ƃ��j�Ƃ����ǂݕ���m���Ă������q����́A�͂��߂Ăł��v�ƁB
�@�\�o�����Ƃ��������́A���ɂƂ��ẮA�������������ł���B
���d��
�@���������A�d�����n�܂�B
�u����낤�v�Ƃ����C�����ƁA�u�������傤�Ԃ��ȁv�Ƃ����C�����B
���̂Q�̋C�������A���G�Ɍ�������B
�̗͓I�ɂ͉��Ƃ��Ȃ�B
���������̑�s���B
���̂����W���W���ƁA���̉e�����o�Ă���͂��B
���N�x�i�Q�O�P�Q�N�̂R���܂Łj�́A���Ƃ��Ȃ邾�낤�B
���������̐悪�ǂ߂Ȃ��B
�@�ŁA���C�t�́A���������̂Ȑ��i������A�������������Ă���B
�u�Ԃꂽ��A�I�[�X�g�����A�ւł��s���܂��傤��v�ƁB
�@�ǂ������̋������Ԃ��̂��A�y���݂ɂ��Ă���l�q�i�H�j�B
���������Ƃ�������B
�u���܂ŁA��x���܂������Ƃ��Ȃ��A�����܂ł���Ă����̂�����A���ӂ��Ȃ����Ⴀ�v�ƁB
�܂�u�������イ�Ԃ�d�������Ă����B����߂Ă������v�ƁB
���邢�́u���Ȃ�����N�ސE������H�v�ƁB
�@���A���̎��ɂ́A�d�������������ɂȂ��Ă���B
���̐����������A����̂Ă�킯�ɂ͂����Ȃ��B
���Ƃ��ẮA���ʒ��O�܂ŁA�d�������Ă������B
�ł���s���R���Ƃ������ɕ����������B
�I�[�X�g�����A�ւ��s���������A�u�s���ĉ�������H�v�ƍl�����Ƃ���A�ӗ~���A�X�[�b�ƈނ��Ă����B
�@�Ƃ��������A�������Ď��̉ċx�݂́A�I���B
���A�܂�������߂��킯�ł͂Ȃ��B
�u�����̖���A�ǂ����̉���֍s�������v�Ɛ���������ƁA���C�t�́A�u�������`�H�v�ƁB
�C�̐i�܂Ȃ��Ԏ����A�Ԃ��Ă����B
�@�c�c�������ė��s���ł���̂��A���̂����B
�悭�āA�������N�B
���́A������قǁA���������𗷍s���Ă��������B
���W���Q�R��
�@���A�U���A�N���B
���͂ق��ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��A�ߌ�P�O���ɏA�Q�B
�W���ԁA���������ƂɂȂ�B
��x�A�g�C���ɋN�������A���ꂾ���B
�@�c�c�Ƃ������ƂŁA�����́A�C���A�u���B
�]�݂��̓������A�܂��܂��B
�������ăp�\�R���̃L�[�{�[�h��@���w���A�y�₩�B
�悩�����I
����ƒ��q���߂��Ă����B
�����J
�@�H��̒��́A���J�Ŏn�܂����B
�H���͂W������B
�P�O������̓d�Ԃɏ��A����ցB
����o�X�Ŗ��É��ցB
�قڃm���X�g�b�v�B
���v���Ԃ́A�S���ԁB
�V�����Ɠ��}�����p�����́A���Ԃ͂�����B
�����������́A���z�B
�}�����łȂ���A�����o�X�̂ق����A�y�B
�@�u�z�e������H��w�܂ł́A�^�N�V�[���ȁv�ƁA���A�ӂƁA����Ȃ��Ƃ��l�����B
�����̊O
�@�z�e���Ƃ����Ă��A�r�W�l�X�z�e���H
�����ȃr�W�l�X�z�e���Ƃ����������B
�i�t�����g�ŕ�������A�S���t�N���u�̃N���u�n�E�X�������Ƃ̂��ƁB�j
���̒��ɁA�|�c���ƌ����Ă���B
�ڂ̉��ɂ͍r�ꂽ�y�n�B
���̌������ɂ́A�����Â��Ă���B
�ꌬ�����Ƃ����邪�A�����ӂ��̖��ƁB
�@�E�̕��p�ɐ痢�l������͂������A��������͌����Ȃ��B
����͉����ɒႢ�R�X�����������A�����́A�����_�ɕ����A����������Ȃ��B
���������ς��ɊJ�����B
�ĂƂ����̂ɁA�����������A�T�[�b�Ɛ�������ł����B
�ߌォ��́A�܂��ҏ��ɋt�߂肷��Ƃ����B
�����Y�ꂽ���A����́A�S���I�ɁA�P�O�����{�̋G�߂������Ƃ����B
������āA�u�P�O�����āA�����Ȃv�ƁB
�@�����Ŏ��ƃ��C�t�̌��_�B
�i�P�j�V�[�Y���I�t��I��
�i�Q�j�q�̏��Ȃ����فi�z�e���j��I��
�i�R�j�قǂقǂ̋����̂Ƃ���ɂ��閼����I��
�@�H�ɂȂ�A���s�V�[�Y���B
�y���݂��҂��Ă���B
���H�������
�@�z�e������w�܂ł͕������B
�r���A�X�ǂŋ���̗F�l�Ƀn�K�L���o���B
���������J�B
���C�t���P���������B
�����P���������B
���傤�ǂS�O���قǂŁA�i�q�H��w�ɁB
�@�X���Q�U�����̋���s���B
�ݍs��ԁB
�Ȃ͂����Ă����B
�@�p�\�R�����J���ƁA�܂����[����ǂށB
�Â��ăj���[�X�B
���̂Ƃ���܂��C�ɂȂ�̂��A�l���B
�u�l���͂������傤�Ԃ��H�v�ƁB
�n�k���߂��B
���ꂪ�C�ɂȂ�B
������ꂽ�Q�O�N
�@���������n���֗��Ă݂�ƁA�u����ꂽ�Q�O�N�v�̈Ӗ����A�悭�킩��B
���̂S�O�N���Q�ɕ�����B
�ŏ��̂Q�O�N�A���̓��{�́A�{���̂��Ƃ��ω������B
���������̂Q�O�N�A���̓��{�́A�����Ŏ��Ԃ��~�߂��܂܁B
�@���̓ݍs��Ԃɂ��Ă��A�����������T�r���炯�B
���K���X�͉��ꂽ�܂܁A�����܂��Ă���B
���A�������������~�߂��̂��A�u�l�v�B
�@�����A�ʘH���͂����Α��̐ȂɁA�Q�l�̏����������吺�Řb������ł���B
�Б��͍��Ȃɂ������܂܁B
����̓X�J�[�g���A�傫���߂��肠���Ă���B
�P�l�́A�T�O�ΑO�B
�����P�l�́A�U�O�ΑO��B
�܂��Ɂu���v��Y�ꂽ�I�o������B
�i�i�����i���Ȃ��B
���{�l�Ƃ������́A�y�����Z���B
�\�o�̓y�����Z���B
�@�ǂ����ď����́A�����Ȃ�̂��H
���������l�����ɂ��A�Ⴍ�Ĕ������Ƃ����������͂��B
�����������N���������āA�����Ȃ�B
�ǂ����āH
�@�c�c���{�����Č����ɒǂ����߂��u�ɉh�v�Ƃ͉��������̂��B
���邢�͕��~�̒Nj��ɂ����Ȃ������̂��B
���̌��ʁA�܂肻�ꂪ�I������Ƃ��A�c�����̂́A���~�����B
���̂Q�O�N�ŁA���̕��~�������A����͂���ĕ\�ɏo�Ă����B
���������I�o������̉��p�����Ă���ƁA����Ȋ���������B
���ΐ쌧
�@�d�Ԃ͂̂ǂ��ȓc���n�т𑖂�B
�ЂƂ������̂́A�悪�ڗ����ƁB
��w���ƂɁA��n������A���H�����ɕ悪�����B�ꂷ��B
���Ƃ͎G�R�Ƃ����X���݂ƁA�G���B
���H�������A���H�������A�G�����炯�B
������Ƃ����n�ł��A�đ���������A�r�����ɂȂ��Ă���B
���N�O�A�ΐ쌧���ɋ߂�F�l���A�����������B
�u�ΐ쌧�́A�n��������v�ƁB
�@���̕n�������A�����P�O�N�ŁA���������Ђǂ��Ȃ����H
����Ȉ�ۂ��������B
�i�܂������Ă�����A���߂�I�j�@
������
�@�c�c�Ƃ������ƂŁA����́A�����ΐ쌧�H��s�܂ł���Ă����B
���Ƃt�e�n�ɂ��Č����A�V���������́A�Ȃ������B
�Ñ�j�Ƃt�e�n�̊W�A�Ñ㕶���Ƃt�e�n�̊W�A����ɂ́A�ނ�͂�����A���̖ړI�������āA���̒n���ւ���Ă����̂��c�c�B
���Ƃ��V�����[�������A����i�����V���I�j�����Ƃ̊W�ȂǁB
���������Ƃ���܂ŁA���ݍ���œW������ƁA���s�����{������̂ł́H
�@�F���D�i�t�e�n�ł͂Ȃ��j�̓W�������W�`�X���B
�t�e�n�Ɋւ��Ă����A�Q�A�R�̓W�����ƁA���Ƃ̓p�l���ʐ^�����B
���̂����肪�A�������������Ă���펯�̊����ƍl���Ă悢�B
�t�e�n�I�����[�ƂȂ�ƁA�J���g���i�����M���j����댯��������B
��͂�t�e�n�ɂ��ẮA�قǂقǂ̂Ƃ���ŁA�قǂقǂ̃��}�����y���ނ̂��悢�B
�[����͋֕��B
���̓_�A��Ǐ��ꎁ�́A�����悢�B
�c�̂�g�D�Ƃ́A����������Ă���B
�@����̗��s������ƁA�����������ƂɂȂ�B
�����������L��
�@���É�����́A���S�d�Ԃɏ�芷�����B
���}�A�L���s���B
���������Ȃ��A�y�������������B
���������e�́A�Q�R�y�[�W�i�S�O�����R�U�s�j�B
�܂��܂��̐��ʁB
�@�p�i�\�j�b�N�А��̃��b�c�E�m�[�g���ق����I
�s�n�r�g�h�a�`�̂l�w�ł́A���͕s���B
�o�b�e���[�`�F�b�N������ƁA�u�Q�P���ŁA�P���ԂR�X���v�ƕ\�����ꂽ�B
�܂�o�b�e���[�̎c�ʂ́A�Q�P���B
�c��A�P���ԂR�X���B
���ۂɂ́A���ƂR�O��������ƁA�x���\���������B
�@�c�c���̔]�݂��ɂ��Č����Ȃ�A�u�Q�O���A�V�N�v���ȁH
���ƂV�A�W�N��������A�g�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ�H
����Ȋ���������B
�i�͂₵�_�i�@�H��@�F���Ȋw�����ف@�R�X���A�C���@��Ǐ���@�t�e�n�@�\�o�ւ̗��@�͂₵�_�i�@�ΐ쌧�@�H��s�@���K�[�f���z�e���@�H��s�@���B�@�ڂ��ڂ��@�͂₵�_�i�@�ڂ��ڂ��@�H��@�������@�ڂ��ڂ��j
|
||
|
||
|
||

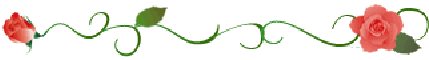

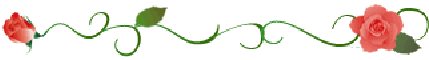
| |
��l�ɂȂ�����A���ɂȂ肽���H �Ƃ̐��i�Ɂu��l�ɂȂ�����A���ɂȂ肽���H�v�Ƃ����ƁA�����Ƃ�ł��Ȃ��Ԏ����Ԃ��Ă���B�ŋߕ������u�H�H�H�v�ȕԓ��̃����L���O�B ��O�ʁA�_�f�B�[�}���B �l�̂��Ƃ������O�܂ŁA�_�f�B�[�}��(��������j�j���ČĂ�ł����̂����ǁA����ɂȂ肽�����������Ƃ炵���B ���ʁA�C�[�T���̔ޏ��B �v���X�N�[���œ����N���X�̐e�F�̃C�[�T�����Ă����j�̎q������̂����ǁA�ނ́u�ޏ��v�ɂ��肽���̂��������E�E�B ���̐��ɂ͒j�ɐ��܂�Ȃ��琫�i�͏��A�Ƃ����l������̂����������A���i�͕��i�ʂɂ���n�̊����ł͂Ȃ��B�������ˑR���������˔��q���Ȃ����������ނ����������E�E�E�H�H ��P�ʁA�W�����A�̂��������B �������v���X�N�[���ňꏏ�̃W�����A���Ă������̎q������̂����ǁA�ޏ��̂����������Ȃ肽���Ƃ����̂��B���̂��������A��قLj�ې[�������炵���B���̒��ǂ�Ȃɂ�������Ă��Ȃ�Ȃ����̂�����̂ɁB |